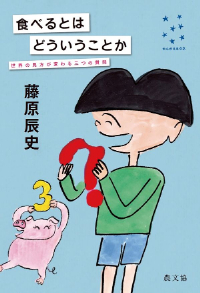〈書評〉解かずに読む共通テスト2022
2022.02.16
今年は1月15、16日の2日間にわたって大学入学共通テストが行われた。本との出会いは様々だが、入試問題での出会いはそのなかでもとびきりドラマチックなものだ。しかし、二次試験に向けて勉強を続ける受験生は、出題作品を振り返ってもいられないだろう。
この企画では今年の共通テストに登場した8つの作品を取り上げ、出題箇所を振り返りつつ作品そのものの書評を掲載する。受験生諸君の大学入試の思い出に、これらの作品との特別な出会いが加わる助けとなれば幸いだ。また在学生も、自分が受験した年の作品を振り返ってはどうだろうか。(編集部)
また、倫理では小説の『人類の子供たち』が引用され、将来世代への意識に関する設問が出された。なお、昨年度の世界史Bの『1984』に続き、2年連続でディストピア小説が登場した。
ひとつは「哲学」だ。一般に哲学といえば、実生活から縁遠い抽象的な思想を扱う学問がイメージされるだろう。その点で『食べることの哲学』という表題は、日常的な「食」と「哲学」の組み合わせがちぐはぐな印象を与える。しかし、本書がいう哲学はそうした一般的なイメージに近い。筆者の檜垣氏はフランス現代思想を専門とする哲学者であり、宮沢賢治の作品や人類学者レヴィ=ストロースの主張といった具体的な素材を用いて、食べるという行為や食べ物の根本を考察していく。この具体から抽象へと向かう過程は、人や世界の根底にある原理を突き詰める哲学の営みに沿った流れだといえる。
対して『食べるとはどういうことか』では、「哲学」を「世の中で当たり前とされていることを問い直すこと」「答えの無い問いについて考えること」と、より身近な営みとして捉えている。これは本書の内容のもとになった座談会で、筆者である藤原氏が12歳から18歳の学生たちに繰り返し語った考えだ。「哲学」を広く定義することで、日常の中にある食が学問の素材になりうること、さらには分野を問わず、ある問いについて根気強く追究することがいかに大切で身近なものなのかが、効果的に読者の心に響いてくる。
もうひとつのキーワードは「文化」である。ただし両方とも単なる食文化、つまり特定の民族や社会と結びついた食習慣を指しているわけではない。『食べるとはどういうことか』の中では、生物として人間が抱く食欲が満たされて初めて生まれる、食べる喜びを「文化」だと定義する。食に伴うポジティブな感情こそが、食べるという行為に栄養摂取以上の意味合いを与えているというのである。現代社会ではサプリメントやゼリー食品の開発が進んでいる。食事を手早く済ませようとする風潮を見直すうえで、この「文化」は重要な意味を持つ。
一方『食べることの哲学』では、「文化」は常に「自然」、すなわち人間がもつ動物的側面と対立する概念として登場する。料理という食文化は人間が自然環境に働きかけた結果生まれるため、食べることは「自然」と「文化」という対立する概念を結び付けるものだと主張している。そして多くの食文化でタブーとされるカニバリズム、いわゆる食人行為へと議論が進む。カニバリズムは単に文化の面から禁じられているだけではなく、複雑な自然との関わりがその根底にあるのではないかという問いが引き出され、宮沢賢治の作品がその問いを検討する素材として登場するのだ。
議論の展開は異なる2冊だが、どちらも個人的体験から出発して論を進めている点が興味深い。藤原氏は座談会の始めに、いままで食べたもので何が一番おいしかったかを学生たちに尋ね、食べるという行為には人間関係や風景が重層的に関わっていると示している。檜垣氏は自身のフランスでの食体験をもとに、「単調な」ヨーロッパ系の食とコクや旨みを重視する他地域の食を一貫して区別している。そのため、筆者の主張に必ずしも頷けるとはかぎらない。特にヨーロッパの食事を「味気ない」と言い切り、そのような価値判断を混ぜたまま話を進めていく檜垣氏の姿勢には疑問を覚える。
だからといって、その主張を検討するに値しないと切り捨てるのは間違いだ。藤原氏と学生たちが座談会で導き出した通り、食べることには人間のさまざまな感覚が関わっている。食を追究するうえでは、個人の具体的な体験こそが学問の種なのだと気づかされる。身近なものごとを突き詰めて考えを深めていく楽しさ、学問の根本にある喜びを実感できる2冊である。(凡)
主人公よだかは、外見を理由に周囲の鳥たちにばかにされる存在である。同じ名前を持つ鷹に名前を変えなければつかみ殺すと脅されたよだかは、自分の生に見切りをつけて遠く空の向こうへ去ることを決意するが、連れて行ってくれと頼んだ太陽や星々にも冷たくあしらわれてしまう。ひとり孤独に身を任せて地面に落ちようとした時、突如よだかは力を得てどこまでも高く飛び上がり、青く光る星になるのだ。
この話は、外見で他者を判断することを戒める道徳的な話として解釈されることが多い。それは、現代社会で顕在化するルッキズムの問題と重なる非常に重要なテーマである。確かによだかのモデルとなったヨタカは、賢治の描写通りのまだらな羽の色と耳まで裂けた平たい口を持つが、鳥にとっての美醜に疎い人間の目線では、それが美的に貶められる原因になるとはあまり思えない。美的感覚は、環境に依存した相対的なものである。
また、いじめの問題として本作を解釈するならば、遠くへ去ろうとするよだかを心配し引き留めた川せみの存在が重要になるだろう。鳥たちに散々に否定され、追い込まれて周りが見えなくなっている時にも、よだかの近くに味方はいたのだ。しかし、よだかはその存在に気がつくことができなかったし、川せみも、よだかの行動を変えることはできなかった。あと一歩、互いに歩み寄ることがどうしても難しい。
一方、今回の共通テストでは、よだかを取り巻く「食べるものと食べられるもの」の関係に焦点が当てられた。周囲にさげすまれ疎まれ続けたよだかは、自分の生に悲観的になり、どうしてこんな目にあうのかと運命を呪う。が、ひとたび風を切って空を飛べば、何もせずとも口に虫が入りそれを飲み込まずにはいられないのだ。自分の生命の意味を疑えば疑うほどに、その土台に存在する他の生き物たちの死が重くのしかかる。
自分が多くの生命を奪って生きていることを自覚したよだかは、深い悲しみに襲われ、誰も知らない遠くの空へ飛び立つ、すなわち、この世から離れることを決意する。このような描写には、賢治自身が抱いていた法華経信仰が色濃くあらわれているだろう。また法華経では、生命を持つもの全ては生まれながらに仏となる素質を持ち、信じて修行すれば皆仏になることができると説かれる。それだけを根拠に、星となったよだかの最後を仏になったものと理解するのは極端だが、あまりに人間らしい鳥たちの振る舞いやよだかの内面の葛藤には、万物に平等に仏性を見出す法華経の感性が見て取れる。
よだかが天にあげられて青く輝く星となる最後は、賢治にとっての、苦しむ者に対する本当の救いのあり方を示しているように思えてならない。賢治にとっての救済とは、敵が報いを受けることでも誰かに苦しみを理解してもらうことでもなく、苦しみを感じることのない、どこまでも美しく純粋なものになることだったのではないか。優しくも切ない賢治の信念がうかがえる作品である。(桃)
長年勤めた仕事を定年退職した主人公は、1人自宅で過ごす時間が増えた新しい生活に慣れることができず、今まで何気なく見過ごしていた家の様子に敏感になっていた。
題名の「庭」は自宅の庭ではない。数十年前に庭部分に子ども部屋を増築した結果、夫婦は庭を失っていた。その代わり、キッチンの窓から見える隣家の庭を眺めるようになった。
そんなある日、隣人の庭に白い小屋が造られた。どうやら、高校生になる息子のひとり部屋のようである。はじめ主人公は、両親や祖父母のいる母屋を離れて晴れて自室を持ったことを内心で祝福していた。しかし、次第に小屋の周りにベンチや看板など雑多なものが置かれていき、庭の風景の変貌を主人公が憂うる中、ついに「庭の男」――海外映画の立て看板らしきものに描かれた男、が現れた。自宅のキッチンの窓越しに目があう男の鋭い視線に、主人公は辟易する。ついにはキッチンにいない時にすら男の視線が気になって仕方がなくなってしまった。
主人公は妻にこのことを話すが、妻は庭の男のことをさして気にしていない。主人公だけが異常に敏感であるのは、庭の男が突如現れたという直接要因よりも、退職して家と向き合う時間が急激に増えたことが大きく作用しているらしい。自宅で過ごす時間が一気に増えたことで、隣家の庭に注目がいくのだ。
また、主人公の興味が必要以上に隣家の庭に注がれるのは、かつての自身の家の様子を隣家に重ねているからではないか。男の回想の端々からは、これまで住宅や家族のことを率先して考え、決断してきたのは妻の方であったことが窺える。主人公は面倒ごとが発生するたび、その問題を考えないようにしてその場をしのいできた。
だから、主人公は、庭の男や隣家の子ども部屋を通して疑似的に自分の家の様子に関心を抱いているようにも見える。隣家では、2人の子どもが成長し、庭を犠牲に子ども部屋が造られ、いずれ巣立っていく……といった主人公の家と同じ流れが、数十年遅れで繰り返されている。そこに主人公は、かつての自身の家を重ねて見ていたのではないか。
物語の最後、庭の男は主人公を長きにわたって苦しめたのが嘘かのようにあっけなく姿を消す。隣家で小屋を巡って父子の一悶着があり、小屋ごと取り壊されてしまったのだった。それを知った主人公は、妻から「寂しそう」と指摘される。主人公の生活は小屋が出来る前の、家の中から隣家の広い庭を眺める安寧なものに戻る。しかし、壮年期の自分とその家庭を疑似的に体験することはもうできない。子どもが巣立ち、妻が出掛けてひとりきりの自宅と向き合う日々が始まることに、主人公は無自覚ながら寂しさを感じている。庭の男の「私のそんな焦りを見透かしたかのように」「眼に黒い光を溜め、こちらを凝視」するような視線は、主人公の心の内をずっと見透かしていたのかもしれない。(滝)
筆者である二条は幼くして母を亡くし、4歳の頃から後深草院の下で育てられた。
共通テストでは後深草院が二条の異母妹・前斎宮に恋慕する場面が取り上げられていたが、彼は二条のことを愛人の1人として寵愛し続けた。しかし、後深草院の弟であり、すでに出家した身でもある有明の月との関係が始まるのを機に、作中屈指の激動のストーリーが展開していく。
「樒(しきみ)摘む暁起きに袖濡れて見果てぬ夢の末ぞゆかしき」。この和歌は、2人が結ばれる以前に有明の月が二条に送ったものである。樒という仏事に使われる花を摘むために早起きをしたせいで見切れなかったあなたとの夢の続きが見てみたい、という、仏教に身を置く立場とはっきり認めたうえでの愛情表現は、なかなかに衝撃的だ。
二条は有明の月と結ばれて子どもをもうけるが、二条を待ち受けているのは有明の月や、かつての恋人かつ長きにわたって仕えた主・後深草院など大切な人達との別れであった。話の後半では、出家したのちの日々が綴られている。
まるでフィクションのように急激でロマンティックで、そして切ないストーリーは、1人称で書かれているからこその迫真さがある。「尋ねられていないけれど語る」と言って始まった語りは、数百年経った現在でも途絶えることを知らない。(滝)
春城花事小園多
幾度看花幾度歌
花為我開留我往
人随春去奈春何
思翁夢好遺書扇
仙蝶図成染袖羅
他日誰家還種竹
坐輿可許子猷過
本作は、清代中国の政治家・阮元(げんげん)によって書かれた詩文集である。22年度共通テストでは、不思議な蝶と二度に渡って自分の庭で遭遇した体験を描写した、七言律詩とその序文が出題された。今回は、その出題箇所に焦点を当てたい。
漢詩というものは得てして、日本の詩文と比べ、題材となる世界観の壮大さや読み手の器の大きさを印象付ける作品が多い。それはこの詩も例外でなく、序文から詩全体に、作者の文化人らしい落ち着きが漂っている。まず、明代を代表する書画の大家、董其昌直筆の扇を持っている時点で非常な文化人であることがうかがえる。さらにそこに書かれた「名園」「蝶夢」の句と庭に偶然出現した蝶から発想を得て庭に名前をつけるなど、驚くべき優雅さである。
また、広大な中華帝国では、土地から土地への移動が非常に長期間に渡る別れをもたらすため、新天地や戦場へ向かう故人への送別の辞が多くの漢詩で詠まれてきた。本作品にも、住み慣れた都を離れる寂しさが読み込まれるが、今回は、それが人や動植物でなく庭に対する感慨だというのが粋である。松尾芭蕉の『奥の細道』の冒頭、「草の戸も住み替はる代ぞ雛の家」の句にもあるように、愛着のある家屋を残して遠く旅に出る感傷は、時代や国を超えて人々に共有される感覚と言える。
作者の阮元は、南京市の北東に位置する江蘇省儀徴の出身で、1789年に26歳で科挙に合格し、地方の総督を歴任した。在官中は、広東で学海堂(がっかいどう)、浙江で詁経精舎(こけいしょうじゃ)を設立して学問の復興をはかったほか、多くの学者を集めて古典語の字解書や経学に関する書物の編纂事業も行った。学者や書家としても名が知られた人物である。(桃)
だがその先入観を捨てて本書に向き合ってみると、切々と語られる言葉にはなめらかで心地よいリズムがあることに気づくはずだ。織り交ぜられた比喩表現も魅力的である。特に「断片」の項にある「水の上に滴らした石油のやうに散つてしまつて」「雀を追ふ鷹のやうに羽音をさせて」といった比喩は、身近な素材を用いつつみずみずしい印象を読者に与える。
語られる思想は確かに抽象的だが、内容を咀嚼して自分に照らし合わせてみると頷けるものが多い。問題文で引用されたのは「三太郎の日記第二」の「理想と実現」の項で、ここで三太郎は「理想」について、実現を目指されながらも未だ実現していないものだと定義している。だからこそ、実現していない理想を「無価値」と切り捨てるのは間違いだと喝破する。成果ばかりに目を向けるのではなく、理想を抱くことで自分の内面に生じる熱意そのものに意味を見出す。時代を経てなお読み手の心を掴むメッセージだ。
彼の思考全てを理解しようとする必要はないだろう。胸に響く言葉を求めて、気負わずページをめくってみることをおすすめする。(凡)
と、ミステリー作家であるP.D.ジェイムズらしい、衝撃的な場面設定から物語が始まるこの小説は、ディストピア小説に分類される。ディストピア小説とは反理想郷を描いたもので、ジョージ・オーウェルの『1984』、カズオ・イシグロの『わたしを離さないで』等もこれにあたる。しかし、『人類の子どもたち』の描く絶望は他の2作品に比べるとどうも緩やかに思われる。確かに、「自分の一生には限りがあるが、自分の死後も人類は繁栄し続ける」という前提が失われることは多くの人に絶望を与えた。それまでの宗教が権威を失い、扇動的な思想家が支持を集めはじめた。死ぬことを一種の通過儀礼とみなし、集団自殺を行う人たちが現れた。人形を子どもに見立ててベビーカーを引き回す女性が現れた。録音されている青少年たちの朗らかな歌声を、涙なくして聴くことができなくなった。
しかし『1984』のように見えない監視と思想犯罪の摘発に絶えず怯えているわけでもなければ、『わたしを離さないで』のように臓器提供のためのクローンとして生まれた人間が、文字通り命を削り取られていくわけでもない。たとえ人類の滅亡が決まったとしても、すぐに自分が死ぬわけではなく、表面上はそれまでと変わらない日常を営めてしまう。だから、1ページ目から「人類の滅亡」と「独裁者ザン」の両方を知らされたとき、読者はこの物語における「ディストピア」が一体どれにあたるのか、迷わされることとなる。
これには、語り手のセオが支配者側(ザン)被支配者側(民衆)のいずれにも属する立場であることも関連している。セオは従兄弟であるザンを愛しているし、ザンもまた然りだ。成長し、様々な利害関係に揉まれてもなおセオとザンが尊敬し合っていることは、2人の台詞の節々から明らかである。何より、セオの語るザンとの若き日の回想、とりわけ夏にザンの家を訪れた思い出はきらきらと輝いていて、この物語で唯一のユートピア的な雰囲気を纏う。セオは陰鬱な時代を生きる中で、ザンとの若き日の思い出に繰り返し思いを馳せている。そんなセオ目線で描かれるために、ザンは権力を恣にして人民を痛めつけるといった、いわゆる「独裁者」には見えない。
他方でセオは、社会体制に歯向かおうと秘密裏に活動するジュリアたちと親交を深めていく。彼らの口を通して、セオが直接述べはしないザンの政権の実情が語られる。民主的な政治を謳っていながらその実は独裁体制であること、犯罪者たちが無法地帯と化した離島へ流され人権を踏みにじられていること、老人たちの集団自殺に政府が加担していること。しかしそれを耳にしてもなお、セオはザンが悪人とは思えなかった。
そんな折、ジュリアの妊娠が発覚して物語は急展開を迎える。権力を掌握できるだけの手札を得たジュリアの夫・ロルフが、自分ならば良い指導者になれると言ったのに対し、セオは「ザンも前の独裁者を倒すときにそう思っていただろうね」と冷静に反論し、ザンという悪を倒そうと正義心に燃えていたロルフも、ザンの立場になれば結局同じ行動に出るのだと気付かせる。しかも、自分では正しい行為をしていると信じて疑わないままに、かつて自分が忌み嫌っていた人物と同じになってしまうのだ。
セオたちはその後、「人類の子ども」を支配下におきたい政府から必死に逃亡するが、その過程で仲間・無関係の人を問わず多くの命が犠牲となった。一度は潰えた人類の未来を再び繋ぐ1つの命のためにその他大勢の人がいとも簡単に犠牲になってしまう。しかもこの悲劇は生まれて終わりではなく、人類存続の鍵であるこの子を巡り、さらに凄惨な争いが起こることは想像に難くない。
ここで読者は怖ろしいことに気付く。独裁体制の連鎖も、凄惨な死も、人間がいるからこそ起こる。小説を読み始めたときに人類が滅亡することを絶望的に感じていた読者は、読み進めるにつれ、新たな命が生まれることに絶望を抱くのである。
常に現実を生きるセオとザンが、儚い夢想に浸った数少ないシーンの1つに次の場面がある。「もし自分たち2人が最後の人類になれたら」について、夢物語を一言二言だけ口にした。2人は、人類が繁栄する未来にではなく、滅亡する未来に思いを馳せた。少なくとも2人にとって人類再興の世界線は、手放しにユートピアと呼べるものではなかったということか。
ジュリアは無事に子を出産し、人間の歴史が再び動き出した。ディストピアが、始まったのである。(滝)
この企画では今年の共通テストに登場した8つの作品を取り上げ、出題箇所を振り返りつつ作品そのものの書評を掲載する。受験生諸君の大学入試の思い出に、これらの作品との特別な出会いが加わる助けとなれば幸いだ。また在学生も、自分が受験した年の作品を振り返ってはどうだろうか。(編集部)
目次
概評
今年の共通テストでは、国語の第1問にて、食にまつわる論説文2つに加えて宮沢賢治の『よだかの星』が引用された。以下の問題作成方針にあるように、複数の題材の検討が求められる出題であった。また、倫理では小説の『人類の子供たち』が引用され、将来世代への意識に関する設問が出された。なお、昨年度の世界史Bの『1984』に続き、2年連続でディストピア小説が登場した。
【大学入学共通テスト問題作成方針について(一部抜粋)】
国語
近代以降の文章(論理的な文章、文学的な文章、実用的な文章)、古典(古文、漢文)といった題材を対象とし、言語活動の過程を重視する。異なる種類や分野の文章などを組み合わせた、複数の題材による問題を含めて検討する。
倫理
文章や資料を読み解きながら、先哲の基本的な考え方等を手掛かりとして考察する力を求める。問題の作成に当たっては、倫理的諸課題について(中略)原典資料等、多様な資料を手掛かりとして様々な立場から考察する問題などを含めて検討する。
国語
近代以降の文章(論理的な文章、文学的な文章、実用的な文章)、古典(古文、漢文)といった題材を対象とし、言語活動の過程を重視する。異なる種類や分野の文章などを組み合わせた、複数の題材による問題を含めて検討する。
倫理
文章や資料を読み解きながら、先哲の基本的な考え方等を手掛かりとして考察する力を求める。問題の作成に当たっては、倫理的諸課題について(中略)原典資料等、多様な資料を手掛かりとして様々な立場から考察する問題などを含めて検討する。
独立行政法人大学入試センター公式サイトより
目次へ戻る
国語第1問 『食べるとはどういうことか』『食べることの哲学』
身近な「食」を解きほぐす
現代文の大問1で並べて出題されたこの2冊。「食」というテーマは共通しているが、展開される論の違いが面白い。共通するふたつのキーワードに注目して読み比べると、その違いがはっきりと見えてくる。ひとつは「哲学」だ。一般に哲学といえば、実生活から縁遠い抽象的な思想を扱う学問がイメージされるだろう。その点で『食べることの哲学』という表題は、日常的な「食」と「哲学」の組み合わせがちぐはぐな印象を与える。しかし、本書がいう哲学はそうした一般的なイメージに近い。筆者の檜垣氏はフランス現代思想を専門とする哲学者であり、宮沢賢治の作品や人類学者レヴィ=ストロースの主張といった具体的な素材を用いて、食べるという行為や食べ物の根本を考察していく。この具体から抽象へと向かう過程は、人や世界の根底にある原理を突き詰める哲学の営みに沿った流れだといえる。
対して『食べるとはどういうことか』では、「哲学」を「世の中で当たり前とされていることを問い直すこと」「答えの無い問いについて考えること」と、より身近な営みとして捉えている。これは本書の内容のもとになった座談会で、筆者である藤原氏が12歳から18歳の学生たちに繰り返し語った考えだ。「哲学」を広く定義することで、日常の中にある食が学問の素材になりうること、さらには分野を問わず、ある問いについて根気強く追究することがいかに大切で身近なものなのかが、効果的に読者の心に響いてくる。
もうひとつのキーワードは「文化」である。ただし両方とも単なる食文化、つまり特定の民族や社会と結びついた食習慣を指しているわけではない。『食べるとはどういうことか』の中では、生物として人間が抱く食欲が満たされて初めて生まれる、食べる喜びを「文化」だと定義する。食に伴うポジティブな感情こそが、食べるという行為に栄養摂取以上の意味合いを与えているというのである。現代社会ではサプリメントやゼリー食品の開発が進んでいる。食事を手早く済ませようとする風潮を見直すうえで、この「文化」は重要な意味を持つ。
一方『食べることの哲学』では、「文化」は常に「自然」、すなわち人間がもつ動物的側面と対立する概念として登場する。料理という食文化は人間が自然環境に働きかけた結果生まれるため、食べることは「自然」と「文化」という対立する概念を結び付けるものだと主張している。そして多くの食文化でタブーとされるカニバリズム、いわゆる食人行為へと議論が進む。カニバリズムは単に文化の面から禁じられているだけではなく、複雑な自然との関わりがその根底にあるのではないかという問いが引き出され、宮沢賢治の作品がその問いを検討する素材として登場するのだ。
議論の展開は異なる2冊だが、どちらも個人的体験から出発して論を進めている点が興味深い。藤原氏は座談会の始めに、いままで食べたもので何が一番おいしかったかを学生たちに尋ね、食べるという行為には人間関係や風景が重層的に関わっていると示している。檜垣氏は自身のフランスでの食体験をもとに、「単調な」ヨーロッパ系の食とコクや旨みを重視する他地域の食を一貫して区別している。そのため、筆者の主張に必ずしも頷けるとはかぎらない。特にヨーロッパの食事を「味気ない」と言い切り、そのような価値判断を混ぜたまま話を進めていく檜垣氏の姿勢には疑問を覚える。
だからといって、その主張を検討するに値しないと切り捨てるのは間違いだ。藤原氏と学生たちが座談会で導き出した通り、食べることには人間のさまざまな感覚が関わっている。食を追究するうえでは、個人の具体的な体験こそが学問の種なのだと気づかされる。身近なものごとを突き詰めて考えを深めていく楽しさ、学問の根本にある喜びを実感できる2冊である。(凡)
『食べることの哲学』
著者 檜垣 立哉
出版社 世界思想社
発行日 2018年4月
価格 1870円
著者 檜垣 立哉
出版社 世界思想社
発行日 2018年4月
価格 1870円
『食べるとはどういうことか』
著者 藤原 辰史
出版社 農山漁村文化協会
発行日 2019年3月
価格 1650円
著者 藤原 辰史
出版社 農山漁村文化協会
発行日 2019年3月
価格 1650円
目次へ戻る
国語第1問 『よだかの星』
星になったよだかが伝えること
本作は『銀河鉄道の夜』や『注文の多い料理店』と並ぶ宮沢賢治の代表作である。文庫本にして9ページと非常に少ない文量に加えて、難解な寓話の多い賢治作品の中では教訓としてわかりやすいテーマを持つため、学校の教材として扱われることも多い。主人公よだかは、外見を理由に周囲の鳥たちにばかにされる存在である。同じ名前を持つ鷹に名前を変えなければつかみ殺すと脅されたよだかは、自分の生に見切りをつけて遠く空の向こうへ去ることを決意するが、連れて行ってくれと頼んだ太陽や星々にも冷たくあしらわれてしまう。ひとり孤独に身を任せて地面に落ちようとした時、突如よだかは力を得てどこまでも高く飛び上がり、青く光る星になるのだ。
この話は、外見で他者を判断することを戒める道徳的な話として解釈されることが多い。それは、現代社会で顕在化するルッキズムの問題と重なる非常に重要なテーマである。確かによだかのモデルとなったヨタカは、賢治の描写通りのまだらな羽の色と耳まで裂けた平たい口を持つが、鳥にとっての美醜に疎い人間の目線では、それが美的に貶められる原因になるとはあまり思えない。美的感覚は、環境に依存した相対的なものである。
また、いじめの問題として本作を解釈するならば、遠くへ去ろうとするよだかを心配し引き留めた川せみの存在が重要になるだろう。鳥たちに散々に否定され、追い込まれて周りが見えなくなっている時にも、よだかの近くに味方はいたのだ。しかし、よだかはその存在に気がつくことができなかったし、川せみも、よだかの行動を変えることはできなかった。あと一歩、互いに歩み寄ることがどうしても難しい。
一方、今回の共通テストでは、よだかを取り巻く「食べるものと食べられるもの」の関係に焦点が当てられた。周囲にさげすまれ疎まれ続けたよだかは、自分の生に悲観的になり、どうしてこんな目にあうのかと運命を呪う。が、ひとたび風を切って空を飛べば、何もせずとも口に虫が入りそれを飲み込まずにはいられないのだ。自分の生命の意味を疑えば疑うほどに、その土台に存在する他の生き物たちの死が重くのしかかる。
自分が多くの生命を奪って生きていることを自覚したよだかは、深い悲しみに襲われ、誰も知らない遠くの空へ飛び立つ、すなわち、この世から離れることを決意する。このような描写には、賢治自身が抱いていた法華経信仰が色濃くあらわれているだろう。また法華経では、生命を持つもの全ては生まれながらに仏となる素質を持ち、信じて修行すれば皆仏になることができると説かれる。それだけを根拠に、星となったよだかの最後を仏になったものと理解するのは極端だが、あまりに人間らしい鳥たちの振る舞いやよだかの内面の葛藤には、万物に平等に仏性を見出す法華経の感性が見て取れる。
よだかが天にあげられて青く輝く星となる最後は、賢治にとっての、苦しむ者に対する本当の救いのあり方を示しているように思えてならない。賢治にとっての救済とは、敵が報いを受けることでも誰かに苦しみを理解してもらうことでもなく、苦しみを感じることのない、どこまでも美しく純粋なものになることだったのではないか。優しくも切ない賢治の信念がうかがえる作品である。(桃)
『よだかの星』
著者 宮沢 賢治
出版社 筑摩書房
発行日 2017年2月
価格 2750円
著者 宮沢 賢治
出版社 筑摩書房
発行日 2017年2月
価格 2750円
目次へ戻る
国語第2問 『庭の男』
男の視線が見つめるのは
黒井千次の短編集『石の話』に収録されているこの話は、短くて読みやすいながらも、丁寧な心情表現と巧みな構成を辿っていくうちに、奥深い黒井千次の世界観へと引き込まれていく作品だ。長年勤めた仕事を定年退職した主人公は、1人自宅で過ごす時間が増えた新しい生活に慣れることができず、今まで何気なく見過ごしていた家の様子に敏感になっていた。
題名の「庭」は自宅の庭ではない。数十年前に庭部分に子ども部屋を増築した結果、夫婦は庭を失っていた。その代わり、キッチンの窓から見える隣家の庭を眺めるようになった。
そんなある日、隣人の庭に白い小屋が造られた。どうやら、高校生になる息子のひとり部屋のようである。はじめ主人公は、両親や祖父母のいる母屋を離れて晴れて自室を持ったことを内心で祝福していた。しかし、次第に小屋の周りにベンチや看板など雑多なものが置かれていき、庭の風景の変貌を主人公が憂うる中、ついに「庭の男」――海外映画の立て看板らしきものに描かれた男、が現れた。自宅のキッチンの窓越しに目があう男の鋭い視線に、主人公は辟易する。ついにはキッチンにいない時にすら男の視線が気になって仕方がなくなってしまった。
主人公は妻にこのことを話すが、妻は庭の男のことをさして気にしていない。主人公だけが異常に敏感であるのは、庭の男が突如現れたという直接要因よりも、退職して家と向き合う時間が急激に増えたことが大きく作用しているらしい。自宅で過ごす時間が一気に増えたことで、隣家の庭に注目がいくのだ。
また、主人公の興味が必要以上に隣家の庭に注がれるのは、かつての自身の家の様子を隣家に重ねているからではないか。男の回想の端々からは、これまで住宅や家族のことを率先して考え、決断してきたのは妻の方であったことが窺える。主人公は面倒ごとが発生するたび、その問題を考えないようにしてその場をしのいできた。
だから、主人公は、庭の男や隣家の子ども部屋を通して疑似的に自分の家の様子に関心を抱いているようにも見える。隣家では、2人の子どもが成長し、庭を犠牲に子ども部屋が造られ、いずれ巣立っていく……といった主人公の家と同じ流れが、数十年遅れで繰り返されている。そこに主人公は、かつての自身の家を重ねて見ていたのではないか。
物語の最後、庭の男は主人公を長きにわたって苦しめたのが嘘かのようにあっけなく姿を消す。隣家で小屋を巡って父子の一悶着があり、小屋ごと取り壊されてしまったのだった。それを知った主人公は、妻から「寂しそう」と指摘される。主人公の生活は小屋が出来る前の、家の中から隣家の広い庭を眺める安寧なものに戻る。しかし、壮年期の自分とその家庭を疑似的に体験することはもうできない。子どもが巣立ち、妻が出掛けてひとりきりの自宅と向き合う日々が始まることに、主人公は無自覚ながら寂しさを感じている。庭の男の「私のそんな焦りを見透かしたかのように」「眼に黒い光を溜め、こちらを凝視」するような視線は、主人公の心の内をずっと見透かしていたのかもしれない。(滝)
『石の話 黒井千次自選短篇集』
著者 黒井 千次
出版社 講談社
発行日 2004年3月
価格 1320円
著者 黒井 千次
出版社 講談社
発行日 2004年3月
価格 1320円
目次へ戻る
国語第3問 『とはずがたり』
強く美しい、鎌倉女性の生きざま
『とはずがたり』は、鎌倉時代の中後期に、後深草院二条によって書かれた日記文学だ。題名にあるように、「問われなくても語る」というスタンスで実体験が綴られている。筆者である二条は幼くして母を亡くし、4歳の頃から後深草院の下で育てられた。
共通テストでは後深草院が二条の異母妹・前斎宮に恋慕する場面が取り上げられていたが、彼は二条のことを愛人の1人として寵愛し続けた。しかし、後深草院の弟であり、すでに出家した身でもある有明の月との関係が始まるのを機に、作中屈指の激動のストーリーが展開していく。
「樒(しきみ)摘む暁起きに袖濡れて見果てぬ夢の末ぞゆかしき」。この和歌は、2人が結ばれる以前に有明の月が二条に送ったものである。樒という仏事に使われる花を摘むために早起きをしたせいで見切れなかったあなたとの夢の続きが見てみたい、という、仏教に身を置く立場とはっきり認めたうえでの愛情表現は、なかなかに衝撃的だ。
二条は有明の月と結ばれて子どもをもうけるが、二条を待ち受けているのは有明の月や、かつての恋人かつ長きにわたって仕えた主・後深草院など大切な人達との別れであった。話の後半では、出家したのちの日々が綴られている。
まるでフィクションのように急激でロマンティックで、そして切ないストーリーは、1人称で書かれているからこその迫真さがある。「尋ねられていないけれど語る」と言って始まった語りは、数百年経った現在でも途絶えることを知らない。(滝)
『とはずがたり』
著者 後深草院二条
次田香澄全訳注
出版社 講談社
発行日 1987年7月
価格 1450円(上)
1480円(下)
著者 後深草院二条
次田香澄全訳注
出版社 講談社
発行日 1987年7月
価格 1450円(上)
1480円(下)
目次へ戻る
国語第4問 『揅経室集(けんけいしつしゅう)』
蝶との邂逅(かいこう)、去る庭に残す思い
春城花事小園多
幾度看花幾度歌
花為我開留我往
人随春去奈春何
思翁夢好遺書扇
仙蝶図成染袖羅
他日誰家還種竹
坐輿可許子猷過
本作は、清代中国の政治家・阮元(げんげん)によって書かれた詩文集である。22年度共通テストでは、不思議な蝶と二度に渡って自分の庭で遭遇した体験を描写した、七言律詩とその序文が出題された。今回は、その出題箇所に焦点を当てたい。
漢詩というものは得てして、日本の詩文と比べ、題材となる世界観の壮大さや読み手の器の大きさを印象付ける作品が多い。それはこの詩も例外でなく、序文から詩全体に、作者の文化人らしい落ち着きが漂っている。まず、明代を代表する書画の大家、董其昌直筆の扇を持っている時点で非常な文化人であることがうかがえる。さらにそこに書かれた「名園」「蝶夢」の句と庭に偶然出現した蝶から発想を得て庭に名前をつけるなど、驚くべき優雅さである。
また、広大な中華帝国では、土地から土地への移動が非常に長期間に渡る別れをもたらすため、新天地や戦場へ向かう故人への送別の辞が多くの漢詩で詠まれてきた。本作品にも、住み慣れた都を離れる寂しさが読み込まれるが、今回は、それが人や動植物でなく庭に対する感慨だというのが粋である。松尾芭蕉の『奥の細道』の冒頭、「草の戸も住み替はる代ぞ雛の家」の句にもあるように、愛着のある家屋を残して遠く旅に出る感傷は、時代や国を超えて人々に共有される感覚と言える。
作者の阮元は、南京市の北東に位置する江蘇省儀徴の出身で、1789年に26歳で科挙に合格し、地方の総督を歴任した。在官中は、広東で学海堂(がっかいどう)、浙江で詁経精舎(こけいしょうじゃ)を設立して学問の復興をはかったほか、多くの学者を集めて古典語の字解書や経学に関する書物の編纂事業も行った。学者や書家としても名が知られた人物である。(桃)
『揅経室集』
著者 阮元
出版社 中華書局
発行日 2016年3月
価格 9490円
著者 阮元
出版社 中華書局
発行日 2016年3月
価格 9490円
目次へ戻る
倫理第2問 『三太郎の日記』
悩む著者の内省を辿る
本書は阿部次郎が「三太郎」という人物に仮託し自身の思索をつづった評論随筆集で、倫理の問題の中では近代の「理想」に関連する文章として引用された。教養小説として有名だからこそ、内容が抽象的で難解だというイメージを持つ人も多いだろう。だがその先入観を捨てて本書に向き合ってみると、切々と語られる言葉にはなめらかで心地よいリズムがあることに気づくはずだ。織り交ぜられた比喩表現も魅力的である。特に「断片」の項にある「水の上に滴らした石油のやうに散つてしまつて」「雀を追ふ鷹のやうに羽音をさせて」といった比喩は、身近な素材を用いつつみずみずしい印象を読者に与える。
語られる思想は確かに抽象的だが、内容を咀嚼して自分に照らし合わせてみると頷けるものが多い。問題文で引用されたのは「三太郎の日記第二」の「理想と実現」の項で、ここで三太郎は「理想」について、実現を目指されながらも未だ実現していないものだと定義している。だからこそ、実現していない理想を「無価値」と切り捨てるのは間違いだと喝破する。成果ばかりに目を向けるのではなく、理想を抱くことで自分の内面に生じる熱意そのものに意味を見出す。時代を経てなお読み手の心を掴むメッセージだ。
彼の思考全てを理解しようとする必要はないだろう。胸に響く言葉を求めて、気負わずページをめくってみることをおすすめする。(凡)
『三太郎の日記』
著者 阿部 次郎
出版社 KADOKAWA
発行日 2008年11月
価格 3080円
著者 阿部 次郎
出版社 KADOKAWA
発行日 2008年11月
価格 3080円
目次へ戻る
倫理第4問 『人類の子供たち』
「ディストピア」って?
2021年1月1日、語り手が50歳の誕生日を迎えると共に、地球で最後に誕生した人類が亡くなったというニュースが流れるところから、物語は始まる。語り手はセオ、物語の舞台であるイングランドの独裁者・ザンの従兄弟で、生き残っている唯一の身内だ。1995年、突如人間は繁殖能力を失った。あまりにも決定的なこの事件は「オメガ」と呼ばれ、妊婦が1人もいなくなったのみならず、冷凍保存していた精子までもが能力を失っていた。それ以前は、世界の飢餓や環境破壊をはじめ、人類の抱える問題の多くは人口が増えすぎたせいだと考え、少子化を誉めそやしていた人々は、一気に絶望の縁へと追いやられることとなる。と、ミステリー作家であるP.D.ジェイムズらしい、衝撃的な場面設定から物語が始まるこの小説は、ディストピア小説に分類される。ディストピア小説とは反理想郷を描いたもので、ジョージ・オーウェルの『1984』、カズオ・イシグロの『わたしを離さないで』等もこれにあたる。しかし、『人類の子どもたち』の描く絶望は他の2作品に比べるとどうも緩やかに思われる。確かに、「自分の一生には限りがあるが、自分の死後も人類は繁栄し続ける」という前提が失われることは多くの人に絶望を与えた。それまでの宗教が権威を失い、扇動的な思想家が支持を集めはじめた。死ぬことを一種の通過儀礼とみなし、集団自殺を行う人たちが現れた。人形を子どもに見立ててベビーカーを引き回す女性が現れた。録音されている青少年たちの朗らかな歌声を、涙なくして聴くことができなくなった。
しかし『1984』のように見えない監視と思想犯罪の摘発に絶えず怯えているわけでもなければ、『わたしを離さないで』のように臓器提供のためのクローンとして生まれた人間が、文字通り命を削り取られていくわけでもない。たとえ人類の滅亡が決まったとしても、すぐに自分が死ぬわけではなく、表面上はそれまでと変わらない日常を営めてしまう。だから、1ページ目から「人類の滅亡」と「独裁者ザン」の両方を知らされたとき、読者はこの物語における「ディストピア」が一体どれにあたるのか、迷わされることとなる。
これには、語り手のセオが支配者側(ザン)被支配者側(民衆)のいずれにも属する立場であることも関連している。セオは従兄弟であるザンを愛しているし、ザンもまた然りだ。成長し、様々な利害関係に揉まれてもなおセオとザンが尊敬し合っていることは、2人の台詞の節々から明らかである。何より、セオの語るザンとの若き日の回想、とりわけ夏にザンの家を訪れた思い出はきらきらと輝いていて、この物語で唯一のユートピア的な雰囲気を纏う。セオは陰鬱な時代を生きる中で、ザンとの若き日の思い出に繰り返し思いを馳せている。そんなセオ目線で描かれるために、ザンは権力を恣にして人民を痛めつけるといった、いわゆる「独裁者」には見えない。
他方でセオは、社会体制に歯向かおうと秘密裏に活動するジュリアたちと親交を深めていく。彼らの口を通して、セオが直接述べはしないザンの政権の実情が語られる。民主的な政治を謳っていながらその実は独裁体制であること、犯罪者たちが無法地帯と化した離島へ流され人権を踏みにじられていること、老人たちの集団自殺に政府が加担していること。しかしそれを耳にしてもなお、セオはザンが悪人とは思えなかった。
そんな折、ジュリアの妊娠が発覚して物語は急展開を迎える。権力を掌握できるだけの手札を得たジュリアの夫・ロルフが、自分ならば良い指導者になれると言ったのに対し、セオは「ザンも前の独裁者を倒すときにそう思っていただろうね」と冷静に反論し、ザンという悪を倒そうと正義心に燃えていたロルフも、ザンの立場になれば結局同じ行動に出るのだと気付かせる。しかも、自分では正しい行為をしていると信じて疑わないままに、かつて自分が忌み嫌っていた人物と同じになってしまうのだ。
セオたちはその後、「人類の子ども」を支配下におきたい政府から必死に逃亡するが、その過程で仲間・無関係の人を問わず多くの命が犠牲となった。一度は潰えた人類の未来を再び繋ぐ1つの命のためにその他大勢の人がいとも簡単に犠牲になってしまう。しかもこの悲劇は生まれて終わりではなく、人類存続の鍵であるこの子を巡り、さらに凄惨な争いが起こることは想像に難くない。
ここで読者は怖ろしいことに気付く。独裁体制の連鎖も、凄惨な死も、人間がいるからこそ起こる。小説を読み始めたときに人類が滅亡することを絶望的に感じていた読者は、読み進めるにつれ、新たな命が生まれることに絶望を抱くのである。
常に現実を生きるセオとザンが、儚い夢想に浸った数少ないシーンの1つに次の場面がある。「もし自分たち2人が最後の人類になれたら」について、夢物語を一言二言だけ口にした。2人は、人類が繁栄する未来にではなく、滅亡する未来に思いを馳せた。少なくとも2人にとって人類再興の世界線は、手放しにユートピアと呼べるものではなかったということか。
ジュリアは無事に子を出産し、人間の歴史が再び動き出した。ディストピアが、始まったのである。(滝)
『人類の子供たち』
著者 P. D. ジェイムズ
出版社 早川書房
発行日 1993年10月
価格 1748円
著者 P. D. ジェイムズ
出版社 早川書房
発行日 1993年10月
価格 1748円