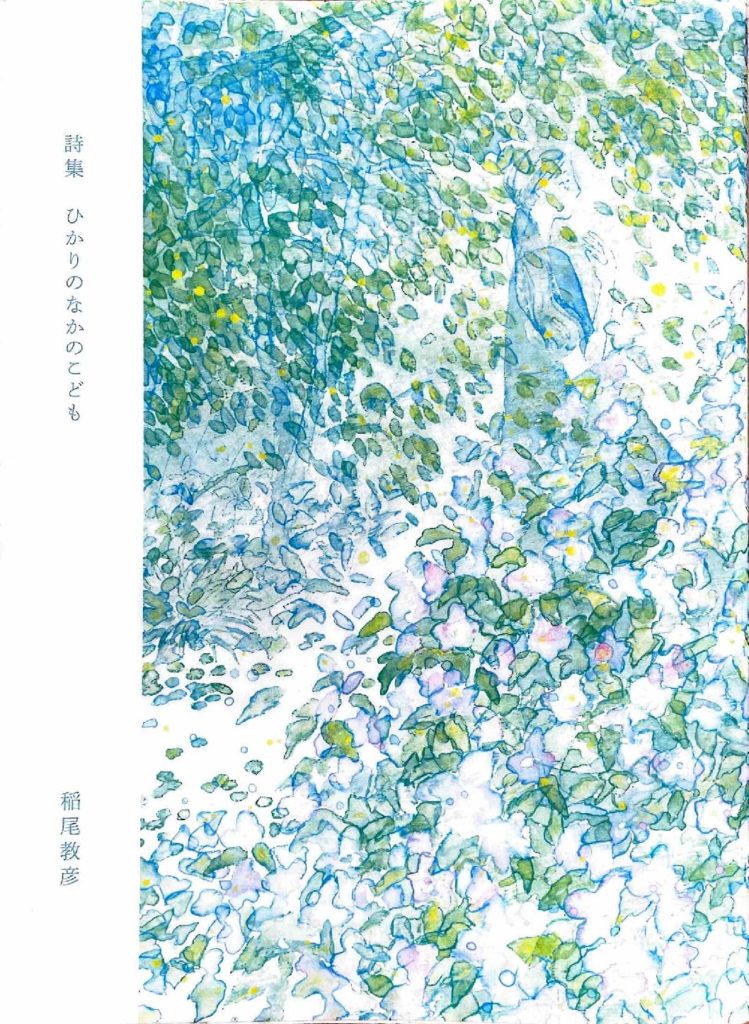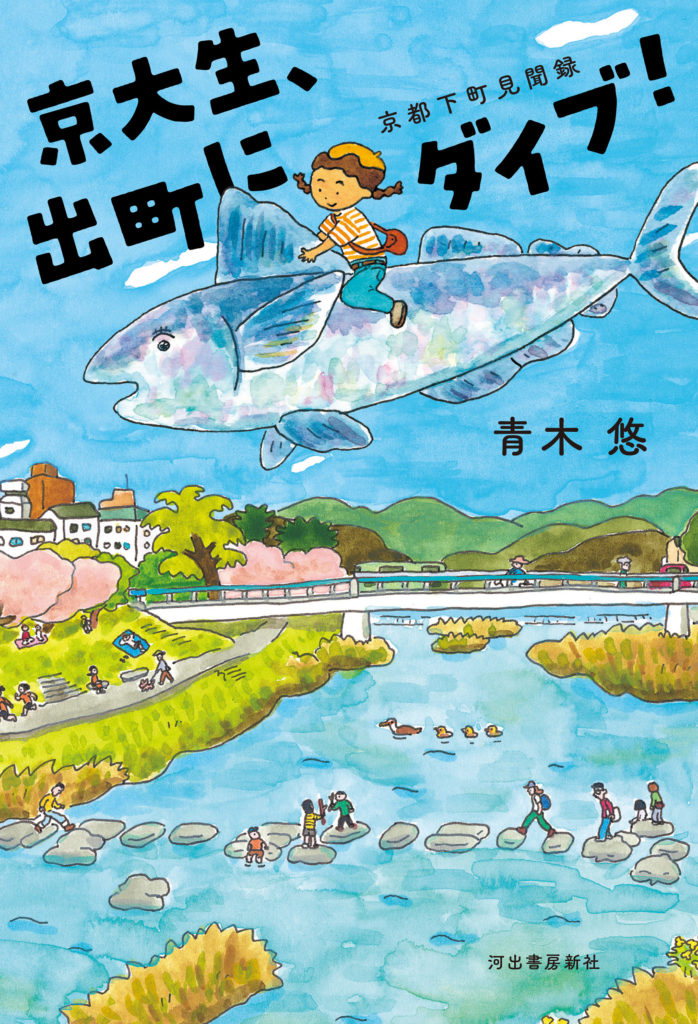〈書評〉滝川事件を掘り下げる 松本清張「京都大学の墓碑銘」
2024.11.01

滝川事件とは、1933年、文部省が京都帝国大学教授の滝川幸辰(刑法)を、その学説が学生や社会に悪影響を及ぼすとして休職に付し、京大法学部の全教官が抗議のため辞表を提出した事件である。
著者の松本清張は、『点と線』などの推理小説でよく知られている。そのため小説家としての印象が強いかもしれないが、本作のように事実を基にした作品も数多く残している。
本作は滝川事件を平明な筆致で描き出す。特に注目すべきは、文部省が「学問の自由を妨げる意思は毫も持っていない」としつつ「滝川事件は非常特別な場合として扱う」とする立場を取ったこと、京大法学部にも判子を忘れたと言って辞職を避けようとした教授が3名いたことであろう。学問の自由を建前上も重視しない文部省と、滝川教授を一枚岩で援護する京大法学部という対立構図では捉えきれない事件の全貌が、清張ならではの緻密な描写で表現される。
昨夏、北九州市立松本清張記念館を訪ねた。展示物の年表から本作の存在を知り、題名をメモした。その時知ったことだが、歴史研究にも取り組んだ清張は、批判無くして学問は発展しないとの意識を持ち、何事にも疑ってかかることを大切にしたという。その精神は本作にも表れている。
「帝国大学が出来て以来、どこの官立大学に真の意味の自主独立があったであろうか」「元来、国家と大学とは、その根底に融和のできない二律背反的な対立が存在している」。本作に散りばめられた清張の考察は、半世紀後の我々をもハッとさせる鋭さを持つ。
3年前、京大の法経本館の掲示板には「滝川事件を忘れるな」という手書きの貼り紙があった。近年、大学では国による「ガバナンス改革」が断行されており、新たな施策が発表されるたび、学問の自由や大学の自治の侵害ではないかと反対の声が上がる。本作は、そのような自由の存在意義を決して自明視しない。憲法で保障されているから重要という、ある意味形式的な理由付けは、明治憲法下の滝川事件には当然妥当しない。本作は教訓を垂れるものではないが、国立大学と国の関係について根本に立ち返って考えるきっかけを与える。
ちなみに本作では、本紙の前身の「京都帝国大学新聞」が少しだけ登場する。当時の紙面は「京都大学学術情報リポジトリ」にてネット公開されているので、本作と合わせて読んでみてはいかがだろうか。(扇)
◆書誌情報
『昭和史発掘4』(「京都大学の墓碑銘」を収録)
松本清張/著
文春文庫
870円+税
『昭和史発掘4』(「京都大学の墓碑銘」を収録)
松本清張/著
文春文庫
870円+税