解かずに読む共通テスト書評2024
2024.02.16
1月13日、14日の2日間にわたって実施された大学入学共通テストでは、今年も様々な問題が出題された。中には受験者を大いに悩ませたものもあったかもしれない。ここでは、共テに出題された作品の書評を4つ掲載する。春を待ちつつ書評で共テを振り返ってみてはいかがだろうか。(編集部)
どんなに遠く離れていてもすべては同時に存在していて、自分もその一部にすぎないのだ 国語 第2問『桟橋』牧田真有子
もう今日では、どんな目的を達成するためにも戦争を使うべきではない 倫理,政治・経済 第2問『人間の尊さを守ろう』吉野源三郎
政治とは、情熱と判断力の二つを駆使しながら、堅い板に力をこめてじわっじわっと穴をくり貫いていく作業である 倫理,政治・経済 第5問『職業としての政治』マックス・ヴェーバー
「音楽」や「芸術」は決して最初から「ある」わけではなく、「なる」ものである
国語の第1問では『サウンドとメディアの文化資源学―境界線上の音楽』が出題された。作者は現在東京音楽大学で教授を務める音楽学者の渡辺裕。音楽や芸術と社会がどのように関係しているかを研究する第一人者だ。
近年、音楽や芸術そのものを文化的・社会的背景から完全に切り出したかのような状況が数多く見られる。「モーツァルトの曲そのものに感動した」といったように、音楽や芸術は特別視、本文中の言葉を使うと「聖域」視されることが多いという。だが、一般に「音楽」や「芸術」と捉えられているものは社会の影響を色濃く受けて存在するようになる。言い換えると「『音楽』や『芸術』は決して最初から『ある』わけではなく、『なる』ものである」。音楽や芸術も様々なコンテクストの影響を受けた紛れもない「文化」だ。本著ではこのことを核に話が進行していく。
試験問題では、モーツァルト没後200年を記念して行われた特別な追悼ミサを具体例に挙げ、音楽とは何かを論じた箇所を取り上げている。追悼ミサ自体が宗教行事であること、随所に音楽ではない宗教的所作があったことを踏まえると、このミサは典礼と言えそうだ。だが、通常の儀式とは会場の設営が異なったこと、ウィーンの著名な楽団や合唱団が演奏する様子をおさめたDVDが販売されたことを鑑みると、このイベントは音楽とも言えそうだ。このように典礼との二項対立で論じられるほど、簡単には音楽を語れないという。
著者は更に視点を広げ、近年は芸術全般に亘り「博物館化」が進んでいると主張する。博物館の展示コーナーでは「聖域」にあると見なされていた物だけでなく、それを取り巻くコンテクストをも見せるようになった。結果として、人々は「『鑑賞』のまなざし」を幅広く向けているという。前述の追悼ミサも、ミサ内の演奏に限って向けられていた「『鑑賞』のまなざし」が典礼そのものにも向けられるようになったと捉えると、「博物館化」の進行の一例と考察できる。とすると、「『鑑賞』のまなざし」の拡大と共に「聖域」が変化している、すなわち、「音楽」や「芸術」という概念は変容的で、様々なコンテクストの影響を受けて成立すると言えるのではないだろうか。
著者のこの主張には確かに納得がいく。美術評論家の柳宗悦に端を発した「民藝」運動もこの一例だろう。柳が普段の暮らしの中で何気なく使われていた日用品にも「芸術」としての価値を見出した結果、保存活動に力が注がれるようになった。消耗品が至高の美術作品と化したこの現況は、確かに文化的・社会的背景を受けていると言わざるを得ないだろう。また、「音楽」の分野に関しては、タイプライターを叩く音を中心にそえた楽曲「タイプライター」や、演奏者が沈黙を貫き、偶発的に生じた周囲の音に耳を傾ける楽曲「4分33秒」を例に挙げたい。こうした楽曲は、作曲家がそれまでは「音楽」と思われていなかったものに目をつけたことで初めて「音楽」となったと考えられる。
余談だが、ふと立ち止まって考えてみると、この考えと社会学者ソシュールの思想との類似性に気付く。ソシュールは言葉が世界を分節し、分節した瞬間に初めて言葉によって命名されたものが存在するようになると主張した。それまで、我々は認知することが不可能だとも訴えた。要は最初から「ある」わけではなく、言葉で媒介することで対象に「なる」という。著者は音楽社会学者でもあり、ソシュールの思想に触れてきたはずだ。とすると、少なからずソシュールの影響を受けていてもおかしくないのではないか。
ここまで色々と述べてきたが、これらは全て、最初に書かれた総論に収斂する。本書ではここから「音楽」・「芸術」と言えるかが微妙な境界線上に位置する事案を8つ取り上げる。ある章では北海道大学恵迪寮の寮歌「都ぞ弥生」に触れるなど、一つの章で一つの例に言及するため、比較的読みやすい。春休みに時間をもて余すよりは、気になった箇所だけでも構わないから読んでみるのはいかがだろうか。そうした知識もまた、自分の中に最初から「ある」わけではないのだから。(郷)

どんなに遠く離れていてもすべては同時に存在していて、自分もその一部にすぎないのだ
『文藝 2017年秋季号』に収録されているこの短編小説は、16歳の高校生イチナが、実家に突然転がり込んできた24歳のおばとの同居生活の中で、自己のあり方を変容させていく物語だ。
「風来坊」のおばは、知り合いの家を転々としながら暮らしている。居候する家から勤め先の縫製工場に通い、休日は自らの立ち上げた劇団の稽古に打ち込む。17歳年上の姉であるイチナの母ははじめ居候に反対していたがしぶしぶ受け入れ、イチナ、両親、おばの4人暮らしが始まった。
イチナがおばと会うのはこれが初めてではない。出題箇所はイチナの幼いころの回想から始まる。幼いイチナにとっておばは「ままごと遊びになぜか本気で付き合ってくれるおねえさん」だった。
居候する理由についてイチナに問われたおばは「私の肉体は家だから、自分の家をほしいとは思えない」と答えた。イチナはこの言葉を「演じるごとに役柄に自分をあけ払うから」ということだと理解した。確固たる自分がいて、その領域を侵されないように守るのではない。おばはいつでも演じているときのように、自分を内側から規定する「枠」から抜け出している。
ある日、おばが演劇の公演のため現地入りするというのでイチナはついていくことにした。おばはイチナに演劇を観に来ることを禁じていたが、舞台は観ないという条件で許可が下りた。その夜、宿でイチナはおばになぜ舞台を観に行ってはいけないのか尋ねた。「私の橋をあなたの橋にはできない」。その答えの意味はイチナにはすぐ理解できなかった。
ここで、驚くべき事実が読者に明かされる。おばは、本当はイチナのおばではない。イチナの母が17歳の時に産んだ子で、戸籍上は祖父母の養子として育てられた。おばには知らされていない秘密だった。しかも、イチナにもまた本人の知らない出生の事情があった。イチナの両親は実の親ではない。おばの父と他の女性との間にできた子で、イチナの母が引き取ったのだ。
法事で訪れた親戚の家で、おばは偶然この秘密を知ってしまう。呆然とするおばは、しかし、何も知らない幼いイチナに真実を告げることなく、彼女のおばを演じる道を選ぶ。
シーンは宿に戻る。眠りから覚めたイチナは、姿を消したおばを探し、入り江から突き出た桟橋にたどり着く。漁港の作業場に血がついているのを目撃した彼女は、何かを問われているように感じ、目を離すことができない。正体のつかめない問いに、その場しのぎの答えを出す。「どんなに遠く離れていてもすべては同時に存在していて、自分もその一部にすぎないのだ」。血は肉体の存在や実存、あるいは血縁を連想させる。イチナは血に確かな実存を読み取り、それが実は自分やおばを含むすべてのものに当てはまることに、無意識のうちに気がついたのだろう。ここにいないおばの存在が、ふいにくっきりとイチナの心に現れる。血というモチーフによってイチナとおばが結び付けられるこの場面は、イチナの身の回りではおばが唯一の血縁者であることを考えるとなかなか心憎い。公演から帰ったおばは荷物をまとめてイチナの家を出て行くのだった。
以来イチナは、おばのあり方を生活に取り入れ始める。「悪の側に立つことになろうが、敗れた存在になろうが、自分を護るために事実に手を加えようとはしなかった。それは自分が自分であるということを後回しにすることでもあった」。自分とイチナの秘密を隠すことから始まった「自分から離れる」ということ。それは他の人とは違うおば独特の生き方として現れ、イチナに伝わっていく。
その後イチナは、おばがイチナに観劇を禁じていた理由が、「橋がねじ切れて桟橋になるから」だったと知る。橋は血縁関係の比喩だろう。おばは、イチナに演じる姿を見られると、それをきっかけとしてイチナと「両親」をつなぐ血縁という橋が本当は桟橋であったこと、つまり血のつながりが存在しないことがイチナに知られてしまうのではと危惧していたのかもしれない。「私の橋をあなたの橋にはできない」というおばの言葉は、変えることのできない血縁という事実に、彼女と同じようにイチナがいつか直面することになることを暗示しているようでさえある。
14ページと短いながら、密度が高く強烈な読後感を残す作品だった。(鷲)

もう今日では、どんな目的を達成するためにも戦争を使うべきではない
吉野源三郎と聞けば、昨年映画化されて話題となった『君たちはどう生きるか』を思い浮かべる人も多いだろう。吉野は1899年生まれで、東京帝国大学を卒業したのち編集者として活動した。本書は第2次世界大戦が終わってから間もない頃に、青少年を対象に執筆した文章をまとめた1冊だ。吉野は戦争を経て変化した社会の仕組みを平易な言葉で語る。共通テストでは、第2次世界大戦が人々の結びつきを崩壊させたとしたうえで、人間への信頼を取り戻す必要があると述べた箇所が引用された。
執筆当時、社会のあり方が大きく転換したことは想像に難くない。吉野は、まず一人ひとりの権利は平等に重んじられるべきだとする「個人主義」について説明する。その上で、社会全体の問題は社会の仕組みやその動きに原因があることが多いため、個人主義では不十分で、「民主主義」の考え方が必要になると述べる。「個人として責任がないことでも、全体のなかのひとりとして、やはり責任を分け合わなくてはいけないことはいろんな場あいにある」。本書を通じて、憲法施行直後に民主主義へ寄せられていた期待をうかがい知ることができる。
民主主義や選挙の話題と並んで、労働組合について解説する章があったことは意外だった。というのも、労働問題は政治的な仕組みと一線を画しているような気がしたからだ。しかし、あとがきを読んでなぜ労働問題を取り上げたのかを理解した。吉野は「民主主義に基づいて法律上すべての国民が一応平等となり、同じ政治的権利を持つようになっても、なお、実際には不平等がなくならないこと、特に経済的な不平等がなくならない」と指摘し、それを打開する1つの方策として労働組合の話に言及したと説明する。
吉野は、労働者階級が社会にとって大事な役割を受け持ちながらも尊敬されないという点で古代の「ドレイ」に近い状態にあることを述べ、労働者が労働組合のもとで団結して行動することで、彼らの役割の重大さを社会に知らせることができるとする。人々は労働を通じて社会に関与しており、労働は個人と社会を繋いでいるという意味で政治的な事柄であるとも考えることができよう。また、日本国憲法が施行された直後に、法律で権利が保障されるだけでは現実は変わらないという鋭い指摘をしていたことに驚いた。
最も印象的だったのは、吉野が戦争はもはや目的達成の道具としてふさわしくないと主張する部分だ。執筆時に進行していた朝鮮戦争を例にとって、双方が自分たちの正義を守るために戦い、その結果甚大な被害が発生していると指摘する。戦争が世の中の進歩をもたらしてきた側面があることを認めた上で、科学技術が発達した社会においては、戦争はこれまで築き上げてきた文明を破壊するほどの被害をもたらすようになってしまったと述べる。
本書の根底を貫くのは、戦争をなくすために社会の仕組みや動きを変える必要があり、その方策を若い世代に伝えなくてはいけないという強い思いだ。今でもなお、政治的な対立を武力によって解決しようとする動きが見られる。現代を生きる我々も、戦争による莫大な被害を目の当たりにした吉野の思いから学ぶべきことが多くある。社会に生きる一員として持つべき自覚と取るべき行動を丁寧に伝える一作だ。(史)

政治とは、情熱と判断力の二つを駆使しながら、堅い板に力をこめてじわっじわっと穴をくり貫いていく作業である
『職業としての政治』は、ドイツの社会学者マックス・ヴェーバーが1919年1月、ミュンヘンの学生団体に対し、政治家の備えるべき内的な資質や態度について論じた講演をまとめたもの。脇圭平訳の岩波文庫は厚さが5㍉で本文は100㌻しかないし、同じヴェーバーの代表作『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』に比べると随分とっつきやすそうに見える。
実際、本論の指摘は政治行動の本質をうがつもので、当時の社会状況に明るくなくても問題なく読め、その意味でとっつきやすいといえよう。ヴェーバーは冒頭で、国家が「正当な物理的暴力の行使」を独占していることが、近代国家の政治に固有の特徴だと指摘する。共通テストでも引用されたこの指摘は、ロシアのウクライナ侵攻やイスラエル・ガザ戦争など、国家による対外的な暴力行使が目立つ昨今にも通じるところがあるだろう。
ヴェーバーが暴力の独占を問題としていないことに注意が必要だ。彼の焦点は、暴力の独占に裏打ちされた「権力」を運用する政治家のあるべき姿を明らかにすることにあった。暴力が背後に控えているために、政治は純粋に倫理的な行動であれば正当化する「心情倫理」を超えた倫理を要求する。それは、権力行使の結果を予見し、行動に対して責任を負う「責任倫理」であり、ヴェーバーは政治を行うものがこの2つの倫理を自らに課し、その対立を超克すべきと説いた。
新聞を発行する団体の一員として、ヴェーバーがジャーナリストを職業政治家の一類型に挙げた点は興味深い。彼は、政治的影響力を持ち、人々の求めに応じて責任感を持って納得のいく意見を表明できるジャーナリストが政治的指導者としての資質を持つと考えた。実際にジャーナリストが指導者となることは少ないが、この理由として、学者や代議士と比べて、収入や交際が不安定であることを挙げている。政界に進んだジャーナリストといえば、日本では戦前から自由主義の精神を先取した論客として知られた石橋湛山などが思い浮かぶ。しかし、IT化の進展に伴ってマス・メディアの影響力や社会的位置は縮小しており、ヴェーバーの描いたジャーナリストのあり方は最早成り立たないようにも思える。
講演当時の時代的状況を踏まえて読むと、本書はなお味わい深い。国家の特徴を「暴力の独占」と前提した本論は、第1次世界大戦後の国際的な平和協調の路線のなかで語られた。当時のドイツはプロイセンの君主制から共和制へ移行する革命のさなかにあったが、革命への世間の陶酔に対するヴェーバーの視線は「誇らしげな名前で飾られたこの乱痴気騒ぎ」と冷ややかだ。10年もすれば「反動の時代」が始まることを予感し(そして実際、この講演から十数年のうちに共和制は崩壊し、ドイツはナチズムの時代に突入する)、革命の陶酔から醒めたとき、いかに反応するかと問いかけた。ヴェーバーの卓見が印象的な1冊である。(汐)
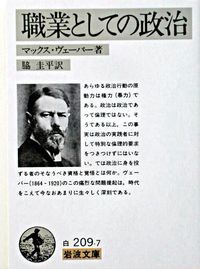
目次
「音楽」や「芸術」は決して最初から「ある」わけではなく、「なる」ものである 国語 第1問『サウンドとメディアの文化資源学―境界線上の音楽』渡辺裕どんなに遠く離れていてもすべては同時に存在していて、自分もその一部にすぎないのだ 国語 第2問『桟橋』牧田真有子
もう今日では、どんな目的を達成するためにも戦争を使うべきではない 倫理,政治・経済 第2問『人間の尊さを守ろう』吉野源三郎
政治とは、情熱と判断力の二つを駆使しながら、堅い板に力をこめてじわっじわっと穴をくり貫いていく作業である 倫理,政治・経済 第5問『職業としての政治』マックス・ヴェーバー
「音楽」や「芸術」は決して最初から「ある」わけではなく、「なる」ものである
国語 第1問『サウンドとメディアの文化資源学―境界線上の音楽』渡辺裕
国語の第1問では『サウンドとメディアの文化資源学―境界線上の音楽』が出題された。作者は現在東京音楽大学で教授を務める音楽学者の渡辺裕。音楽や芸術と社会がどのように関係しているかを研究する第一人者だ。
近年、音楽や芸術そのものを文化的・社会的背景から完全に切り出したかのような状況が数多く見られる。「モーツァルトの曲そのものに感動した」といったように、音楽や芸術は特別視、本文中の言葉を使うと「聖域」視されることが多いという。だが、一般に「音楽」や「芸術」と捉えられているものは社会の影響を色濃く受けて存在するようになる。言い換えると「『音楽』や『芸術』は決して最初から『ある』わけではなく、『なる』ものである」。音楽や芸術も様々なコンテクストの影響を受けた紛れもない「文化」だ。本著ではこのことを核に話が進行していく。
試験問題では、モーツァルト没後200年を記念して行われた特別な追悼ミサを具体例に挙げ、音楽とは何かを論じた箇所を取り上げている。追悼ミサ自体が宗教行事であること、随所に音楽ではない宗教的所作があったことを踏まえると、このミサは典礼と言えそうだ。だが、通常の儀式とは会場の設営が異なったこと、ウィーンの著名な楽団や合唱団が演奏する様子をおさめたDVDが販売されたことを鑑みると、このイベントは音楽とも言えそうだ。このように典礼との二項対立で論じられるほど、簡単には音楽を語れないという。
著者は更に視点を広げ、近年は芸術全般に亘り「博物館化」が進んでいると主張する。博物館の展示コーナーでは「聖域」にあると見なされていた物だけでなく、それを取り巻くコンテクストをも見せるようになった。結果として、人々は「『鑑賞』のまなざし」を幅広く向けているという。前述の追悼ミサも、ミサ内の演奏に限って向けられていた「『鑑賞』のまなざし」が典礼そのものにも向けられるようになったと捉えると、「博物館化」の進行の一例と考察できる。とすると、「『鑑賞』のまなざし」の拡大と共に「聖域」が変化している、すなわち、「音楽」や「芸術」という概念は変容的で、様々なコンテクストの影響を受けて成立すると言えるのではないだろうか。
著者のこの主張には確かに納得がいく。美術評論家の柳宗悦に端を発した「民藝」運動もこの一例だろう。柳が普段の暮らしの中で何気なく使われていた日用品にも「芸術」としての価値を見出した結果、保存活動に力が注がれるようになった。消耗品が至高の美術作品と化したこの現況は、確かに文化的・社会的背景を受けていると言わざるを得ないだろう。また、「音楽」の分野に関しては、タイプライターを叩く音を中心にそえた楽曲「タイプライター」や、演奏者が沈黙を貫き、偶発的に生じた周囲の音に耳を傾ける楽曲「4分33秒」を例に挙げたい。こうした楽曲は、作曲家がそれまでは「音楽」と思われていなかったものに目をつけたことで初めて「音楽」となったと考えられる。
余談だが、ふと立ち止まって考えてみると、この考えと社会学者ソシュールの思想との類似性に気付く。ソシュールは言葉が世界を分節し、分節した瞬間に初めて言葉によって命名されたものが存在するようになると主張した。それまで、我々は認知することが不可能だとも訴えた。要は最初から「ある」わけではなく、言葉で媒介することで対象に「なる」という。著者は音楽社会学者でもあり、ソシュールの思想に触れてきたはずだ。とすると、少なからずソシュールの影響を受けていてもおかしくないのではないか。
ここまで色々と述べてきたが、これらは全て、最初に書かれた総論に収斂する。本書ではここから「音楽」・「芸術」と言えるかが微妙な境界線上に位置する事案を8つ取り上げる。ある章では北海道大学恵迪寮の寮歌「都ぞ弥生」に触れるなど、一つの章で一つの例に言及するため、比較的読みやすい。春休みに時間をもて余すよりは、気になった箇所だけでも構わないから読んでみるのはいかがだろうか。そうした知識もまた、自分の中に最初から「ある」わけではないのだから。(郷)

◆書誌情報
『サウンドとメディアの文化資源学―境界線上の音楽』
渡辺裕/著、春秋社
2013年10月発売
『サウンドとメディアの文化資源学―境界線上の音楽』
渡辺裕/著、春秋社
2013年10月発売
目次へ戻る
どんなに遠く離れていてもすべては同時に存在していて、自分もその一部にすぎないのだ
国語 第2問『桟橋』牧田真有子
『文藝 2017年秋季号』に収録されているこの短編小説は、16歳の高校生イチナが、実家に突然転がり込んできた24歳のおばとの同居生活の中で、自己のあり方を変容させていく物語だ。
「風来坊」のおばは、知り合いの家を転々としながら暮らしている。居候する家から勤め先の縫製工場に通い、休日は自らの立ち上げた劇団の稽古に打ち込む。17歳年上の姉であるイチナの母ははじめ居候に反対していたがしぶしぶ受け入れ、イチナ、両親、おばの4人暮らしが始まった。
イチナがおばと会うのはこれが初めてではない。出題箇所はイチナの幼いころの回想から始まる。幼いイチナにとっておばは「ままごと遊びになぜか本気で付き合ってくれるおねえさん」だった。
居候する理由についてイチナに問われたおばは「私の肉体は家だから、自分の家をほしいとは思えない」と答えた。イチナはこの言葉を「演じるごとに役柄に自分をあけ払うから」ということだと理解した。確固たる自分がいて、その領域を侵されないように守るのではない。おばはいつでも演じているときのように、自分を内側から規定する「枠」から抜け出している。
ある日、おばが演劇の公演のため現地入りするというのでイチナはついていくことにした。おばはイチナに演劇を観に来ることを禁じていたが、舞台は観ないという条件で許可が下りた。その夜、宿でイチナはおばになぜ舞台を観に行ってはいけないのか尋ねた。「私の橋をあなたの橋にはできない」。その答えの意味はイチナにはすぐ理解できなかった。
ここで、驚くべき事実が読者に明かされる。おばは、本当はイチナのおばではない。イチナの母が17歳の時に産んだ子で、戸籍上は祖父母の養子として育てられた。おばには知らされていない秘密だった。しかも、イチナにもまた本人の知らない出生の事情があった。イチナの両親は実の親ではない。おばの父と他の女性との間にできた子で、イチナの母が引き取ったのだ。
法事で訪れた親戚の家で、おばは偶然この秘密を知ってしまう。呆然とするおばは、しかし、何も知らない幼いイチナに真実を告げることなく、彼女のおばを演じる道を選ぶ。
シーンは宿に戻る。眠りから覚めたイチナは、姿を消したおばを探し、入り江から突き出た桟橋にたどり着く。漁港の作業場に血がついているのを目撃した彼女は、何かを問われているように感じ、目を離すことができない。正体のつかめない問いに、その場しのぎの答えを出す。「どんなに遠く離れていてもすべては同時に存在していて、自分もその一部にすぎないのだ」。血は肉体の存在や実存、あるいは血縁を連想させる。イチナは血に確かな実存を読み取り、それが実は自分やおばを含むすべてのものに当てはまることに、無意識のうちに気がついたのだろう。ここにいないおばの存在が、ふいにくっきりとイチナの心に現れる。血というモチーフによってイチナとおばが結び付けられるこの場面は、イチナの身の回りではおばが唯一の血縁者であることを考えるとなかなか心憎い。公演から帰ったおばは荷物をまとめてイチナの家を出て行くのだった。
以来イチナは、おばのあり方を生活に取り入れ始める。「悪の側に立つことになろうが、敗れた存在になろうが、自分を護るために事実に手を加えようとはしなかった。それは自分が自分であるということを後回しにすることでもあった」。自分とイチナの秘密を隠すことから始まった「自分から離れる」ということ。それは他の人とは違うおば独特の生き方として現れ、イチナに伝わっていく。
その後イチナは、おばがイチナに観劇を禁じていた理由が、「橋がねじ切れて桟橋になるから」だったと知る。橋は血縁関係の比喩だろう。おばは、イチナに演じる姿を見られると、それをきっかけとしてイチナと「両親」をつなぐ血縁という橋が本当は桟橋であったこと、つまり血のつながりが存在しないことがイチナに知られてしまうのではと危惧していたのかもしれない。「私の橋をあなたの橋にはできない」というおばの言葉は、変えることのできない血縁という事実に、彼女と同じようにイチナがいつか直面することになることを暗示しているようでさえある。
14ページと短いながら、密度が高く強烈な読後感を残す作品だった。(鷲)

◆書誌情報
『文藝 2017年秋季号』
河出書房新社
2017年7月発売
『文藝 2017年秋季号』
河出書房新社
2017年7月発売
目次へ戻る
もう今日では、どんな目的を達成するためにも戦争を使うべきではない
倫理,政治・経済 第2問『人間の尊さを守ろう』吉野源三郎
吉野源三郎と聞けば、昨年映画化されて話題となった『君たちはどう生きるか』を思い浮かべる人も多いだろう。吉野は1899年生まれで、東京帝国大学を卒業したのち編集者として活動した。本書は第2次世界大戦が終わってから間もない頃に、青少年を対象に執筆した文章をまとめた1冊だ。吉野は戦争を経て変化した社会の仕組みを平易な言葉で語る。共通テストでは、第2次世界大戦が人々の結びつきを崩壊させたとしたうえで、人間への信頼を取り戻す必要があると述べた箇所が引用された。
執筆当時、社会のあり方が大きく転換したことは想像に難くない。吉野は、まず一人ひとりの権利は平等に重んじられるべきだとする「個人主義」について説明する。その上で、社会全体の問題は社会の仕組みやその動きに原因があることが多いため、個人主義では不十分で、「民主主義」の考え方が必要になると述べる。「個人として責任がないことでも、全体のなかのひとりとして、やはり責任を分け合わなくてはいけないことはいろんな場あいにある」。本書を通じて、憲法施行直後に民主主義へ寄せられていた期待をうかがい知ることができる。
民主主義や選挙の話題と並んで、労働組合について解説する章があったことは意外だった。というのも、労働問題は政治的な仕組みと一線を画しているような気がしたからだ。しかし、あとがきを読んでなぜ労働問題を取り上げたのかを理解した。吉野は「民主主義に基づいて法律上すべての国民が一応平等となり、同じ政治的権利を持つようになっても、なお、実際には不平等がなくならないこと、特に経済的な不平等がなくならない」と指摘し、それを打開する1つの方策として労働組合の話に言及したと説明する。
吉野は、労働者階級が社会にとって大事な役割を受け持ちながらも尊敬されないという点で古代の「ドレイ」に近い状態にあることを述べ、労働者が労働組合のもとで団結して行動することで、彼らの役割の重大さを社会に知らせることができるとする。人々は労働を通じて社会に関与しており、労働は個人と社会を繋いでいるという意味で政治的な事柄であるとも考えることができよう。また、日本国憲法が施行された直後に、法律で権利が保障されるだけでは現実は変わらないという鋭い指摘をしていたことに驚いた。
最も印象的だったのは、吉野が戦争はもはや目的達成の道具としてふさわしくないと主張する部分だ。執筆時に進行していた朝鮮戦争を例にとって、双方が自分たちの正義を守るために戦い、その結果甚大な被害が発生していると指摘する。戦争が世の中の進歩をもたらしてきた側面があることを認めた上で、科学技術が発達した社会においては、戦争はこれまで築き上げてきた文明を破壊するほどの被害をもたらすようになってしまったと述べる。
本書の根底を貫くのは、戦争をなくすために社会の仕組みや動きを変える必要があり、その方策を若い世代に伝えなくてはいけないという強い思いだ。今でもなお、政治的な対立を武力によって解決しようとする動きが見られる。現代を生きる我々も、戦争による莫大な被害を目の当たりにした吉野の思いから学ぶべきことが多くある。社会に生きる一員として持つべき自覚と取るべき行動を丁寧に伝える一作だ。(史)

◆書誌情報
『人間の尊さを守ろう』
吉野源三郎/著、ポプラ社
2000年8月発売
『人間の尊さを守ろう』
吉野源三郎/著、ポプラ社
2000年8月発売
目次へ戻る
政治とは、情熱と判断力の二つを駆使しながら、堅い板に力をこめてじわっじわっと穴をくり貫いていく作業である
倫理,政治・経済 第5問『職業としての政治』マックス・ヴェーバー
『職業としての政治』は、ドイツの社会学者マックス・ヴェーバーが1919年1月、ミュンヘンの学生団体に対し、政治家の備えるべき内的な資質や態度について論じた講演をまとめたもの。脇圭平訳の岩波文庫は厚さが5㍉で本文は100㌻しかないし、同じヴェーバーの代表作『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』に比べると随分とっつきやすそうに見える。
実際、本論の指摘は政治行動の本質をうがつもので、当時の社会状況に明るくなくても問題なく読め、その意味でとっつきやすいといえよう。ヴェーバーは冒頭で、国家が「正当な物理的暴力の行使」を独占していることが、近代国家の政治に固有の特徴だと指摘する。共通テストでも引用されたこの指摘は、ロシアのウクライナ侵攻やイスラエル・ガザ戦争など、国家による対外的な暴力行使が目立つ昨今にも通じるところがあるだろう。
ヴェーバーが暴力の独占を問題としていないことに注意が必要だ。彼の焦点は、暴力の独占に裏打ちされた「権力」を運用する政治家のあるべき姿を明らかにすることにあった。暴力が背後に控えているために、政治は純粋に倫理的な行動であれば正当化する「心情倫理」を超えた倫理を要求する。それは、権力行使の結果を予見し、行動に対して責任を負う「責任倫理」であり、ヴェーバーは政治を行うものがこの2つの倫理を自らに課し、その対立を超克すべきと説いた。
新聞を発行する団体の一員として、ヴェーバーがジャーナリストを職業政治家の一類型に挙げた点は興味深い。彼は、政治的影響力を持ち、人々の求めに応じて責任感を持って納得のいく意見を表明できるジャーナリストが政治的指導者としての資質を持つと考えた。実際にジャーナリストが指導者となることは少ないが、この理由として、学者や代議士と比べて、収入や交際が不安定であることを挙げている。政界に進んだジャーナリストといえば、日本では戦前から自由主義の精神を先取した論客として知られた石橋湛山などが思い浮かぶ。しかし、IT化の進展に伴ってマス・メディアの影響力や社会的位置は縮小しており、ヴェーバーの描いたジャーナリストのあり方は最早成り立たないようにも思える。
講演当時の時代的状況を踏まえて読むと、本書はなお味わい深い。国家の特徴を「暴力の独占」と前提した本論は、第1次世界大戦後の国際的な平和協調の路線のなかで語られた。当時のドイツはプロイセンの君主制から共和制へ移行する革命のさなかにあったが、革命への世間の陶酔に対するヴェーバーの視線は「誇らしげな名前で飾られたこの乱痴気騒ぎ」と冷ややかだ。10年もすれば「反動の時代」が始まることを予感し(そして実際、この講演から十数年のうちに共和制は崩壊し、ドイツはナチズムの時代に突入する)、革命の陶酔から醒めたとき、いかに反応するかと問いかけた。ヴェーバーの卓見が印象的な1冊である。(汐)
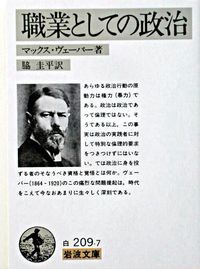
◆書誌情報
『職業としての政治』
マックス・ヴェーバー/著、脇圭平/訳、岩波文庫
1980年3月発売
『職業としての政治』
マックス・ヴェーバー/著、脇圭平/訳、岩波文庫
1980年3月発売


