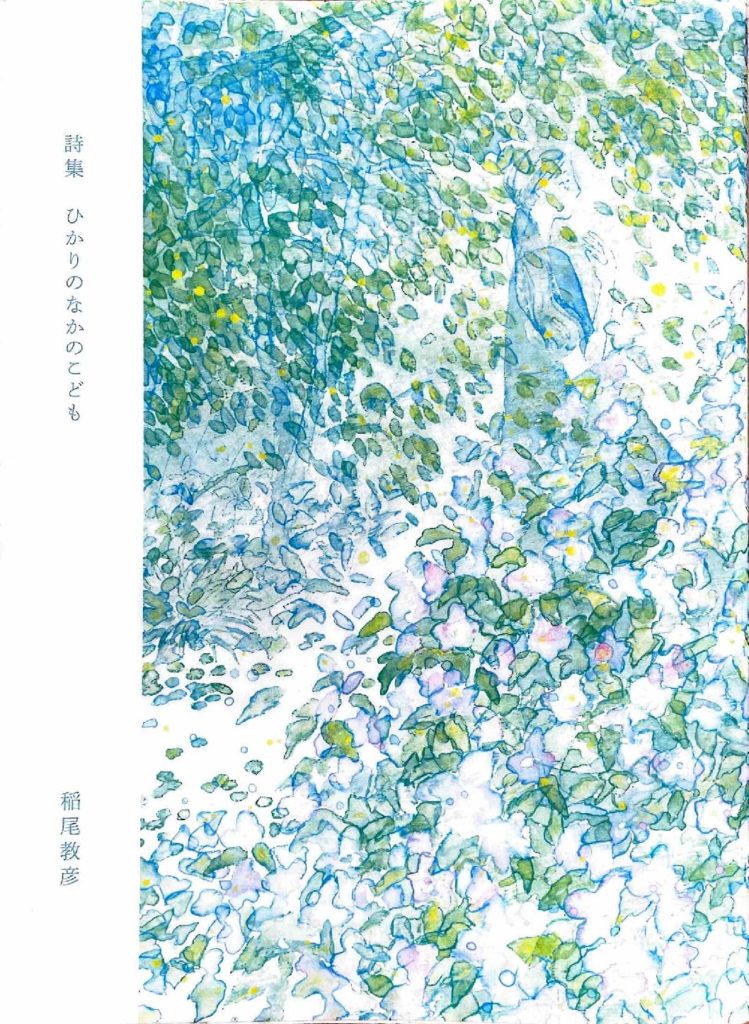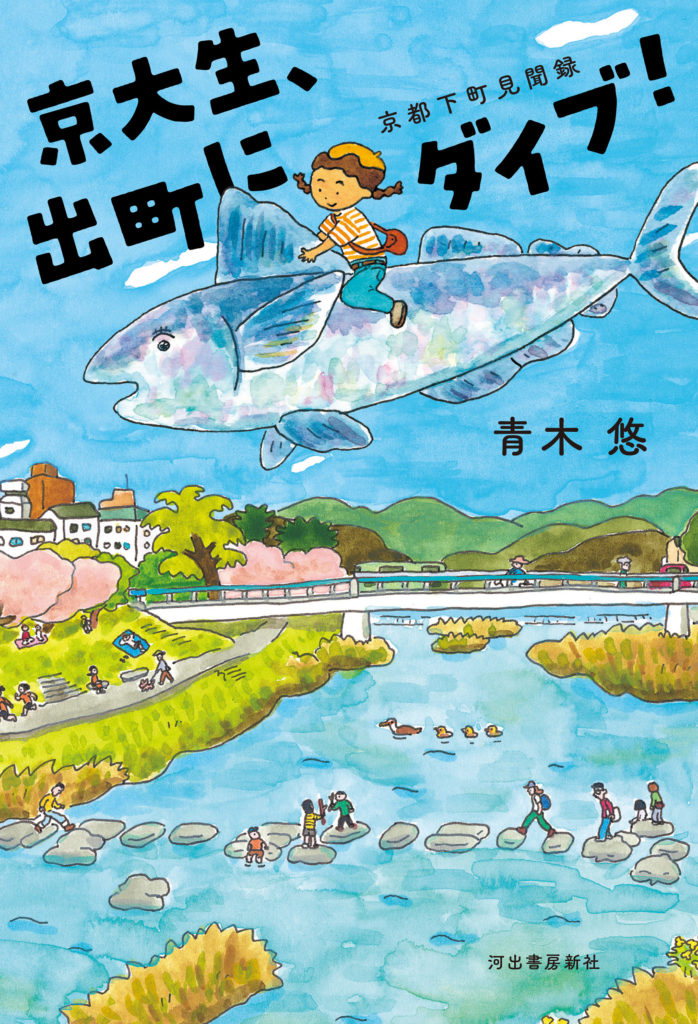京大生の読書傾向を覗き見♪ 年間ルネベスト2024
2025.03.16
本企画では、昨年1年間に京大生協ブックセンター「ルネ」で売れた書籍のランキングと、そこにランクインした本から編集員が選んだ3冊の書評を掲載する。並ぶタイトルは、毎年お馴染みのものから、世相を反映したものまで様々だ。厳しい寒さも緩み、日に日に近づく春の足音に胸が膨らむ今、気になる本を手に取って、静かな春の訪れを堪能してはいかがだろうか。(編集部)
第1位 他者に知られ得ぬ孤独への共感 『百年の孤独』
第19位 酸っぱいりんごも悪くない 『トラタのりんご』
「4千字の期末レポートなんてどう書けばいいかわからない」「思いつくことは全部詰め込んだのに規定の字数に届かない」……締切間近、パソコンの前で頭を抱えながらあらゆる手段を講じてレポートを書き上げ、「こんなはずでは……」と苦々しい思いで提出ボタンを押した経験のある大学生は少なくないだろう。どうすればレポートを、ゆくゆくは論文をうまく書けるようになるのか。さまざまな言説が飛び交うなか、「まったく新しい」という惹句をひっさげて現れた本書は、その名にたがわぬ新たな方法論を提供する。
本書は、まず「論文」に定義を与え、それを満たす文章を書くためにはどうすればよいかを、具体的なトレーニングを読者に課しながら筋道立てて説明する。いわく、「論文とは、アカデミックな価値をもつアーギュメントを提出し、それが正しいことを論証する文章である」。アーギュメントとは、アカデミックな価値とは、正しく論証するとは何か?「原理編」と称された第1~3章で、筆者はこれらの概念をはっきりと言語化し、論文とは何をする場なのかを確実に理解させる。そして、第4~8章の「実践編」では、論文の大半を占める本文の構成単位・パラグラフの洗練のさせ方や、先行研究の引用の仕方、そして論文におけるイントロダクションと結論の意義と書き方のパターンを提示する。
「原理編」で印象的なのは、「論文は飛躍せずして飛躍せねばならない」という第3章の一節だ。論文のイントロダクションで提示されるアーギュメント(論文全体の核となる主張内容)は、非自明で論証を要求するようなアイデアでなければならないが、本文においてはその飛躍を事実と論理によって解消し、誰でも納得できるように説明しなければならない、と論文の本質をまさに言い当てている。
「実践編」の冒頭では、「書けないやつは読めてもいない」というキラーフレーズとともに、「執筆のための読解」にフォーカスが当てられる。ここで紹介される「パラグラフ解析」というテクニックの効果は絶大だ。パラグラフを1文ごとに分解し、その機能を言語化することにより、文章を読み書きするうえで重要な注意力や感度が養われる。筆者の用意したトレーニングをこなしていると、読むことと書くことは根本的には繋がっていることがひしひしと感じられる。そのまま読書術としても応用できそうだ。
本書が類書と一線を画している点は、ただ単に論文を書くための方法論を提供するだけではなく、「なぜ論文を書く必要があるのか」と前提を問い、そこに筆者が一定の回答を与えていることにある。この問いについて議論する第8、9章の「発展編」は、いかにも実用書然としていた「原理編」「実践編」とは異なり、ある種の「論文論」を展開する人文書のような趣きがある。自分の書いている論文に価値はあるのか、なぜ他でもない自分がこの論文を書く必要があるのか、そうした根本的な問いに対して自分なりに答えを出しておくこと。それは、研究を続けるうえでの強靭なモチベーションになるだろうし、自身の研究スタイルの深化にも資するだろう。
筆者は日米の学術的なカルチャーに精通した人文学者であり、本書を通じて解説されるのは「人文学の論文」の書き方である。しかし、理系の学部生である評者にとっても学ぶことは多かった。とくに、第4〜6章で解説されるパラグラフ解析と、先行研究を引用するための論文の読み方は、自然科学の論文に置き換えても十分通用するように思われ、さっそく試してみたくなった。
本書は「教科書」と銘打つものの、いわゆる教科書的な堅苦しさはまったくなく、軽やかかつ明晰な筆致で論文執筆の一から十までを過不足なく解説する。本書に通底する徹底的な実践志向には、「『研究』のスタート地点に最速で立つためのガイド」を標榜する筆者の並々ならぬ心意気が感じられる。人文学にかかわる学生や研究者のみならず、学問にかかわる文章を書くすべての人にお薦めしたい一冊である。(鷲)

本書は1967年に初刊が出版された、ラテンアメリカ文学のベストセラー小説だ。日本での文庫化を期待されつつも長年実現せず、ファンの間では「文庫化したら世界が滅びる」とまで言われていた。そんな中、去年の6月に文庫版がついに新潮社から出版され、話題となった。
本書の舞台は、コロンビアのジャングルの奥地にある蜃気楼の村「マコンド」だ。ブエンディア一族の100年にわたる興亡が、それぞれの内情にスポットライトを当てつつ語られる。
新潮文庫版『百年の孤独』には、ブエンディア家の家系図が付いている。初めて家系図を見た時は、「ホセ・アルカディオ・ブエンディア」「ウルスラ・イグアラン」といった評者には馴染みの薄い南米の名前に正直気おくれした。しかし読み進めるうちに、家系図に書かれた名前を見ると、それぞれの物語が懐かしい思い出のように浮かぶようになった。本書は1世紀にわたって1つの村を地続きに扱う物語であるため、多くの登場人物の人生を追うことが出来る。彼らは成長し、老いて、時にあっさりと死ぬ。家系図を見たときに、ああ、そういう人もいたなと感慨が押し寄せるのである。
さて、本書の魅力は、現実世界と奇妙な世界がまじりあう「マジックリアリズム」と「複数視点」だ。本書の導入部分では、先ほど名前の出たホセ・アルカディオ・ブエンディアについて描かれる。彼はマコンドの開拓者で、優秀なリーダーだ。彼はメルキアデスを名乗るジプシーが棒磁石や望遠鏡を用いて演出した奇跡によって、研究熱に浮かされることがありつつも、リーダーとして人々を導いた。しかし死期が近づくと、彼の前に、旧知の死者が現れるようになる。死者は、ごたごたした死者の国をさまよいながらも彼に会いに来たといい、彼と旧交を温める。その頃から彼は、譫妄状態に陥ったと周囲に認識されるようになる。「月曜日が繰り返されている」とわめいたり、スペイン語圏のマコンドでラテン語の文句をブツブツとつぶやいたり、家の内装を破壊したりする。しかし、彼の視点で語られる世界は至って整合的だ。空や家の壁や花々の様子が、いくら観察しても月曜日から変化がなく、時間が繰り返しているように感じて、月曜日からの脱出を試みて破壊活動といった行動をとる。このように、視点が次々に切り替わり、幽霊や繰り返す月曜日などの非現実な事象が現実にさりげなく差し込まれるため、妄想なのか現実なのかが、読者には判別できなくなってくる。登場人物それぞれの視点から物語が語られるため、それぞれに共感しつつ、自然に奇妙な世界の渦に引き込まれてしまう。
読み進める中で、「孤独」についても思いを馳せた。本書ではそれぞれの登場人物が、何かしら孤独を抱えている。恋愛に悩み、部屋で一人、土を食べ指をしゃぶる癖を繰り返す孤独。若くして最愛の人を亡くし、性的衝動だけが胸に燻る孤独。誰にも研究内容を理解されない孤独。本来他者には知られ得ぬ孤独を知ることで、当然同じく孤独を抱える私は、彼らにより深く共感していく。人間感情の克明な描写と、時おり顔をだす奇妙奇天烈な事象を楽しんで欲しい。(雲)

冬が近づくとスーパーの店先に並ぶりんごを想像してほしい。色は赤か緑、あるいはしましま。かじると、どんな味がするだろうか。おそらく、多くの人が甘い味を思い浮かべるのではないだろうか。
「トラタのりんご」は、そんなりんごが大好きな少年、トラタが主人公だ。ある日、トラタはふとしたきっかけから、ある果樹園に迷い込む。そこには、見たことのないりんごがたくさんなっていた。1つ手に取ってかじってみると、お店の甘いりんごと違って、酸っぱい。「でも、なんだかちょっとおいしいかも」。
酸っぱいりんごが気になったトラタは、家にあるりんごの図鑑で、果樹園でみたりんごを調べる。興味をもったことを(信頼できる情報源から)すぐ調べてみるのはトラタのいいところだし、りんごが大好きなトラタに、りんごの図鑑を贈った大人の心遣いも素敵だ。果樹園でみたりんごが、今ではあまり育てられなくなった古い品種と知って、トラタはますますりんごに興味を持つようになる。
大学生協の書籍コーナーの売り上げ上位に来ているとあって、意外に思われるかもしれないが、本作は児童向けの絵本である。京大iPS研の三成寿作氏が、「社会における科学技術のあり方」を、考え話し合うきっかけになればと企画し、画家のnakaban氏が制作した。企画者が京大の教員ということで、ルネで売れているのだろう。
企画意図を明確に打ち出しているせいで、自由な絵本の解釈が制限されている気はしなくもない。だが、企画者の意図に共感して、考えたり、話し合ったりするきっかけを求めているなら、この本は絶好の入口になるはずだ。単に「科学技術のあり方について話し合おう」と切り出しても、テーマの堅苦しい印象にひるんだり、お行儀の良い「正解」にたどり着いたりして、話が終わってしまうかもしれない。子どもどうし、あるいは大人も一緒になって、自然体で考え話し合おうとするなら、とっつきやすい「りんごの絵本」という体裁はちょうど良いように思える。
品種改良のような科学技術は、特定の価値に焦点をあてて、それを伸ばすような形で物事を発達させてきた。お店で売られるりんごは、甘みを重視したのか、はたまた別の理由で偶然甘い品種が好まれたのか、みな一様に甘い。もちろん、りんごが甘くて美味しいのは良いことだし、規格化されたりんごが増えれば、生産性もあがるだろう。だが、その副作用として、もともとその物が持っていた多様な魅力を消し去ってしまうこともある。トラタが気づいたように、甘くないりんごにも美味しさがある。
生活の諸側面に科学技術が入り込むようになって、随分経った。これまで、科学技術が重視してこなかったために、なくなりつつあるものの価値を、再検討する時が来ているのかもしれない。失われつつある良さに光をあてたとき、それを取り戻そうと思うのは自然なことだろう。一方、りんごは甘ければそれで良いのであって、失われた「酸っぱいりんご」をわざわざ取り戻す必要はない、というのも1つの考え方だ。どちらの立場をとるとしても、科学技術による改良の陰で、見えなくなってきたものがあると気づき、それがどういうものか知ることが大切だ。その点で、トラタから学ぶところは多そうだ。(汐)

目次
第4位 すべての書き手に贈る最良の指南書 『まったく新しいアカデミック・ライティングの教科書』第1位 他者に知られ得ぬ孤独への共感 『百年の孤独』
第19位 酸っぱいりんごも悪くない 『トラタのりんご』
| 順位 | 書名 | 著者 |
|---|---|---|
| 1 | 百年の孤独 | ガブリエル・ガルシア=マルケス |
| 2 | なぜ働いていると本が読めなくなるのか | 三宅香帆 |
| 3 | 思考の整理学 | 外山滋比古 |
| 4 | まったく新しいアカデミック・ライティングの教科書 | 阿部幸大 |
| 5 | シャーロック・ホームズの凱旋 | 森見登美彦 |
| 6 | 成瀬は天下を取りにいく | 宮島未奈 |
| 7 | アルジャーノンに花束を | ダニエル・キイス |
| 8 | 三体 | 劉慈欣 |
| 9 | 勉強の哲学 | 千葉雅也 |
| 10 | 成瀬は信じた道をいく | 宮島未奈 |
| 11 | 暇と退屈の倫理学 | 國分功一郎 |
| 12 | 正欲 | 朝井リョウ |
| 13 | ケアの倫理 | 岡野八代 |
| 14 | 夜は短し歩けよ乙女 | 森見登美彦 |
| 14 | センスの哲学 | 千葉雅也 |
| 14 | 構造と力 | 浅田彰 |
| 17 | 四畳半神話大系 | 森見登美彦 |
| 17 | 歴史学はこう考える | 松沢裕作 |
| 19 | トラタのりんご | nakaban |
| 20 | 論理的思考とは何か | 渡邉雅子 |
| 21 | 現代思想入門 | 千葉雅也 |
| 22 | 三体Ⅱ 黒暗森林 上 | 劉慈欣 |
| 23 | 冬期限定ボンボンショコラ事件 | 米澤穂信 |
| 23 | 三体Ⅱ 黒暗森林 下 | 劉慈欣 |
| 23 | 傲慢と善良 | 辻村深月 |
| 26 | 八月の御所グラウンド | 万城目学 |
| 27 | 哲学史入門Ⅰ | 千葉雅也 ほか |
| 27 | 言語の本質 | 今井むつみ、秋田喜美 |
| 29 | 世界はラテン語でできている | ラテン語さん |
| 29 | 言語哲学がはじまる | 野矢茂樹 |
| 31 | 人生は20代で決まる | メグ・ジェイ |
| 32 | コンビニ人間 | 村田沙耶香 |
| 32 | 検証 ナチスは「良いこと」もしたのか? | 小野寺拓也、田野大輔 |
| 34 | すべての、白いものたちの | ハン・ガン |
| 35 | ジェンダー史10講 | 姫岡とし子 |
| 35 | スマホ脳 | アンデシュ・ハンセン |
| 35 | 哲学史入門Ⅱ | 上野修 ほか |
| 38 | 嫉妬論 | 山本圭 |
| 39 | 三体Ⅲ 死神永生 下 | 劉慈欣 |
| 39 | 鴨川ホルモー | 万城目学 |
| 39 | 哲学史入門Ⅲ | 谷徹 ほか |
| 39 | 世界でいちばん透きとおった物語 | 杉井光 |
| 39 | 三体Ⅲ 死神永生 上 | 劉慈欣 |
| 44 | 実力も運のうち 能力主義は正義か? | マイケル・サンデル |
| 44 | 問いの立て方 | 宮野公樹 |
| 46 | ブッダに学ぶ老いと死 | 山折哲雄 |
| 46 | プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神 | マックス・ヴェーバー |
| 46 | 資本論 第一巻 上 | カール・マルクス |
| 49 | 金閣寺 | 三島由紀夫 |
| 50 | 日本哲学入門 | 藤田正勝 |
| 50 | 統治される大学 | 駒込武 |
| 50 | 黒牢城 | 米澤穂信 |
| 50 | 異世界エルフと京大生 | 森田季節 |
| 50 | 数学者の思案 | 河東泰之 |
データ提供:京大生協ブックセンタールネ
※ただし、教科書類は編集部で除外しています。
※ただし、教科書類は編集部で除外しています。
第4位 すべての書き手に贈る最良の指南書 『まったく新しいアカデミック・ライティングの教科書』
「4千字の期末レポートなんてどう書けばいいかわからない」「思いつくことは全部詰め込んだのに規定の字数に届かない」……締切間近、パソコンの前で頭を抱えながらあらゆる手段を講じてレポートを書き上げ、「こんなはずでは……」と苦々しい思いで提出ボタンを押した経験のある大学生は少なくないだろう。どうすればレポートを、ゆくゆくは論文をうまく書けるようになるのか。さまざまな言説が飛び交うなか、「まったく新しい」という惹句をひっさげて現れた本書は、その名にたがわぬ新たな方法論を提供する。
本書は、まず「論文」に定義を与え、それを満たす文章を書くためにはどうすればよいかを、具体的なトレーニングを読者に課しながら筋道立てて説明する。いわく、「論文とは、アカデミックな価値をもつアーギュメントを提出し、それが正しいことを論証する文章である」。アーギュメントとは、アカデミックな価値とは、正しく論証するとは何か?「原理編」と称された第1~3章で、筆者はこれらの概念をはっきりと言語化し、論文とは何をする場なのかを確実に理解させる。そして、第4~8章の「実践編」では、論文の大半を占める本文の構成単位・パラグラフの洗練のさせ方や、先行研究の引用の仕方、そして論文におけるイントロダクションと結論の意義と書き方のパターンを提示する。
「原理編」で印象的なのは、「論文は飛躍せずして飛躍せねばならない」という第3章の一節だ。論文のイントロダクションで提示されるアーギュメント(論文全体の核となる主張内容)は、非自明で論証を要求するようなアイデアでなければならないが、本文においてはその飛躍を事実と論理によって解消し、誰でも納得できるように説明しなければならない、と論文の本質をまさに言い当てている。
「実践編」の冒頭では、「書けないやつは読めてもいない」というキラーフレーズとともに、「執筆のための読解」にフォーカスが当てられる。ここで紹介される「パラグラフ解析」というテクニックの効果は絶大だ。パラグラフを1文ごとに分解し、その機能を言語化することにより、文章を読み書きするうえで重要な注意力や感度が養われる。筆者の用意したトレーニングをこなしていると、読むことと書くことは根本的には繋がっていることがひしひしと感じられる。そのまま読書術としても応用できそうだ。
本書が類書と一線を画している点は、ただ単に論文を書くための方法論を提供するだけではなく、「なぜ論文を書く必要があるのか」と前提を問い、そこに筆者が一定の回答を与えていることにある。この問いについて議論する第8、9章の「発展編」は、いかにも実用書然としていた「原理編」「実践編」とは異なり、ある種の「論文論」を展開する人文書のような趣きがある。自分の書いている論文に価値はあるのか、なぜ他でもない自分がこの論文を書く必要があるのか、そうした根本的な問いに対して自分なりに答えを出しておくこと。それは、研究を続けるうえでの強靭なモチベーションになるだろうし、自身の研究スタイルの深化にも資するだろう。
筆者は日米の学術的なカルチャーに精通した人文学者であり、本書を通じて解説されるのは「人文学の論文」の書き方である。しかし、理系の学部生である評者にとっても学ぶことは多かった。とくに、第4〜6章で解説されるパラグラフ解析と、先行研究を引用するための論文の読み方は、自然科学の論文に置き換えても十分通用するように思われ、さっそく試してみたくなった。
本書は「教科書」と銘打つものの、いわゆる教科書的な堅苦しさはまったくなく、軽やかかつ明晰な筆致で論文執筆の一から十までを過不足なく解説する。本書に通底する徹底的な実践志向には、「『研究』のスタート地点に最速で立つためのガイド」を標榜する筆者の並々ならぬ心意気が感じられる。人文学にかかわる学生や研究者のみならず、学問にかかわる文章を書くすべての人にお薦めしたい一冊である。(鷲)

◆書誌情報
『まったく新しいアカデミック・ライティングの教科書』
阿部幸大/著
光文社
2024年
『まったく新しいアカデミック・ライティングの教科書』
阿部幸大/著
光文社
2024年
目次へ戻る
第1位 他者に知られ得ぬ孤独への共感 『百年の孤独』
本書は1967年に初刊が出版された、ラテンアメリカ文学のベストセラー小説だ。日本での文庫化を期待されつつも長年実現せず、ファンの間では「文庫化したら世界が滅びる」とまで言われていた。そんな中、去年の6月に文庫版がついに新潮社から出版され、話題となった。
本書の舞台は、コロンビアのジャングルの奥地にある蜃気楼の村「マコンド」だ。ブエンディア一族の100年にわたる興亡が、それぞれの内情にスポットライトを当てつつ語られる。
新潮文庫版『百年の孤独』には、ブエンディア家の家系図が付いている。初めて家系図を見た時は、「ホセ・アルカディオ・ブエンディア」「ウルスラ・イグアラン」といった評者には馴染みの薄い南米の名前に正直気おくれした。しかし読み進めるうちに、家系図に書かれた名前を見ると、それぞれの物語が懐かしい思い出のように浮かぶようになった。本書は1世紀にわたって1つの村を地続きに扱う物語であるため、多くの登場人物の人生を追うことが出来る。彼らは成長し、老いて、時にあっさりと死ぬ。家系図を見たときに、ああ、そういう人もいたなと感慨が押し寄せるのである。
さて、本書の魅力は、現実世界と奇妙な世界がまじりあう「マジックリアリズム」と「複数視点」だ。本書の導入部分では、先ほど名前の出たホセ・アルカディオ・ブエンディアについて描かれる。彼はマコンドの開拓者で、優秀なリーダーだ。彼はメルキアデスを名乗るジプシーが棒磁石や望遠鏡を用いて演出した奇跡によって、研究熱に浮かされることがありつつも、リーダーとして人々を導いた。しかし死期が近づくと、彼の前に、旧知の死者が現れるようになる。死者は、ごたごたした死者の国をさまよいながらも彼に会いに来たといい、彼と旧交を温める。その頃から彼は、譫妄状態に陥ったと周囲に認識されるようになる。「月曜日が繰り返されている」とわめいたり、スペイン語圏のマコンドでラテン語の文句をブツブツとつぶやいたり、家の内装を破壊したりする。しかし、彼の視点で語られる世界は至って整合的だ。空や家の壁や花々の様子が、いくら観察しても月曜日から変化がなく、時間が繰り返しているように感じて、月曜日からの脱出を試みて破壊活動といった行動をとる。このように、視点が次々に切り替わり、幽霊や繰り返す月曜日などの非現実な事象が現実にさりげなく差し込まれるため、妄想なのか現実なのかが、読者には判別できなくなってくる。登場人物それぞれの視点から物語が語られるため、それぞれに共感しつつ、自然に奇妙な世界の渦に引き込まれてしまう。
読み進める中で、「孤独」についても思いを馳せた。本書ではそれぞれの登場人物が、何かしら孤独を抱えている。恋愛に悩み、部屋で一人、土を食べ指をしゃぶる癖を繰り返す孤独。若くして最愛の人を亡くし、性的衝動だけが胸に燻る孤独。誰にも研究内容を理解されない孤独。本来他者には知られ得ぬ孤独を知ることで、当然同じく孤独を抱える私は、彼らにより深く共感していく。人間感情の克明な描写と、時おり顔をだす奇妙奇天烈な事象を楽しんで欲しい。(雲)

◆書誌情報
ガブリエル・ガルシア=マルケス/著、鼓直/訳
『百年の孤独』(新潮文庫刊)
2024年
ガブリエル・ガルシア=マルケス/著、鼓直/訳
『百年の孤独』(新潮文庫刊)
2024年
目次へ戻る
第19位 酸っぱいりんごも悪くない 『トラタのりんご』
冬が近づくとスーパーの店先に並ぶりんごを想像してほしい。色は赤か緑、あるいはしましま。かじると、どんな味がするだろうか。おそらく、多くの人が甘い味を思い浮かべるのではないだろうか。
「トラタのりんご」は、そんなりんごが大好きな少年、トラタが主人公だ。ある日、トラタはふとしたきっかけから、ある果樹園に迷い込む。そこには、見たことのないりんごがたくさんなっていた。1つ手に取ってかじってみると、お店の甘いりんごと違って、酸っぱい。「でも、なんだかちょっとおいしいかも」。
酸っぱいりんごが気になったトラタは、家にあるりんごの図鑑で、果樹園でみたりんごを調べる。興味をもったことを(信頼できる情報源から)すぐ調べてみるのはトラタのいいところだし、りんごが大好きなトラタに、りんごの図鑑を贈った大人の心遣いも素敵だ。果樹園でみたりんごが、今ではあまり育てられなくなった古い品種と知って、トラタはますますりんごに興味を持つようになる。
大学生協の書籍コーナーの売り上げ上位に来ているとあって、意外に思われるかもしれないが、本作は児童向けの絵本である。京大iPS研の三成寿作氏が、「社会における科学技術のあり方」を、考え話し合うきっかけになればと企画し、画家のnakaban氏が制作した。企画者が京大の教員ということで、ルネで売れているのだろう。
企画意図を明確に打ち出しているせいで、自由な絵本の解釈が制限されている気はしなくもない。だが、企画者の意図に共感して、考えたり、話し合ったりするきっかけを求めているなら、この本は絶好の入口になるはずだ。単に「科学技術のあり方について話し合おう」と切り出しても、テーマの堅苦しい印象にひるんだり、お行儀の良い「正解」にたどり着いたりして、話が終わってしまうかもしれない。子どもどうし、あるいは大人も一緒になって、自然体で考え話し合おうとするなら、とっつきやすい「りんごの絵本」という体裁はちょうど良いように思える。
品種改良のような科学技術は、特定の価値に焦点をあてて、それを伸ばすような形で物事を発達させてきた。お店で売られるりんごは、甘みを重視したのか、はたまた別の理由で偶然甘い品種が好まれたのか、みな一様に甘い。もちろん、りんごが甘くて美味しいのは良いことだし、規格化されたりんごが増えれば、生産性もあがるだろう。だが、その副作用として、もともとその物が持っていた多様な魅力を消し去ってしまうこともある。トラタが気づいたように、甘くないりんごにも美味しさがある。
生活の諸側面に科学技術が入り込むようになって、随分経った。これまで、科学技術が重視してこなかったために、なくなりつつあるものの価値を、再検討する時が来ているのかもしれない。失われつつある良さに光をあてたとき、それを取り戻そうと思うのは自然なことだろう。一方、りんごは甘ければそれで良いのであって、失われた「酸っぱいりんご」をわざわざ取り戻す必要はない、というのも1つの考え方だ。どちらの立場をとるとしても、科学技術による改良の陰で、見えなくなってきたものがあると気づき、それがどういうものか知ることが大切だ。その点で、トラタから学ぶところは多そうだ。(汐)

◆書誌情報
『トラタのりんご』
nakaban/作
岩波書店
2023年
『トラタのりんご』
nakaban/作
岩波書店
2023年