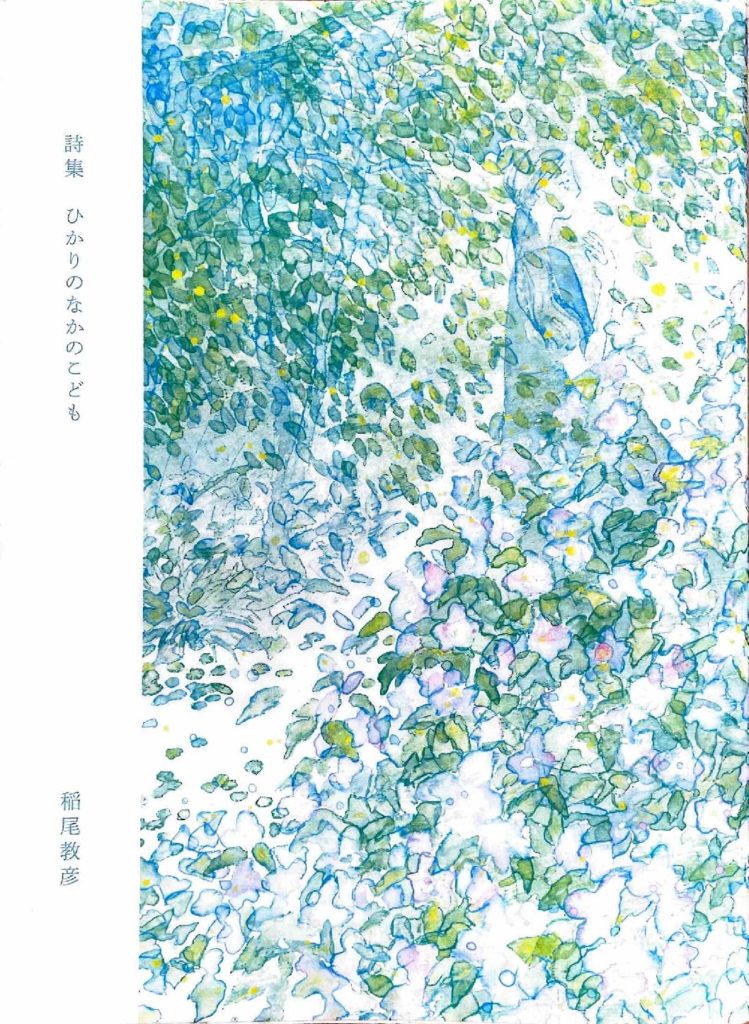解かずに”読む”共テ書評2025
2025.02.16
共通テスト「国語」や「公共、倫理」で出題される文章題は、世相や世代にあったテーマを扱う文献から引用されることも多く、じっくり読むと意外に面白い。とはいえ問題を解く立場だと、問題文をのんびり読んでる場合ではないし、内容にちょっと興味を持ったとしても、試験後の忙しさにかまけて忘れてしまう受験生が少なくないのではないだろうか。
京大新聞では例年、その年の共テ問題文の出典から数冊をピックアップし、その書評を掲載している。本面をきっかけに出題文を思い出し、受験後にでも読んでみようか、と思ってもらえれば幸いだ。(編集部)
〝触角の取れた虫。方向感覚を破壊された鳥〟 国語 第2問「繭の遊戯」
たくさんの本を読み、物知りになることは、「博学」とは違う 国語 第5問『論語』
〝美的体験はそれ自身が一つの倫理、一つの「実践」、生の実現の一つのあり方となる〟 公共、倫理 第3問『見えないものを見るカンディンスキー論』
〝観光とは見ることである。それはさながら呪文のようでもある〟
「観光は見ることである」。本文中で「呪文」と称され、繰り返し用いられるこの文言を軸に、観光社会学者・高岡文章氏の論考は展開する。所収本の題『〈みる/みられる〉のメディア論』が示唆する通り、本論は徹頭徹尾「見る」ことと「観光」の関係に焦点を当てつつ、「見ない」「する」「見られる」といった、見る行為の変容にも目を向けていく。
本論はまず「見る」ことを俎上に載せる。見ることが認識における主軸である、とするフーコーの認知論を基盤として、20世紀の終わり、社会学者のアーリは観光もまた見ることに規定されていると述べた(『観光のまなざし』)。この考え方が後世の研究を規定し、観光学と「まなざし」の概念は不可分となった。そして「観光は見ることである」という呪文が生まれた、と筆者は述べる。と同時に、筆者はアーリの研究を更に援用しつつ、観光における「見ない」という行為にも着目する。個人のまなざしは社会的・文化的な制度に規定され、「まなざしには常に選別がともなっている」というのだ。この主張には大いに頷けるものがある。京都でも、花見小路通を歩く観光客は花街や芸者の華やかさばかりに視線を注ぎ、時に彼女たちが直面してきた悲惨な状況からは目を背けるのだから。
続いて論考は、「見る」と「する」への対比へと進む。筆者は「見る」観光の受動的・疎外的な一面を指摘しつつ、その反動として生まれた「する」観光について言及する。農山漁村での生活体験、地元住民のガイドによる街歩きなど、能動的な「体験」や「交流」を核とする新しい観光を例示し、アーリの観光論を乗り越えようとする新たな研究にも触れる。呪文によって見ることに縛られていた観光は、「する」という新たな視座を得ていく。
終盤では「見る」主体と客体の入れ替わりや、視線を注ぐ対象の変容が議論される。かつての観光は観光客が生活者を見ていたのに対し、今では生活者も観光客を見ているという「相互のまなざし」論が、オーバーツーリズムに憤る生活者の例を介して紹介される。デジタルネイティブ世代としてとりわけ興味深いのは、ネット時代における「見る対象」の変化を取り上げた部分だ。かつて観光客は自己の外にある「世界」を見ていたのに対し、今や行く先々で自撮り写真の撮影者/投稿者となり、写真の中の世界ではなく、そこに映る「自分自身」を注視している。人々は世界を「撮り」「シェアする」ことに没頭している、という鋭い指摘や、「この世界がもはや『映え』の残り滓でしかないのかもしれない」という一節は、評者を含め多くの現代人にとって耳の痛い忠告ではないだろうか。
試験問題では中盤部分が引用された。アーリを初め多数の論者の研究が引用されており、読み進めるのに難儀した受験生も多かったことだろう。とはいえ、全12ページとは思えないほど内容は充実し、旅好きにもそうでない人にも示唆に富む論考となっている。受験が終わったら、仲間と共に旅行に出かける人もいるかもしれない。その前に一読し、自らの「観光」に対する観念を見つめ直してみてはいかがだろうか。(晴)

〝触角の取れた虫。方向感覚を破壊された鳥〟
本作は、短編よりも短い「掌編」小説で、本文は10ページほどしかない。しかし、5歳ほどの「わたし」と働かずに小屋に籠るおじさんとのやり取りを通じて描かれる彼らの心模様や、詩人である著者によって散りばめられた比喩表現は掌には収まりきりそうにないほどだ。
一読すれば「繭」というのが、おじさんの暮らす小屋の比喩であることは容易に理解できる。では、「遊戯」とは何を示しているのだろうか。おじさんの振る舞い、「わたし」の葛藤、ふたりの交流、あるいはその全てだろうか。いずれにせよ「遊戯」とは「仕事」の対局にあるものだ。おじさんは「大人」だが、仕事をしてお金を稼いでいない、いわゆる「ニート」のような状態で、そのことで母をはじめ家族中から疎まれているのだった。
そんなおじさんは小屋でギターを弾いたり、絵を描いたりしていた。どれも技術的に優れているというわけではないが、一つ一つにこだわりや思い入れがあるようで、それが彼を魅力的に映す。そして、部屋に「インドの匂い」を漂わせシードルの瓶の口を舐める様は、世間の価値観に迎合せず、自由を謳歌する生き方をも思わせる。
おじさんはある日、オカリナを「わたし」に見せ、「売るんだ」と得意げに告げる。正しく音階を奏でることはできないようだが、独自の運指法を書いた紙まで用意していた。彼もお金を稼ごうと思っていたのだ。実は周囲の目が気になっていたのか、ただ生活費が必要になったのか。ここで、彼も彼なりに葛藤していたのではないかということ、また、誰もがお金を稼ぐ必要性からは逃れられないということを突き付けられる。そして、彼の生活は「自由な生き方」などと賛美できるものではなく、所詮は「遊戯」に過ぎないのではないかという考えが頭に浮かぶ。そもそもオカリナを売るといっても大した金額にはならないだろうし、お金を稼ぐ手段としては不十分だろう。そんな他人には価値のないように見えることに熱心に取り組む、「触角の取れた虫」「方向感覚を破壊された鳥」のようなおじさんは、一体どこへ向かうのか。行く先は最後まで示されていない。
実際におじさんのような人物が身内にいたら、母のような反応になるのも当然だろう。中には、読んでいるだけで、その無責任さに苛立ちを覚える人もいるかもしれない。そして、「働いてお金を稼ぐ」ことが正しい大人の姿であるという価値観をつい自明視しがちだ。私自身はというと、就活の影もちらつく中で、自然とその道を歩み始めていた。物語はその考えを、取り立てて否定するわけではない。ただ、少しの間立ち止まってその行き先を見つめ直す機会を与えてくれる、そんな掌編だ。(省)
たくさんの本を読み、物知りになることは、「博学」とは違う
漢文を題材とした大問5では、3つの文章が出題された。1つ目の『論語』は、言わずと知れた古代中国の大思想家・孔子の言行録である。2つ目は、18世紀から19世紀初めに活躍した江戸時代の儒学者・皆川淇園の論語注釈書、3つ目は、淇園の弟子である田中履堂のいわば読書論である。時間にすれば、2200年以上の歳月を経た共演である。
今年の漢文では、「博識な人」をめぐる議論が扱われた。孔子は弟子の子貢に問う。「君は私がたくさん学び、多くの知識を覚えていると思うか」。もちろん子貢はハイと答える。しかし、これに対して孔子は、「違う、私は一つのことを貫いている」と答えた。ここに込められたメッセージについて、淇園はこう解釈する。「学問の方法とは、いたずらに多くを求めて雑多にしてはいけない、それではむしろ愚かになってしまう。何か道を見つけて、これを主として進むべきだ(学問之法、不可貪多務博、龐雑冗乱、反闇其智)」。また弟子の履堂も、「万巻の本に大雑把に目を通すよりも、一冊の本を深く理解したほうがよい(粗涉万卷、不如精通一卷)」とする淇園の言葉を引用しつつ、多くの本を読んでいる人は、物知りとは言えても、「博」学とは言えないと述べる。
世間はたくさんの本を読んで多く覚えている人を「博識な人」と言い、羨むかもしれない。しかし履堂の言葉を借りながらまとめると、「博」とは、何かに精通しているという意味であって、単なる物知りとは違う。一冊の書物に精通していれば、これもまた博学というべきである。(なるほど、特定の分野の専門家である博士には、「博」の字がついている。)
おそらく情報過多になりがちな現代の、「ファスト文化」に対する出題者らの問題提起であろう。アニメにせよ、ドラマにせよ、映画にせよ、早送りにしたり、切り抜きだけで楽しんだりする風潮がある。この方が、零細な隙間時間でも見られるし、周りの人の話についていくためには効率がいい。また、ビジネスシーンでうまく立ち回るために、手早く「教養」と呼ばれるようなものをおおざっぱに仕入れていく「ファスト教養」も流行っている。言うなれば、情報の破片が飛び散っている状況で、人々はそれらを集めて、「効率よく」かき揚げみたいに言葉を生産している。(なおこのような情報収集は生成AIの最も得意とするところである。)出題者は、現代社会に生きる受験生に対して、雑多な情報を集めるのに終始するのではなく、大学で腰を据えて学問に励んでほしいという思いを、古の聖賢たちに代弁させたのかもしれない。
大学生も胸に手を当てるべきだ。日々バイトやサークルに追われ、「忙しい」をステータスのように振りかざしながら、テストの直前では教科書の原文に当たらず、レジュメを切り貼りしたような答案やレポートを書いてしまった経験はあるだろう。一方で、「日々書を読んでいる自分とは関係ない」という人もいるだろう。自由な学風に甘やかされて、好奇心の赴くままに本を読んでいるといえば聞こえはいいものの、「専門性」と問われると困ってしまう人も中にはいるに違いない。これは別のレイヤーの問題ではあるが、評者もまたその一人である。最初にこの文章を読んだ時は、頭をガーンと殴られた気持ちだった。
反論したいがぐうの音も出ないのが古典というものかもしれない。バイトやサークルに勤しんでいる人も、勉強らしきことをしている人にも等しくクリティカルヒットを与える。だからと言って、それが全部正しいとも思わない。時代背景が違うし、ユークリッドは「学問に王道はない」と言っている。これ以上の学問論は学部3年生の手に負える話題ではないが、現代に生きる我々も古典を紐解いて、自分の学びを点検してみるのは面白いかもしれない。(唐)

〝美的体験はそれ自身が一つの倫理、一つの「実践」、生の実現の一つのあり方となる〟
本書は、画家カンディンスキーの抽象絵画を題材に、哲学者ミシェル・アンリが自身の「生の現象学」を深化させた思想書である。フランスで哲学を学び、同じく20世紀の哲学者であるフッサールやハイデガーに影響を受けたアンリは、既存の現象学(哲学の一分野)では人間の「生」を十分に捉えきれないと考え、独自の「生の現象学」を打ち立てた。芸術にも深い造詣を持つ彼は、「生の現象学」の視座から絵画を眺め、「芸術とは尽きることのない生の復活」であると結論づけた。
この結論だけ聞くと凡庸に思えるかもしれないが、その思考過程は「生」に対して誠実であり納得のいくところも多い。アンリはまず、現象学の伝統的な枠組みを批判する。フッサール現象学では知覚的な経験により私たちの「生」は形づくられると見做すが、そのアプローチでは日常を過ごす中で感じる「生」の生々しさを掬い取れない。「生」の実感は、知覚対象に定まる前のプリミティブな自己を、隔たりなしに感受することで得られる。ここでの隔たりとは時間的な距離を意味する。フッサールの「把持―原印象―予持」(『内的時間意識の現象学』)において、意識とは時間であった。時間的な隔たりがひととものの間に設けられた結果、対象や客観が現れる(見える)ならば、この隔たりをゼロへと極限するとき、主観性はその内側から自己を触発として感じるだろう。そうして己を内的に知ることを、感情、と言い換えると、感情こそが主観性の自己を成り立たせていると考えられる。アンリによれば、知覚と感情の共存・共生(情感性)によって初めて、「生」がアクチュアルに体感されるのである。
フッサール現象学によると、意識は、感覚による体験としての現れ(現出)から、ある志向に基づいて(志向性)、知覚による経験としての現れ(現出者)へと向かうとされる。例えば、平面上に立体的に描かれた机と思しきイラストを見るとき、目に映る通りの平行四辺形(現出)は、それは机であり机の形は通常平行四辺形ではなく長方形であるという意味づけに照らし合わせること(志向性)により、長方形(現出者)として即座に知覚される。しかしこのような意識のプロセスでは、志向性において少なからず目的的で緊密な連関が生じ、それは実用性や合理性と結びつきかねない。そうなると「現出から現出者へ」という意識の流れは、遊びのない、息苦しいものとなって、本来的な「生」の実感を隠蔽してしまうだろう。実際に私たち現代人の多くが、志向性に囚われているために情感性が機能せず、「生」の充足感を得られない日々を送っている、とアンリは指摘する。
そのような私たちを「生の現象学」へと解放する契機になりうるのが、抽象絵画であり、絵画であり、芸術である。アンリは本書で、カンディンスキーの抽象絵画を例にあげ、芸術は「生」の自己感受そのものであると論じる。カンディンスキーは、対象(現出者)から分離させた色や形などの絵画的フォルム(現出)をタブロー上に配置することで、抽象絵画を創出した。つまり抽象絵画とは、「現出から現出者へ」という意識の枠組みを破壊する芸術形態なのだ。そしてその枠組みから逸脱する営みこそが、まさに生の体験そのものである。さらには抽象絵画に限らず、あらゆる絵画、ひいてはあらゆる芸術は、現出そのものに主眼を置くという点において抽象であって、抽象により誘起される情感性の変容は「生」の自己感受に匹敵する、とアンリは考えた。一人の芸術家は、創作を通じて自身の(と同時に普遍的な)情感性を表現する。対して複数の鑑賞者は、表現された情感性を介して万人普遍の起源としての「生」を各々で共時的に実感する。カンディンスキーの絵画的フォルムは、情感性を喚起する諸要素にまで還元されているがゆえに、鑑賞者に生の自己享楽(これは自己受苦と表裏一体ではあるが)を実践させる。おそらくアンリにとって、カンディンスキーの作品は「生」の復活の象徴であったのだろう。
私事ではあるが、評者が医学生として思うのは、医療は患者の情感性を無視してはならないということだ。病気により鋭敏になった情感性を患者と共に育み、目的性や有用性に縛られた「現出から現出者へ」という既定路線からの逸脱の伴走者となることも、医療の役割である、とは言い過ぎだろうか?もし医療の究極的な目標が生の実感の増進だとすれば、アンリの「生の現象学」という視点が医療においても欠かせないことは少なくとも事実であろう。いずれにせよ本書は、たんなる絵画論にとどまらない、「生」に根差したアンリの哲学的思索が展開された幅広く示唆に富む一冊である。(柄)

京大新聞では例年、その年の共テ問題文の出典から数冊をピックアップし、その書評を掲載している。本面をきっかけに出題文を思い出し、受験後にでも読んでみようか、と思ってもらえれば幸いだ。(編集部)
目次
〝観光とは見ることである。それはさながら呪文のようでもある〟 国語 第1問「観光は『見る』ことである/ない」〝触角の取れた虫。方向感覚を破壊された鳥〟 国語 第2問「繭の遊戯」
たくさんの本を読み、物知りになることは、「博学」とは違う 国語 第5問『論語』
〝美的体験はそれ自身が一つの倫理、一つの「実践」、生の実現の一つのあり方となる〟 公共、倫理 第3問『見えないものを見るカンディンスキー論』
〝観光とは見ることである。それはさながら呪文のようでもある〟
国語 第1問「観光は『見る』ことである/ない」
「観光は見ることである」。本文中で「呪文」と称され、繰り返し用いられるこの文言を軸に、観光社会学者・高岡文章氏の論考は展開する。所収本の題『〈みる/みられる〉のメディア論』が示唆する通り、本論は徹頭徹尾「見る」ことと「観光」の関係に焦点を当てつつ、「見ない」「する」「見られる」といった、見る行為の変容にも目を向けていく。
本論はまず「見る」ことを俎上に載せる。見ることが認識における主軸である、とするフーコーの認知論を基盤として、20世紀の終わり、社会学者のアーリは観光もまた見ることに規定されていると述べた(『観光のまなざし』)。この考え方が後世の研究を規定し、観光学と「まなざし」の概念は不可分となった。そして「観光は見ることである」という呪文が生まれた、と筆者は述べる。と同時に、筆者はアーリの研究を更に援用しつつ、観光における「見ない」という行為にも着目する。個人のまなざしは社会的・文化的な制度に規定され、「まなざしには常に選別がともなっている」というのだ。この主張には大いに頷けるものがある。京都でも、花見小路通を歩く観光客は花街や芸者の華やかさばかりに視線を注ぎ、時に彼女たちが直面してきた悲惨な状況からは目を背けるのだから。
続いて論考は、「見る」と「する」への対比へと進む。筆者は「見る」観光の受動的・疎外的な一面を指摘しつつ、その反動として生まれた「する」観光について言及する。農山漁村での生活体験、地元住民のガイドによる街歩きなど、能動的な「体験」や「交流」を核とする新しい観光を例示し、アーリの観光論を乗り越えようとする新たな研究にも触れる。呪文によって見ることに縛られていた観光は、「する」という新たな視座を得ていく。
終盤では「見る」主体と客体の入れ替わりや、視線を注ぐ対象の変容が議論される。かつての観光は観光客が生活者を見ていたのに対し、今では生活者も観光客を見ているという「相互のまなざし」論が、オーバーツーリズムに憤る生活者の例を介して紹介される。デジタルネイティブ世代としてとりわけ興味深いのは、ネット時代における「見る対象」の変化を取り上げた部分だ。かつて観光客は自己の外にある「世界」を見ていたのに対し、今や行く先々で自撮り写真の撮影者/投稿者となり、写真の中の世界ではなく、そこに映る「自分自身」を注視している。人々は世界を「撮り」「シェアする」ことに没頭している、という鋭い指摘や、「この世界がもはや『映え』の残り滓でしかないのかもしれない」という一節は、評者を含め多くの現代人にとって耳の痛い忠告ではないだろうか。
試験問題では中盤部分が引用された。アーリを初め多数の論者の研究が引用されており、読み進めるのに難儀した受験生も多かったことだろう。とはいえ、全12ページとは思えないほど内容は充実し、旅好きにもそうでない人にも示唆に富む論考となっている。受験が終わったら、仲間と共に旅行に出かける人もいるかもしれない。その前に一読し、自らの「観光」に対する観念を見つめ直してみてはいかがだろうか。(晴)

◆書誌情報
『〈みる/みられる〉のメディア論』
高馬京子・松本健太郎編
ナカニシヤ出版
2021年
『〈みる/みられる〉のメディア論』
高馬京子・松本健太郎編
ナカニシヤ出版
2021年
目次へ戻る
〝触角の取れた虫。方向感覚を破壊された鳥〟
国語 第2問「繭の遊戯」
本作は、短編よりも短い「掌編」小説で、本文は10ページほどしかない。しかし、5歳ほどの「わたし」と働かずに小屋に籠るおじさんとのやり取りを通じて描かれる彼らの心模様や、詩人である著者によって散りばめられた比喩表現は掌には収まりきりそうにないほどだ。
一読すれば「繭」というのが、おじさんの暮らす小屋の比喩であることは容易に理解できる。では、「遊戯」とは何を示しているのだろうか。おじさんの振る舞い、「わたし」の葛藤、ふたりの交流、あるいはその全てだろうか。いずれにせよ「遊戯」とは「仕事」の対局にあるものだ。おじさんは「大人」だが、仕事をしてお金を稼いでいない、いわゆる「ニート」のような状態で、そのことで母をはじめ家族中から疎まれているのだった。
そんなおじさんは小屋でギターを弾いたり、絵を描いたりしていた。どれも技術的に優れているというわけではないが、一つ一つにこだわりや思い入れがあるようで、それが彼を魅力的に映す。そして、部屋に「インドの匂い」を漂わせシードルの瓶の口を舐める様は、世間の価値観に迎合せず、自由を謳歌する生き方をも思わせる。
おじさんはある日、オカリナを「わたし」に見せ、「売るんだ」と得意げに告げる。正しく音階を奏でることはできないようだが、独自の運指法を書いた紙まで用意していた。彼もお金を稼ごうと思っていたのだ。実は周囲の目が気になっていたのか、ただ生活費が必要になったのか。ここで、彼も彼なりに葛藤していたのではないかということ、また、誰もがお金を稼ぐ必要性からは逃れられないということを突き付けられる。そして、彼の生活は「自由な生き方」などと賛美できるものではなく、所詮は「遊戯」に過ぎないのではないかという考えが頭に浮かぶ。そもそもオカリナを売るといっても大した金額にはならないだろうし、お金を稼ぐ手段としては不十分だろう。そんな他人には価値のないように見えることに熱心に取り組む、「触角の取れた虫」「方向感覚を破壊された鳥」のようなおじさんは、一体どこへ向かうのか。行く先は最後まで示されていない。
実際におじさんのような人物が身内にいたら、母のような反応になるのも当然だろう。中には、読んでいるだけで、その無責任さに苛立ちを覚える人もいるかもしれない。そして、「働いてお金を稼ぐ」ことが正しい大人の姿であるという価値観をつい自明視しがちだ。私自身はというと、就活の影もちらつく中で、自然とその道を歩み始めていた。物語はその考えを、取り立てて否定するわけではない。ただ、少しの間立ち止まってその行き先を見つめ直す機会を与えてくれる、そんな掌編だ。(省)
◆書誌情報
『極上掌篇小説』
(著)片岡 義男、車谷 長吉、橋本 治、矢作 俊彦、又吉 栄喜、高橋 源一郎、佐伯 一麦、大崎 善生、三田 誠広、勝目 梓、石田 衣良、高橋 三千綱、佐野 洋、小池 昌代、堀江 敏幸、大岡 玲、吉田 篤弘、重松 清、玄侑 宗久、蜂飼 耳、高橋 克彦、平野 啓一郎、嶽本 野ばら、筒井 康隆、星野 智幸、いしい しんじ、伊集院 静、歌野 晶午、西村 賢太、古川 日出男
KADOKAWA 2006年※販売は終了しています。
『極上掌篇小説』
(著)片岡 義男、車谷 長吉、橋本 治、矢作 俊彦、又吉 栄喜、高橋 源一郎、佐伯 一麦、大崎 善生、三田 誠広、勝目 梓、石田 衣良、高橋 三千綱、佐野 洋、小池 昌代、堀江 敏幸、大岡 玲、吉田 篤弘、重松 清、玄侑 宗久、蜂飼 耳、高橋 克彦、平野 啓一郎、嶽本 野ばら、筒井 康隆、星野 智幸、いしい しんじ、伊集院 静、歌野 晶午、西村 賢太、古川 日出男
KADOKAWA 2006年※販売は終了しています。
目次へ戻る
たくさんの本を読み、物知りになることは、「博学」とは違う
国語 第5問『論語』
漢文を題材とした大問5では、3つの文章が出題された。1つ目の『論語』は、言わずと知れた古代中国の大思想家・孔子の言行録である。2つ目は、18世紀から19世紀初めに活躍した江戸時代の儒学者・皆川淇園の論語注釈書、3つ目は、淇園の弟子である田中履堂のいわば読書論である。時間にすれば、2200年以上の歳月を経た共演である。
今年の漢文では、「博識な人」をめぐる議論が扱われた。孔子は弟子の子貢に問う。「君は私がたくさん学び、多くの知識を覚えていると思うか」。もちろん子貢はハイと答える。しかし、これに対して孔子は、「違う、私は一つのことを貫いている」と答えた。ここに込められたメッセージについて、淇園はこう解釈する。「学問の方法とは、いたずらに多くを求めて雑多にしてはいけない、それではむしろ愚かになってしまう。何か道を見つけて、これを主として進むべきだ(学問之法、不可貪多務博、龐雑冗乱、反闇其智)」。また弟子の履堂も、「万巻の本に大雑把に目を通すよりも、一冊の本を深く理解したほうがよい(粗涉万卷、不如精通一卷)」とする淇園の言葉を引用しつつ、多くの本を読んでいる人は、物知りとは言えても、「博」学とは言えないと述べる。
世間はたくさんの本を読んで多く覚えている人を「博識な人」と言い、羨むかもしれない。しかし履堂の言葉を借りながらまとめると、「博」とは、何かに精通しているという意味であって、単なる物知りとは違う。一冊の書物に精通していれば、これもまた博学というべきである。(なるほど、特定の分野の専門家である博士には、「博」の字がついている。)
おそらく情報過多になりがちな現代の、「ファスト文化」に対する出題者らの問題提起であろう。アニメにせよ、ドラマにせよ、映画にせよ、早送りにしたり、切り抜きだけで楽しんだりする風潮がある。この方が、零細な隙間時間でも見られるし、周りの人の話についていくためには効率がいい。また、ビジネスシーンでうまく立ち回るために、手早く「教養」と呼ばれるようなものをおおざっぱに仕入れていく「ファスト教養」も流行っている。言うなれば、情報の破片が飛び散っている状況で、人々はそれらを集めて、「効率よく」かき揚げみたいに言葉を生産している。(なおこのような情報収集は生成AIの最も得意とするところである。)出題者は、現代社会に生きる受験生に対して、雑多な情報を集めるのに終始するのではなく、大学で腰を据えて学問に励んでほしいという思いを、古の聖賢たちに代弁させたのかもしれない。
大学生も胸に手を当てるべきだ。日々バイトやサークルに追われ、「忙しい」をステータスのように振りかざしながら、テストの直前では教科書の原文に当たらず、レジュメを切り貼りしたような答案やレポートを書いてしまった経験はあるだろう。一方で、「日々書を読んでいる自分とは関係ない」という人もいるだろう。自由な学風に甘やかされて、好奇心の赴くままに本を読んでいるといえば聞こえはいいものの、「専門性」と問われると困ってしまう人も中にはいるに違いない。これは別のレイヤーの問題ではあるが、評者もまたその一人である。最初にこの文章を読んだ時は、頭をガーンと殴られた気持ちだった。
反論したいがぐうの音も出ないのが古典というものかもしれない。バイトやサークルに勤しんでいる人も、勉強らしきことをしている人にも等しくクリティカルヒットを与える。だからと言って、それが全部正しいとも思わない。時代背景が違うし、ユークリッドは「学問に王道はない」と言っている。これ以上の学問論は学部3年生の手に負える話題ではないが、現代に生きる我々も古典を紐解いて、自分の学びを点検してみるのは面白いかもしれない。(唐)

◆書誌情報
『論語』
金谷治 訳注
岩波文庫
1999年
『論語』
金谷治 訳注
岩波文庫
1999年
目次へ戻る
〝美的体験はそれ自身が一つの倫理、一つの「実践」、生の実現の一つのあり方となる〟
公共、倫理 第3問『見えないものを見るカンディンスキー論』
本書は、画家カンディンスキーの抽象絵画を題材に、哲学者ミシェル・アンリが自身の「生の現象学」を深化させた思想書である。フランスで哲学を学び、同じく20世紀の哲学者であるフッサールやハイデガーに影響を受けたアンリは、既存の現象学(哲学の一分野)では人間の「生」を十分に捉えきれないと考え、独自の「生の現象学」を打ち立てた。芸術にも深い造詣を持つ彼は、「生の現象学」の視座から絵画を眺め、「芸術とは尽きることのない生の復活」であると結論づけた。
この結論だけ聞くと凡庸に思えるかもしれないが、その思考過程は「生」に対して誠実であり納得のいくところも多い。アンリはまず、現象学の伝統的な枠組みを批判する。フッサール現象学では知覚的な経験により私たちの「生」は形づくられると見做すが、そのアプローチでは日常を過ごす中で感じる「生」の生々しさを掬い取れない。「生」の実感は、知覚対象に定まる前のプリミティブな自己を、隔たりなしに感受することで得られる。ここでの隔たりとは時間的な距離を意味する。フッサールの「把持―原印象―予持」(『内的時間意識の現象学』)において、意識とは時間であった。時間的な隔たりがひととものの間に設けられた結果、対象や客観が現れる(見える)ならば、この隔たりをゼロへと極限するとき、主観性はその内側から自己を触発として感じるだろう。そうして己を内的に知ることを、感情、と言い換えると、感情こそが主観性の自己を成り立たせていると考えられる。アンリによれば、知覚と感情の共存・共生(情感性)によって初めて、「生」がアクチュアルに体感されるのである。
フッサール現象学によると、意識は、感覚による体験としての現れ(現出)から、ある志向に基づいて(志向性)、知覚による経験としての現れ(現出者)へと向かうとされる。例えば、平面上に立体的に描かれた机と思しきイラストを見るとき、目に映る通りの平行四辺形(現出)は、それは机であり机の形は通常平行四辺形ではなく長方形であるという意味づけに照らし合わせること(志向性)により、長方形(現出者)として即座に知覚される。しかしこのような意識のプロセスでは、志向性において少なからず目的的で緊密な連関が生じ、それは実用性や合理性と結びつきかねない。そうなると「現出から現出者へ」という意識の流れは、遊びのない、息苦しいものとなって、本来的な「生」の実感を隠蔽してしまうだろう。実際に私たち現代人の多くが、志向性に囚われているために情感性が機能せず、「生」の充足感を得られない日々を送っている、とアンリは指摘する。
そのような私たちを「生の現象学」へと解放する契機になりうるのが、抽象絵画であり、絵画であり、芸術である。アンリは本書で、カンディンスキーの抽象絵画を例にあげ、芸術は「生」の自己感受そのものであると論じる。カンディンスキーは、対象(現出者)から分離させた色や形などの絵画的フォルム(現出)をタブロー上に配置することで、抽象絵画を創出した。つまり抽象絵画とは、「現出から現出者へ」という意識の枠組みを破壊する芸術形態なのだ。そしてその枠組みから逸脱する営みこそが、まさに生の体験そのものである。さらには抽象絵画に限らず、あらゆる絵画、ひいてはあらゆる芸術は、現出そのものに主眼を置くという点において抽象であって、抽象により誘起される情感性の変容は「生」の自己感受に匹敵する、とアンリは考えた。一人の芸術家は、創作を通じて自身の(と同時に普遍的な)情感性を表現する。対して複数の鑑賞者は、表現された情感性を介して万人普遍の起源としての「生」を各々で共時的に実感する。カンディンスキーの絵画的フォルムは、情感性を喚起する諸要素にまで還元されているがゆえに、鑑賞者に生の自己享楽(これは自己受苦と表裏一体ではあるが)を実践させる。おそらくアンリにとって、カンディンスキーの作品は「生」の復活の象徴であったのだろう。
私事ではあるが、評者が医学生として思うのは、医療は患者の情感性を無視してはならないということだ。病気により鋭敏になった情感性を患者と共に育み、目的性や有用性に縛られた「現出から現出者へ」という既定路線からの逸脱の伴走者となることも、医療の役割である、とは言い過ぎだろうか?もし医療の究極的な目標が生の実感の増進だとすれば、アンリの「生の現象学」という視点が医療においても欠かせないことは少なくとも事実であろう。いずれにせよ本書は、たんなる絵画論にとどまらない、「生」に根差したアンリの哲学的思索が展開された幅広く示唆に富む一冊である。(柄)

◆書誌情報
『見えないものを見るカンディンスキー論』
ミシェル・アンリ著
青木研二訳
叢書・ウニベルシタス法政大学出版局、
2016年
『見えないものを見るカンディンスキー論』
ミシェル・アンリ著
青木研二訳
叢書・ウニベルシタス法政大学出版局、
2016年