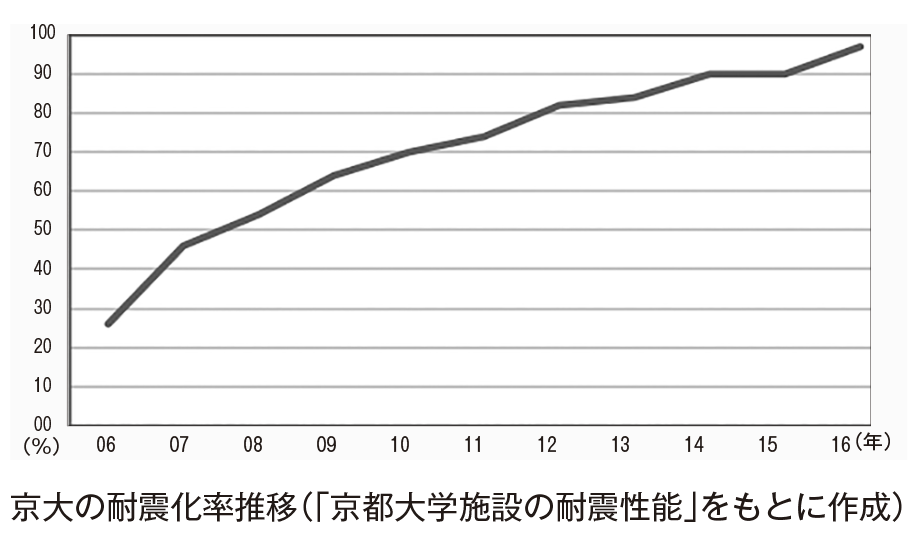【連載第十三回】吉田寮百年物語(最終回)
2022.09.16
《連載にあたって》
京大が吉田寮現棟の明け渡しを求めて寮生を提訴した問題で、8月10日に第14回口頭弁論が開かれた。19年4月から訴訟が続くなか、本紙では同年7月16日号より「吉田寮百年物語」を連載している。吉田寮の歴史を振り返り、今後のあり方を考える視点を共有することを目的とし、連載にあたり吉田寮百年物語編集委員会(※)を立ち上げた。前回第十二回では、それまで約10年ずつに区切って載せていた通史をおさらいする総集編のほか、自治寮での生活や団体交渉に関する寄稿を掲載した。今回が最終回となる。これまでの連載に収まりきらなかった論考を3本掲載し、他大学の寮の状況や、吉田寮における性をめぐる議論の歴史を振り返る。なお、連載の内容を網羅した書籍の出版を予定している。
※「21世紀の京都大学吉田寮を考える実行委員会」や「21世紀に吉田寮を活かす元寮生の会理事会」の会員と趣旨に賛同する個人からなる。京都大学新聞社が編集に協力している。
※これまでの連載↓
第一回 第二回 第三回 第四回 第五回 第六回 第七回 第八回 第九回 第十回 第十一回 第十二回
目次
《コラム1》近年の「教育寮」「国際学生寮」と吉田寮《コラム2》入寮枠の性別要件をめぐる歴史
《コラム3》新棟建設とオールジェンダートイレ
《コラム1》近年の「教育寮」「国際学生寮」と吉田寮
【寄稿】冨岡勝(近畿大学教職教育部教授)
学生寮に関する全国調査
独立行政法人日本学生支援機構が2019年に全国の大学・短大・高等専門学校を対象に実施した学生支援に関するアンケート調査(以下、「学生支援調査」と略)には、4年制大学782校(国立86校、公立92校、私立604校)の学生寮についての調査も含まれている。その主な結果を同機構のウェブサイトで公開されている報告書から紹介し、近年の学生寮の動向を知る手がかりにしたい。
8.7%の大学が2018年度から19年度末までに学生寮を新設置・増設したと回答している。新設置・増設した大学がその理由(複数回答可)として主に挙げているものは、「外国人留学生の確保」(63.6%)、「快適な生活環境の提供」(52.9%)、「遠方からの学生の確保」(50.0%)、「日本人学生と外国人留学生との共同生活による異文化理解・外国語能力の向上」(50.0%)、「学生の経済的問題への配慮」(44.1%)、「コミュニケーション能力の向上」(42.6%)、「共同生活を通じた規律意識の醸成」(39.7%)である。
学生寮の運営形態についての設問(複数回答可)では、「学校による直接運営」と回答した大学が65.2%(国立大学の回答では73.5%)、「運営を外部に委託」が44.1%(国立大学では36.1%)、「学生による自治」が19.8%(国立大学では47.0%)、「その他」が5.7%(国立大学では3.6%)となっている(図1を参照)。
学生寮入居学生の形態についての設問(複数回答可)では、「日本人学生のみ」が39.5%(国立大学では33.7%)、「外国人留学生のみ」が19.3%(国立大学では36.1%)、「日本人学生と外国人留学生(混住型)が71.4%(国立大学では96.4%)となっている。
いずれも興味深い結果である。大きな傾向としては、近年の大学では日本人学生と留学生との共同生活を重視していることなどが特徴となっていることがわかる。
なお、学生の経済面への配慮も学寮の新設置・増設の理由として挙げられている。ただし、2004年の国立大学法人化以降、各大学の裁量で学寮の寄宿料を設定できるようになったことをきっかけに、寄宿料の大幅値上げも見られることに注意が必要であろう(注1)。
「教育寮」「国際学生寮」とRAへの注目
この「学生支援調査」では、先進事例と位置づけられた学寮に対する実地調査も行われている。例えば立命館アジア太平洋大学(2000年開学)の国際教育寮「APハウス」と一橋大学の国際学生宿舎小平一橋寮が2019年度「学生支援調査」の調査報告で紹介されている。この2例の特徴は、留学生と日本人学生の混住寮であることと、RA(レジデントアシスタント、以下RAと略)が運営の中心を担う「教育寮」であることである。
RAというのは大学に雇われた(あるいはボランティアの)学生スタッフのことであり、アメリカの大学を中心に作られた制度である。アメリカの学生支援論の影響を受け、近年は日本の大学でも導入され始めている。アメリカの学寮史を研究している橋場論によれば、アメリカでは1960年代までは寮母の代わりに学生を監督するのがRAの主役割であったが、1970年代以降、心理学にもとづいた学生発達理論が学生支援を先導するようになると、RAの役割として「学寮の運営」「カウンセリングの実施」「プログラムの企画」なども重視されるようになってきたという(注2)。
立命館アジア太平洋大学の国際教育寮「APハウス」は、定員1310名で1年次の国際学生全員と希望する国内学生が入寮し、国際学生と国内学生の割合は47・4%と52・6%(2019年5月現在)で、大学とRAが連携して運営しているという。各フロアに1~2名、合計64名が配置されるRAは、寮生のサポート、RA会議、フロアミーティング、シフト制でのキッチン清掃、フロアイベント、寮祭などを実施する。任期は1年間(更新可)でエッセイ、グループワーク、グループ面接といった審査を経て大学に採用され、10日間前後の研修を受けている。なお、RAは毎月の寮費(住居費など)4万9千円が免除されている。
一橋大学の国際学生宿舎小平一橋寮(2002年完成)には、一橋大学の学生(日本人学生と留学生)と近隣の東京学芸大学・東京農工大学・電気通信大学の留学生が暮らす。単身743室、夫婦室20室、家族室22室のうち、480室に留学生が居住している。寮運営の基盤として、学生組織「ISDAK」(International Student Dormitory Association of Kodaira)が設置され、寮生のサポートや寮運営全般のサポートを担当する学生スタッフとして任期1年間(更新可)のRA34名(2019年12月現在)が、書類選考と面接を経て大学に採用され、年2回の研修がおこなわれている。原則としてフロアごとにRAまたはCA(コミュニティアシスタント)が1名配置され、寮生とコミュニケーションをとりながら、チューターとしての役割も果たしているという。RAは会計、環境整備、寮内交流イベント開催なども担当している。RAは寄宿料月額2万4千円が免除されている。
学寮の歴史と「教育寮」「国際学生寮」
つまり近年注目されつつある「国際学生寮」は、留学生と国内学生がともに暮らす場であるとともに、RAが中心となって寮生の交流活動などを一種の教育プログラムとして進める「教育寮」であることが特徴であるといえるのかもしれない。全国の大学で今後新設される学生寮のモデルは、「国際学生寮」「教育寮」とRAとなっていく可能性がある(注3)。
たしかに、千人前後が暮らす大規模な学寮が新たにつくられるような場合は、寮生の自治活動の伝統がない状態なので、多人数の寮生が生活する上で生じる様々な問題の解決をいきなり学生だけに任せることは、大学としてためらうかもしれない。同時に、寮生活で生じる様々な問題を大学の教職員が一つ一つ解決していくことも容易ではないだろう。また、学寮を「教育寮」にしようとして教職員だけが行事などを用意しても、できることは少ないだろう。そこで新設の大規模寮などの場合、寮生と密接にコミュニケーションをとりながら学寮内の生活上の諸問題を解決し、交流プログラムや教育プログラムを主導していくRAが活躍するかもしれない、ということは理解できる。
しかし、日本の大学では近年登場したばかりのRA制度は、問題点のない完璧な方法なのだろうか。これについてはいくつかの疑問が湧き出てくる。例えば、「RA本人は様々な活動を経験して人間的に大きく成長をするかもしれないが、他の寮生たちは、大学やRAが準備したプログラムに参加するだけで大きく成長するのだろうか」、「RA以外の寮生たちは、自分たちで寮生活をつくっていくのではなく、サービスの受け手としての姿勢が強くなってしまうのではないか」、「寮内で起こる問題を話し合いで解決していくためには少数意見を尊重したり、互いの意見を丁寧に聴き合うことが重要だと考えられるが、学生に過ぎないRAが上から指導するだけでそうしたことは実現できるのだろうか」などの疑問をすぐに思いつくことができる。RAを導入した大学では、RA研修に力を入れたり、業者にRAと大学とをつなぐ役割を持たせたり、複数の大学間での学寮職員やRAの経験交流会を開催したりといった試みも行われているが、試行錯誤はしばらく終わらないのではないだろうか。
ここで大学の寮の歴史を簡単に振り返ってみよう。戦前期は第一高等学校などの旧制高等学校で寄宿舎は、単に遠方からの学生の生活の便宜を図る存在としてだけでなく、自治的・自律的な共同生活を通じて人間的な成長を目指していく教育的施設として次第に意識されるようになっていった。また、連載第1回で紹介されたように京都帝国大学の寄宿舎は、日露戦後の時期から「自重自敬」を目指した教育を実践する重要な機関として位置づけられるようになっていった。
戦後は経済状態の混乱のなかで、大学の学寮は学生生活を支える厚生施設としての役割が切実に求められるようになったが、多くの学寮で寮生たちは、戦前期同様、寮生活に関わることに自治的に取り組んでいた。また、1962年に文部省の学徒厚生審議会から出された答申「大学における学寮の管理運営の改善とその整備目標について」では、学生の経済生活を支える役割とともに、人間形成に対する学寮の役割が意識されていた。
1971年の中央教育審議会答申「今後における学校教育の総合的な拡充整備のための基本的施策について」は、1962年の学徒厚生審議会答申の趣旨を基本的には引き継ぎ、学寮は「豊かな学生生活を保障し、学生の人間形成を助長する」役割を持つのでこれを改善充実していくことは重要であるとしながら、1960年代末を中心に学寮の管理方針をめぐって大学と学生が激しく対立する状況があったことなどを指摘し、「これまで学寮が果たしてきた機能を分解して、それに代わる方策をとることも必要であろう」と述べた。
この1971年の中教審答申を承け、1970年代後半からの国立大学でつくられた学生寮のほとんどは、「新規格寮」あるいは「新々寮」と呼ばれる完全個室・食堂無し・集会室無しの、共同性を極端に削減して管理効率だけを追求した学寮であった。1970年代末ごろから、老朽化などを名目に旧寮(1950年代までに建設された寮)や新寮(1960年代から1970年代半ばまでにつくられた寮)を廃止する動きと、「新々寮」をつくる動きが岡山大学や大阪大学など全国的に見られるようになった。1980年代の吉田寮第一次在寮期限の設定や、1990年代から2000年代始めにかけての山形大学学寮や東京大学駒場寮の廃寮をめぐる一連の経過も、そうした流れの一環としてとらえられるだろう。
ところが21世紀に入るころから、留学生数の拡充政策や1970年代からのアメリカの大学教育における学習者中心主義の登場(注4)などの影響を受けて、「国際学生寮」や「教育寮」を作る動きが見られるようになってきた。共同生活の慣行や自治的な運営の蓄積をもった「旧寮」「新寮」が大幅に減らされた後で、「新々寮」には不足していた共同生活による教育的役割を重視した寮として、「国際学生寮」や「教育寮」が新たに注目されつつあるといえるだろう。
吉田寮の経験がヒントに
筆者は「国際学生寮」や「教育寮」を支えるRA制度については、学寮の歴史のなかでのさまざまな取り組みの一つとして興味深く感じる。と同時に、RA制度のような新しい試みを充実させるためには、アメリカ大学教育の事例だけでなく、日本国内のさまざまな「旧寮」や「新寮」で積み重ねられてきた経験が役立つのではないかと考えている。
例えば、「RAと寮生との関係をどのようにしてより良くしていけるか」というような課題を考えるとしたら、様々な「旧寮」や「新寮」で寮自治組織の委員をどうやって選んできたのか、どうやって後継の委員を育ててきたのか、どうやって寮生は話し合いをできる素地を作っていったのか、どうやって委員とその他の寮生が話し合いを充実させてきたのかなどに関する「旧寮」や「新寮」の経験がヒントになるのではないだろうか。したがって、大規模な寄宿舎を新設してRA制度を導入するような場合には、「旧寮」や「新寮」を含む学内外の多様な学寮との交流が有効だと考える。
しかし、今年(2022年)になってからも「新寮」である金沢大学の泉学寮(せんがくりょう)・白梅寮(はくばいりょう)、静岡大学の雄萌寮(ゆうほうりょう)の廃寮決定についての報道があったように、全国の「旧寮」や「新寮」は老朽化などの理由で減少傾向にあるのが残念である。寮生活の自治は、長い期間の試行錯誤の積み重ねによって形成されてくることが多いため、廃寮によっていったん経験が途絶えてしまうと、断絶をカバーするのは容易ではないからである。
「旧寮」である吉田寮は1913年築の現棟と食堂(食堂は2015年に全面補修)が現在も寮として活用され続けられながら、寮生活に関するさまざまな経験が日々蓄積されている。また、連載第7回で紹介されたように、吉田寮では30年以上にわたって留学生も寮生として受け入れ、生活ぐるみでの異文化交流の経験を重ねている。
新しいタイプの「国際学生寮」や「教育寮」を含む様々な学寮が改善にむけて試行錯誤を続けていく上でも、古い歴史をもつ吉田寮が貴重な建築物とともに21世紀、22世紀……と存続し、寮生自身の手で寮生活がバージョンアップされ続けていくことの意味は大きいのではないだろうか。
注1 2003年までは、国立大学の学寮の寄宿料は授業料と同様に文部科学省令で定められ、建築年などによって400円(旧寮)、700円(新寮)、4300円(新々寮)などの月額が設定されていた。しかし近年は、一橋大学国際学生宿舎小平一橋寮の月額2万4千円のような例も見られる(2018年の値上げ前は5900円)。2019年の日本学生支援機構学生寮調査でも、寄宿料月額5千円未満の学寮を有する大学が55.4%、月額5千円以上1万円未満の学寮を有する大学が62.7%であるが、同時に、寄宿料月額2万円以上3万円未満の学寮を有する大学が33.7%、月額3万円以上4万円未満の学寮を有する大学が19.3%、月額4万円以上5万円未満の学寮を有する大学が12.0%となっている(図2を参照)。近年新設あるいは建て替えられた学寮では高額の寄宿料が設定されるケースがあるのではないかと推測される。2019年に建て替えられた京都大学女子寮の寄宿料も月額2万5千円(2022年現在)に設定されている(建て替え前は400円)。しかし、厳しい経済状況の中で親元からの仕送りなしに自活する学生も存在していることを考えると、たとえ新築だからといっても寄宿料が従来の5倍以上に設定されているのでは、学生の経済面への十分な配慮がなされているといえるかどうか疑問である。
注2 橋場論「米国における学寮と学寮プログラムの歴史的展開」、安部有紀子・望月由起・橋場論 編『学寮プログラムの現代的展開』高等教育研究叢書145、広島大学高等教育研究開発センター、2019年3月、所収。
注3 RAは、京都大学でも注目され始めている。2019年10月より、京都大学の外国人研究者と留学生の宿泊施設である国際交流会館でRA制度が開始されている。設置の理由について京都大学は、「会館でのより良い生活環境を作るとともに、日本人学生との国際交流の機会も期待できるため」と説明している(「国際交流会館 日本人学生も入居へ 留学生の生活を支援」、京都大学新聞2019年11月16日)。ただし、学生の自治的経験の蓄積を考慮すれば、〝既存の自治寮を無くしてRA制度の「教育寮」「混住寮」に置き換えればよい〟とはいえないのではないだろうか。
注4 くわしくは前掲『学寮プログラムの現代的展開』所収の安部有紀子「米国学寮プログラムにおける学習者中心主義の影響について」を参照。
目次へ戻る
《コラム2》入寮枠の性別要件をめぐる歴史
誰が入寮する資格を持つか
吉田寮は開設の当初から京大の「日本人の男子学部生」のみを入寮資格としてきた。しかし、1970年代以降、そうしたあり方の見直しがなされた結果として、現在では入寮資格は「京都大学の学籍を有する者及びその者との切実な同居の必要性のある者」となっている。学生と切実な同居の必要性のある者の入寮に関しては、第7回連載で「《記録》家族で入寮するまでの経緯―セーフティネットとしての機能―」という記事を掲載した。
今回の記事では、性別の要件が撤廃されていった歴史を、寮内に蓄積されている資料(これらのアーカイブについては第11回コラム「『資料室』とファイリングの始まり」を参照)から繙き、誰が吉田寮に入ることができるかという場のあり方にとって根本的な問題に、寮生がどう向き合い、どのような議論がなされてきたのかを明らかにしたい。あらかじめ要点を先取りすれば、本連載の通史第7回で示された「1985年から学部の男女学生に入寮資格枠を広げた」という記述は、「吉田寮小史」などの配布物、寮内資料でいわば通説となってきたものであるが、不正確である。実際には、1972年ストーム事件をきっかけに女性差別の向き合い方を問われた吉田寮は、1974年度から女子入寮を開始し、現に入寮者が存在したものの、その事実は1980年代以降、継承されなかったのであった。そうした入寮資格という制度面だけなく、実際の生活も含めて場のあり方における女性差別を見直す動きが寮内で重ねられてきたことが資料からうかがえることも重要である。単に機会平等で事足れりとするのではなく、実質平等を実現することを目指した寮生たちの取り組みを、刻み込んでおきたい。(小)
寮のあり方が問われたストーム事件
1985年に男子のみという制限が解かれたという歴史が不正確であると述べた。その証左としてまず、「74年新入寮生発表自主選考権を維持女性も選考対象に」という京都大学新聞第1685号(吉田寮・熊野寮自治会の署名記事、1974年11月18日)の記事が挙げられる。この記事では、社会一般の選考が実質的な「選別」であるのに対し、寮自治会の入退寮選考権の行使においては「寮の性格上、経済状態を軸にしながらも、入寮希望者の特殊事情を十分考慮し、我々と入寮希望者との要求を相互に出し合い、その間のギャップを討論で、又寮生活を通して克服していく方向で自主選考の内実を検討してきた」と述べる。そして、「女性から提起のあった女性入寮の問題については、充分な討論の結果女性を選考対象に組み入れることを決定した」と明らかにしている。そして、実際に入寮者がいたことが寮内新聞「文化部機関誌」第3号(吉田寮文化部、1975年3月6日)の記事から分かる。ここでは「二名の女性が正式入寮している」状況のなかで、女性が入寮するに至る具体的な契機として1972年のストーム問題が挙げられている。ストームとは、寮内の居室や、時に近隣の女子寮に寮生が集団で押しかけて騒ぐイベントで、旧制高校以来の風習となっていた。吉田寮でも長らく続いてきたストームが問題となったのは、1972年3月8日に開かれた卒寮コンパ後の深夜に、当時の吉田西寮の近所にあった看護学校の女子寮・瑞穂寮へのストームを行った際、参加した寮生が部落解放運動のビラを剥がしたり、女性差別的言辞を弄したりするなどした行動が、部落解放運動への敵対や女性差別として糾弾される事件が起こったためである。この事件をきっかけとして、執行部を中心に吉田寮内で「女性差別とどう闘うのか」が問われたのであった。
この事件の寮内での総括は、1971年度後期の「活動総括」や「議案書」において表明されている。議案書内の執行委員会による「特別アピール」では、「ストームは、いかなる意味付与を持ってなされようとも、その背景としての学生特有の「社会に対する甘え」と京大生特有の「思い上がり」=エリート意識、そして、女性差別意識、男中心主義の産物そのものであり、それを許容し、再生産(襲撃を受けた女性への犠牲の上に成立する)行為であることを我々は確認しなければならない」(原文ママ)と述べられ、その議案書が提起された1972年4月の寮生大会でストームの撤廃が決議された。同時に「単に〈ストーム〉を止めれば問題が片付くということでは決してない。問われたものは、〈ストーム〉を許容あるいは行なった我々そのものなのである」として、問題意識をさらに深めていくことが確認された。1972年度前期「活動総括」によれば、「4月には、さかんに学習会、討論会等が持たれ、ある程度寮生内部にも問題の所在が明らかにされた」ものの、同時に「直接自分自身の存立にふれる重要な問題として取られ得ないがゆえに忘れられようとしている」という危機感が表明されている。その過程の中で、寮祭やコンパが中止され、見直しの議論がなされるものの、ストーム事件で問われたことの共有・継承が進まず、議論が活発化しないまま中止の状態が継続した。ストーム事件の当時に執行委員長であった髙橋龍太郎氏は、責任者として矢面に立たされたその時期を振り返り、「自分は加わっていないけれども寮の責任者の立場である以上他にやり様はない、と糾弾を受けました。吉田寮食堂で開かれた糾弾集会では、糾弾に立ち上がった看護学生が最初に短く私たちに抗議をし、そのあとは代わりに男性の活動家が〈女性差別〉や〈部落差別〉を追及するという展開となりました。数回の糾弾集会が開かれたのち連絡も途絶え立ち消えました。当時は、目前に迫った沖縄返還をめぐってさまざまな政治潮流が生死を賭けてぶつかり合う状況で、きっかけとなったストーム事件について私たちの中での組織だった議論は深まりませんでした」と述べている(2021年8月26日、吉田寮現棟・食堂明渡請求訴訟第8回口頭弁論裁判報告集会におけるスピーチ)。
入寮資格枠の見直し
上述したようにストーム事件をきっかけに、女性差別を問われた吉田寮は、入寮資格枠を見直し、1974年度の入寮募集から、募集対象が「男女学部学生」となった。1970年代後半から83年まで吉田寮と熊野寮が共同名義で出していた入寮募集案内のチラシでは「吉田寮・熊野寮は女子寮生も募集しています」との小見出しで「京大学内でおこった女性差別事件を契機に、女性差別を温存させるような寮の存在が問題となり、寮内討論の末、女子入寮がかちとられています。男女が共同生活を行うことを通して、男女を分断・利用させている現状と内なる差別意識を問題視することから女性差別の撤廃の道があるのではないかと考えています」などと書かれていた。しかし、資料で分かる範囲では、1977年には吉田寮の女性在寮者は途絶えたようである。その後、吉田寮は実質的な男子寮に回帰し、女子学生が入寮を希望しても熊野寮へ入るよう説得され、入寮が事実上断られた事例もあったという。
その後、大学当局によって設定された在寮期限が1986年3月末に迫る中で、1985年春期から女性入寮が「開始」された。「吉田寮新聞」第9号(1984年12月1日)には「次期選考で女子寮生を獲得せよ」というタイトルの記事があり、「女子学生の入寮を実質的に拒否すること」は経済的な差別であると述べられている。1984年後期の「吉田寮自治会 総括」には「女子入寮についての総括」と題された文章があり、吉田寮が「受け入れ体制が整っていないので責任が持てない」などといった理由で「事実上入寮拒否の方向をとってきた」ことの「欺瞞性は明らか」であると自己批判をしている。ここで、女子入寮について「再開」という言葉が使われなかったのは、寮生の入れ替わりによって歴史が継承されなかったと見るのが妥当だろう。
なお、ストームと合わせて寮祭は、その問題の解決が不十分という理由から、1972年から中止されていた。寮祭における高揚感は、ストームの高揚感と根っこが同じであり、寮祭を様々な「解放運動」の中で再定義しない限り開催しないことになった。1980年4月、9年ぶりに吉田寮祭が復活した。「祭り」の再定義はされなかったが、希薄になった「仲間意識」の恢復や寮の存在のアピールを求めて、寮生の素朴な欲求という名目で開催が決まった。ここにも経験や問題意識の断絶が見てとれる。
寮空間のあり方の問い直し
福利厚生施設としての公共性から、差別に基づく排除を行わないことを吉田寮は重要と考えてきた。とりわけ、「男子寮」として始まり、入寮資格枠が見直された後も、京大がそうであるように男性中心的な空間であり続ける吉田寮においては、そのことについての問い直しが少なからず行われてきた。
1992年にはシャワー室の覗き事件を受けて、それをセクハラ・性暴力として問題化し、「性問題に関する特別委員会」が立ち上げられるなど、寮空間のあり方について様々な話し合いが行われたことが、当時の「吉田寮新聞」第72号(同年3月3日)、第73号(同年4月30日)、第75号(1993年2月20日)の記事から分かる。比較的近年で言えば、複数のセクハラ事件を契機として、2014年にセクハラ対策特別委員会が設置され、セクハラ被害の相談窓口としての活動や、寮内で性やジェンダーについて話す場を作る取り組みなどがなされている。
「2015年熊野寮祭企画ストームにおけるセクシュアル・ハラスメントに対する声明」(2016年4月28日)は、このような問題意識がまとまった形で言語化され対外的に公表されているものの一つである。これは、2015年12月5日未明、吉田寮受付周辺にて行われたストームにおけるセクハラ行為のSNS投稿を問題化したものである。紙幅の都合から詳しく立ち入ることはできないのだが、A4用紙9頁にわたるその声明文の中では、熊野寮と吉田寮という空間が「「男性」性を共有した者たちが多勢を占める」ため、「男性」性を共有しない者を排除して構築されたホモソーシャルな場が幅を利かせると分析する。その上で、加害者の一連の言動には「寮を支配する「男性」的なノリ」が読み取れると指摘している。「ひとたびホモソーシャルな場が登場すれば、寮に住まう者たちは常に「男かそうでないか」と監視され続けることになる。そしてその中で「男性」でいられない者たちは、「男性」にモノとして消費されるほかない。「男性」が「男性」であることを謳歌する、そのすぐ足もとには「女性」あるいは「男性ではない者」として排除され、蹂躙された人間が倒れていることを自覚すべきである」という言葉で示されている問題意識は、それまでの寮内における女性差別や性暴力を問題化してきた取り組みの延長上にあると理解すべきであろう。
なお、1985年以降、吉田寮が発表する募集要項において募集対象は、「男女学生多数」と性別に言及する形で書かれていた。90年代の入寮募集パンフレットには、女性として吉田寮に住むことをテーマとした文章がよく掲載されており、男子寮と誤解されがちな学生寮として「女性」が住んでいることをアピールすることが切実であった状況がうかがえる。一方で90年代以降、寮内においても、「男・女」という「性別」で人間は二分できるという男女二元論が抑圧を生じさせている問題を指摘する声が現れるようになっており、2005年の募集要項からは募集対象の「男女学生」という文言が消えた。ただし、入寮希望者が寮自治会に提出する入寮願には性別選択欄が残っていたりと不徹底な部分もある。
まとめ
吉田寮の「女子入寮」は、ストーム事件を契機として1974年に始まったが、その歴史はいったん継承されなかった。1985年に「女子入寮」は再開し、定着していく中で、単に形式的・制度的な差別を撤廃するだけでなく、実生活上における様々な形の差別を問題化し、そのようなことが起こりにくい場所づくりが様々な形で試行されてきた。その延長の中で、「男・女」という枠組みの自明性も問い直され、募集要項における文言から性別についての言及はなくなった。寮空間のあり方の見直しは自治のなかで現在も連綿と続いている。
目次へ戻る
《コラム3》新棟建設とオールジェンダートイレ
理念と寮内外での交渉
2015年に完成した新棟のトイレは、全室個室の洋式型であり、性別指定のないオールジェンダートイレとして使われている。これは、福利厚生施設として性のあり方に基づく排除を行わないために、寮内および大学当局との団体交渉で議論を重ねて設置に至り、建設後に運用されてきた設備である。ここに至るまでの歴史を資料に基づいて振り返る。(小)
なぜオールジェンダートイレを求めたか
吉田寮現棟のトイレの設備は、一方の壁に沿って男性用小便器が並び、反対の側に壁と扉で囲まれた和式大便器が一個ずつ並んでいるという状況で、もともと男子トイレであったものを、女子入寮が始まって以降に共用トイレとして運用し、新棟建設の議論を始める時期には基本的に性別指定のないものとして使っている状況であった。2012年9月に新棟建設を大学当局と合意して以降、新棟の設計について検討をする中で、2013年1月から2月にかけて、寮内でトイレについての議論がなされた。そこで、トイレを性別指定なく使えて、かつプライバシーや防犯面も考慮したものにしたいとの提起があった。それは、公共空間である以上、誰でも安心して使いやすいトイレが必要であるという理由からであった。別稿「誰が入寮する資格を持つか入寮枠の性別要件をめぐる歴史」でも書いたように、寮を女性差別・性暴力が起こりにくい空間としようという志向性には寮内に長い系譜があり、この設計を巡る議論にもその蓄積が反映されている。話し合いの過程の1月24日には、『トイレのレッスン』(原題:Toilet Training/監督:Tara Mateik and the Sylvia Rivera Law Project/2003年)という、トランスジェンダー当事者の監督が作成した映画の上映会も行われた。そのドキュメンタリー作品は、男女別トイレが精神的・物理的に健康を阻害されるバリアとなることについて、当事者のインタビューをまとめたものである。そして、2013年2月、洗面台と防犯ベルを内設した完全個室型のトイレを大学当局に対して要望した。
大学当局との交渉
吉田寮からの要望に対する学務部(現・教育推進・学生支援部)からの返事は3月にあり、「トイレについては、男女別にする予定」との返答がなされた。そこで、寮務担当の窓口や3月26日、28日および4月12日の団体交渉において、吉田寮からの反論がなされたが、大学当局側も「男女別トイレが一般的である」「男女共用トイレは性犯罪が起こりやすい」「異性と同じトイレを使うことが嫌な人も多いはず」などと主張して男女別トイレを譲らなかった。これに対して吉田寮は、「「一般的」でないからと否定するのは少数者の圧迫」「オールジェンダートイレが、男女別トイレに比べて性犯罪が有意に起こりやすいという根拠がない」「吉田寮が求めているのは誰もが使いやすいトイレであり、より簡潔な構造のものを最初に作れば話し合いによって使い方を決められる」と反論した。さらに、それまで3回の交渉の出席者である学務部の職員が自らの権限では大学当局の方針を変えられないと主張していたことから、赤松明彦副学長の出席を求めた。赤松副学長出席のもとで開かれた5月10日の団体交渉において、吉田寮は交渉冒頭で『トイレのレッスン』を上映し、改めてオールジェンダートイレの必要性を説明した。赤松副学長はオールジェンダートイレの意義は認め、「吉田寮だけの問題ではなく公共のトイレ全体をどうするべきかという問題である」と述べた上で、将来的に間仕切り・標識を外してオールジェンダーに移行する可能性を認めた。しかし、「この問題の議論は長い時間がかかる」と述べ、建設時にトイレを性別指定のないものとすることには否定的で、交渉の破棄もちらつかせた。交渉決裂のリスクを重くみた吉田寮は、同年6月着工に合意。7月から工事が始まり2015年2月に完成した新棟に作られたトイレは、個室型で中央に仕切り板が設けられ(図)、男・女分けの標識が付けられたものであった。
しかし、吉田寮は、誰もが使いやすいトイレという理念には、性別指定の区分は不要であるという理由から、標識を取り除いてオールジェンダートイレとしての運用を開始した。その後の新入寮生のオリエンテーションでは、二元論的な性別という枠によってトイレから排除される人がいるという問題を扱い、オールジェンダートイレとして運用することの意義を説明するとともに、上述したような交渉の経緯が共有されている。
紙面では、図表や写真も掲載しています。ぜひご覧ください。