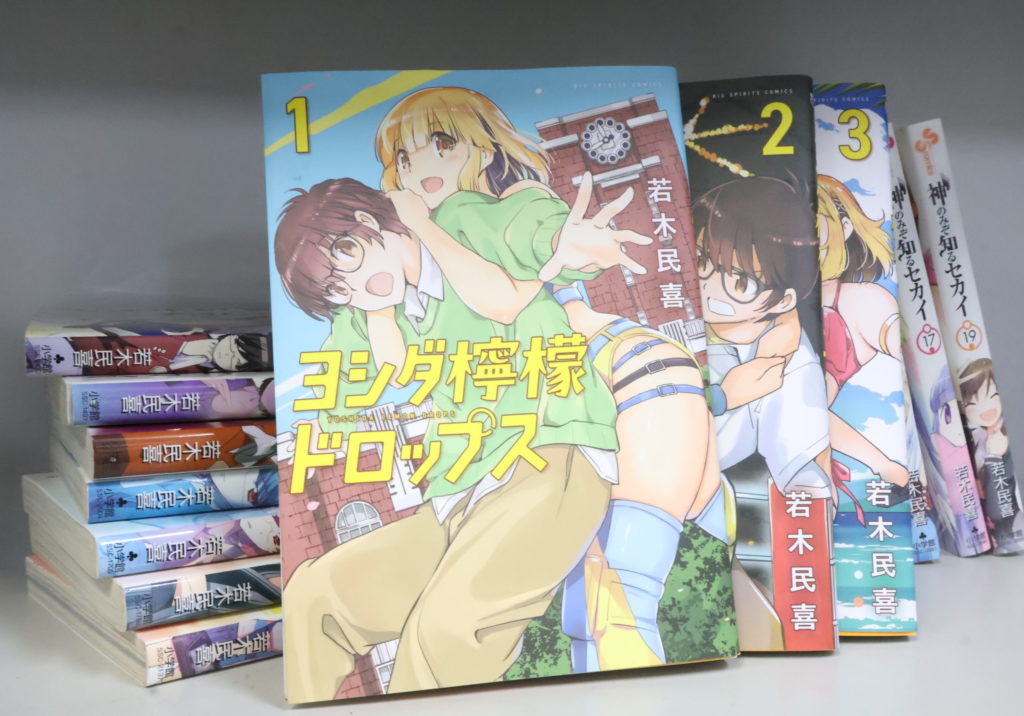【卒業生インタビュー 京大出たあと、 何したはるの?】Vol.12 味の素株式会社 会長 藤江太郎さん 「幸せの素」で世界を満たしたい
2025.04.01

手に持つのは、ウインドサーフィン部2025年全国優勝を祈願したフィン
目次
高校時代に牧場修業ウインドサーフィンに没頭
信念は「志×熱×磨」
環境問題や物価高への意識
「企業経営は箱根駅伝」
高校時代に牧場修業
――京大入学前について。
子供の頃はわんぱく坊主でした。お年玉を貯めて自分の鍋や包丁を買うほどの料理好きで、NHKの「きょうの料理」という番組が好きでした。料理をすることも好きでしたが、それよりも家族や友人に振舞った時に喜んでくれる顔を見るのが好きでした。
――高校時代について。
大阪府にできた新設高校の1期生として入学しました。不良の多い高校でしたが、気持ちのいい人ばかりで面白い学校でした。
高校時代、3ヶ月ほど学校をサボって北海道の牧場で修業をしたことがあります。牧場の経営をしたいと思い牧場に電話をかけて回りアポイントを取りました。牛を300頭ほど飼っている大規模な牧場で、そこでの仕事は大変やりがいがありましたが、牧場主から「藤江の家は金持ちか?」と聞かれました。「普通のサラリーマン家庭です」と答えると「それじゃあ無理だ」と言われました。当時、牧場を経営するための土地や機械を揃えるには3億円ほどの資金が必要でした。牧場主の3歳の娘と将来結婚するなら、と言われましたが諦めました(笑)。しかし修業を経て、酪農業は世の中のためになる仕事だと実感しました。
――京大を目指したきっかけについて。
最初は酪農を学ぼうと北海道大や帯広畜産大を目指していましたが、酪農の夢を諦めてからは、今でいうサステナビリティに近い分野を学ぼうと思い農学部林学科を志望しました。京大農学部林学科卒だったいとこから森が自然を守る機能について聞いたこともきっかけの1つです。
目次へ戻る
ウインドサーフィンに没頭
――大学時代について。
大学から新しいことをしたいと思うなかでウインドサーフィンと知り合いました。必要な費用をアルバイトで稼いで没頭しました。当時、ロサンゼルス五輪にウインドサーフィンが初めて採用され、最終強化選手にまでなりました。本当は学業と両立させたかったのですが、「京大農学部卒業」というよりは「京大琵琶湖学部卒業」というくらい熱中していました(笑)。
3回生のときに同好会から体育会にしようと動きました。当時、ウインドサーフィンは有名でなく、それほど成績も良くありませんでした。そんな同好会が体育会のメンバーになっていいのか議論になった中で、大学に陳情して、ようやく認めてもらいました。その過程で学んだことは大きいと思います。
今年2月、京大ウインドサーフィン部がインカレ団体戦(全日本学生ボードセーリング選手権大学対抗戦)で7年ぶりの全国優勝を果たしました(本紙3月16日号参照)。OBとして嬉しい想いでいっぱいです。
――ウインドサーフィンの経験・知見を会社経営に活かせたことは。
ウインドサーフィンは海に浮かべたブイの間をジグザグに通り、風上に行って風下に下りてくるスピードを競うスポーツです。左右どちらの海面に進むか判断するには、天気図を読んだり風や潮の流れを考慮したりする必要があるので、かなり頭を使います。
企業経営においても、どういう領域にいつ進出すべきか、どれほど資金や人財を費やせばいいのかを考えます。ウインドサーフィンと企業経営は共通点が多く面白いです。
――就職活動について。
就活解禁日の少し前に、味の素に就職した2年上の先輩から「就活しているか?」と電話で聞かれました。当時ウインドサーフィンに没頭してのんびりしていたので就活は何もしていませんでした。その通り答えると、西天満にある味の素社大阪支店に行けと言われました。父親のスーツを借り、明るいネクタイを買って大阪支店の面接に行きましたが、就活の準備や企業研究をしていないことはすぐ見抜かれましたね。面接で「味の素の製品を10個言ってみろ」と言われ、他社の製品名を言ってしまい、パンチパーマの総務課長にえらく怒られました。ですがそのとき、人に真剣に向き合う会社だなと思いました。
後から振り返ってみると、小学生の頃から食を通して人を幸せにするのが好きだったので、食品業界には何らかの興味があったと思います。
目次へ戻る
信念は「志×熱×磨」
――海外赴任で得た知見について。
初めて海外に赴任したのは42歳で、比較的遅い方でした。海外赴任では、各国・各地域で食文化が違うことの面白さを感じました。最初の赴任地である中国は豚肉や鶏肉が大好きな国でした。同じ中国国内でも広東料理や上海料理、北京料理はそれぞれの美味しさがあります。地域間の違いは驚きも含めてすごく面白かったです。
一方、海外勤務と国内勤務には、人と人との信頼関係が色々な物事の基本になるという共通点があります。当時の中国では「味の素Ⓡ」の売り上げが芳しくなく、従業員に給料が払えないほどの状況に追い込まれましたが、信頼する中国人マネージャーと協力して事業を立て直しました。その信頼関係は今でも続いています。
信頼関係があれば様々な困難は乗り越えられることを海外赴任で学びました。
――信頼関係を作る時に大切にしていることは。
「志×熱×磨」が大事だと思います。「志」というのは、自分がどうしたいのか、どうありたいのか、ということ。これを相手に伝えきらなければなりません。「熱」は熱意のことです。志に対する熱意がどれだけ高まっていくかが大事です。そして、志と熱意があるのが大前提ですが、実力を磨き込まないといけません。信頼関係を作るときにも「磨」が大事だと感じています。
――2022年に社長に就任した。刻々と変わる社会情勢をどう乗り越えてきたか。
「何が起こるかわからないことだけがわかっている社会である」と考えてきました。そうした社会で生き残る方法を考えると、自分の力をつけ続けるしかありません。そのためにも、「志×熱×磨」で個人が力をつけていく、同時に組織としても力をつけていくことが非常に大事だと思っています。
社会では「自分の目標を会社の目標に合わせる」ことを求められがちですが、僕は自分のやりたいことを軸にして、会社の志(パーパス)と重なる部分を探せばいいと思います。僕は従業員に、自分の志と重なる部分を探して「会社をうまく活用して使い倒していけばいい」と言っています。これが本人の成長に繋がりますし、優秀な従業員が力を発揮することで会社も良くなります。
何があるかわからない社会なので、自分の力を高め続けるしかない。そのためには志という文言に戻って考えてほしいです。
目次へ戻る
環境問題や物価高への意識
――味の素の事業としてなじみ深いのは食品産業だが、化粧品や電子材料といった事業にも取り組んでいる。多岐にわたる事業をまとめることの難しさや面白さは。
例えば皆さんが使っているパソコンの中にも「味の素ビルドアップフィルムⓇ」という製品が入っています。多岐にわたる事業の中で、味の素はアミノサイエンスⓇ(※)という大きな軸を持っています。味の素はアミノ酸のはたらきを100年以上探求し続けてきた会社で、アミノ酸に関するノウハウや、そこから生まれてくる素材の活用方法を世界一持っています。「味の素ビルドアップフィルムⓇ」も「味の素Ⓡ」を作る製造過程で出てきた副産物から出来ており、広い意味でアミノサイエンスⓇを活用しています。味の素が発展する1番の基盤は、アミノサイエンスⓇです。
※編集部注 アミノサイエンスⓇ
アミノ酸のはたらきに徹底的にこだわった研究プロセスや実装化プロセスから得られる多様な素材・機能・技術・サービスの総称。また、それらを社会課題の解決やWell-beingの貢献につなげる、味の素グループ独自の科学的アプローチのことを指す。
アミノ酸のはたらきに徹底的にこだわった研究プロセスや実装化プロセスから得られる多様な素材・機能・技術・サービスの総称。また、それらを社会課題の解決やWell-beingの貢献につなげる、味の素グループ独自の科学的アプローチのことを指す。
――味の素が主体的に自然の循環に関与している。
「ピクチャー・オブ・ザ・フューチャー」という手法で、2050年の社会の姿について、若い従業員を中心に議論をしました。そのなかで定めたアミノサイエンスⓇの4つの成長領域の1つがグリーン分野です。例えば、サトウキビを原料に「味の素Ⓡ」を作り、そこから生まれる副産物を畑に戻すとアミノ酸リッチな肥料になるので、アミノ酸がより活きていきます。昔から味の素は、事業で利益をあげながら、地球環境を良くするという理念のもと、事業を進めてきました。創業時はサステナビリティという言葉はありませんでしたが、時代が追いついてきたのは非常に嬉しいことです。
日本企業の多くは、環境に与えるネガティブな影響を抑える事業をしていますが、味の素の場合は、ポジティブな影響を与える事業に長年取り組んでいます。
例えばアミノ酸製剤を用いて、温室効果ガスの削減に取り組んでいます。温室効果ガスのうち、牛のゲップに含まれるメタンは大きな割合を占めています。当社の製剤を使うとコストを上げずにメタン排出量を10%程度削減できます。現在、乳業メーカーと協業して持続可能な酪農業を目指しています。
これもアミノサイエンスⓇを活用してポジティブなインパクトを生み出す事業の一環です。
――運送事業で同業者と協力体制を敷いたり、スタートアップ企業と協働したりしている。味の素だけにとどまらない体制を作っている意図は。
1社だけでできることもありますが、他社と組むことで社会への影響力を大きくできます。食品メーカー各社で資本を出し合って作った、F―LINEという物流会社は「競争は商品で物流は共同で」という理念を掲げています。物流などの共通機能は競争領域ではないので共同して取り組み、競争領域ではしっかりと競合するという考えです。例えば、運送を1社だけでまかなうと、一方通行的にしか物を運ぶことができません。しかし他社と協働すると、出発地と終着地の両方向から荷物を運ぶことができます。
このような非競争領域はもっとあるので、味の素は会社の中だけにとどまらない、開かれた会社である必要があります。
――今は物価高の時代。食品業界を主導する企業の1つとして、どのような考えを持っているか。
中国とフィリピン、ブラジルの3か国で働いた経験が非常に活きています。日本では「値上げ=悪」という考えに30年間ほど陥っており、「失われた30年」と呼ばれる課題に繋がりました。
ブラジルの場合、物価が10%ほど上がることで、自然と最低賃金が上がる仕組みになっており、長期的には消費者の購買力が戻り好循環になります。健全な賃上げによって景気を好循環させる基本的な仕組みを作らなければなりません。
日本の問題は、賃金が上がらなかったことにあります。賃金を上げるためには、商品の値段を継続的に上げることが大事です。日本は福祉制度があり、所得の低い人に対するサービスが整備されています。低所得者に対する支援をより拡充する必要がありますが、少なくとも、「値上げ=悪」という考えに一石を投じていきたいと、味の素の会長として提言しています。
ただ、最近は風向きが変わってきています。3年前は「この時代にどうして値上げをするんだ」と怒られることがありましたが、最近は値上げをした方が業績が良くなると知られるようになってきました。今後、大手企業だけでなく中小企業でも、値上げがどれほど賃上げに繋がるのかを注目することが重要だと考えています。
目次へ戻る
「企業経営は箱根駅伝」
――入社してから本を読むように上司に言われたとのこと。最近印象に残っている本は。
新人時代は「年に100冊は読め」とよく言われました。病気をして入院した際にも本をたくさん読みました。最近読んでいる本で非常に良いのが『1日1話、読めば心が熱くなる365人の仕事の教科書』(致知出版社)です。1日2ページほど読み進めると、自分が知らなかったことに気が付きます。読書は知的好奇心を刺激するだけでなく、文章を自分なりに咀嚼して得た知見を企業経営に生かしていく楽しさがあります。
競争力の根本的な源泉は無形資産、とりわけ人財資産だと思っています。人がどういう時にやる気になるか、困難を乗り越えられるかを知るヒントが、本や活字の中にあるのです。
――会社の中で新入社員と話す機会を作っている。社内の風通しに関して心がけていることは。
僕自身、新入社員から学ぶことも多いです。長く生きている方が失敗などから学んだ経験も多いですが、例えばAIなど新たな技術を活用することに関しては若い人の方が長けています。同じ人間ですので、地位によって偉そうにするのではなく、お互い様で学び合うことが必要です。立場の違いで物が言いづらい状況が一番良くありません。会長だからといって裃を着るのではなく、胸襟を開いて従業員の言葉を聞くことを大事にしています。
――設立100年を迎える企業を率いることについて。
企業経営は箱根駅伝のようなものです。晴れの日もあれば雨、雪の日もある。上り坂もあれば下り坂もある。逆風もあれば追い風もある。何が起こるかわからないけれど、1分でも1秒でも早くたすきを渡そうと次に向かいます。
リーダーが代わっても業績が大きく変化しないことが、日本企業の強みだと思います。1人のカリスマが引っ張っていく会社ではなく、志の合った集団が継続して事業に取り組み発展していく企業でありたいと思います。僕は味の素の第14代社長を務めました。期間は3年ほどと、あまり長くはありませんが、企業理念を受け継いで次に渡すことができたので、非常に良い区間を走れたと思います。
――仕事をしていく上の原動力は。
原動力は、従業員やお客様といろいろな信頼関係を結んでいくことです。幸せを他の人にあげればあげるほど、その人自身も幸せになる。「幸せの素」で世界を満たしていきたいという気持ちが原動力になっています。好きなテレビ番組が「オモウマい店」(中京テレビ)です。店主が一番幸せそうなことが好きな理由です。店主がお客さんに、差し上げたいことを深く考えていて、そういう人たちはすごく幸せだと思います。
――現在の志は。
世界を健康で幸せな状態で満たしたいというのが僕の志です。味の素にいるので、アミノサイエンスⓇを用いて世界をWell-beingで満たしたいですね。
病気になって、改めて健康のありがたみを実感しました。親身になってくれた家族や同僚に恩返しをしたいですし、Well-beingの価値を再認識することができたので、自分が病気になったことにも何か意味があったのだと思います。
――ありがとうございました。
目次へ戻る
藤江太郎(ふじえ・たろう)
1961年、大阪府高槻市生まれ。高槻北高校を経て京都大学農学部林学科(当時)卒。1985年に味の素株式会社に入社。フィリピン味の素社社長、ブラジル味の素社社長を経て2022年に代表執行役社長に就任。2025年2月、体調不良を理由に社長を退任し、会長に就任(現職)。
1961年、大阪府高槻市生まれ。高槻北高校を経て京都大学農学部林学科(当時)卒。1985年に味の素株式会社に入社。フィリピン味の素社社長、ブラジル味の素社社長を経て2022年に代表執行役社長に就任。2025年2月、体調不良を理由に社長を退任し、会長に就任(現職)。