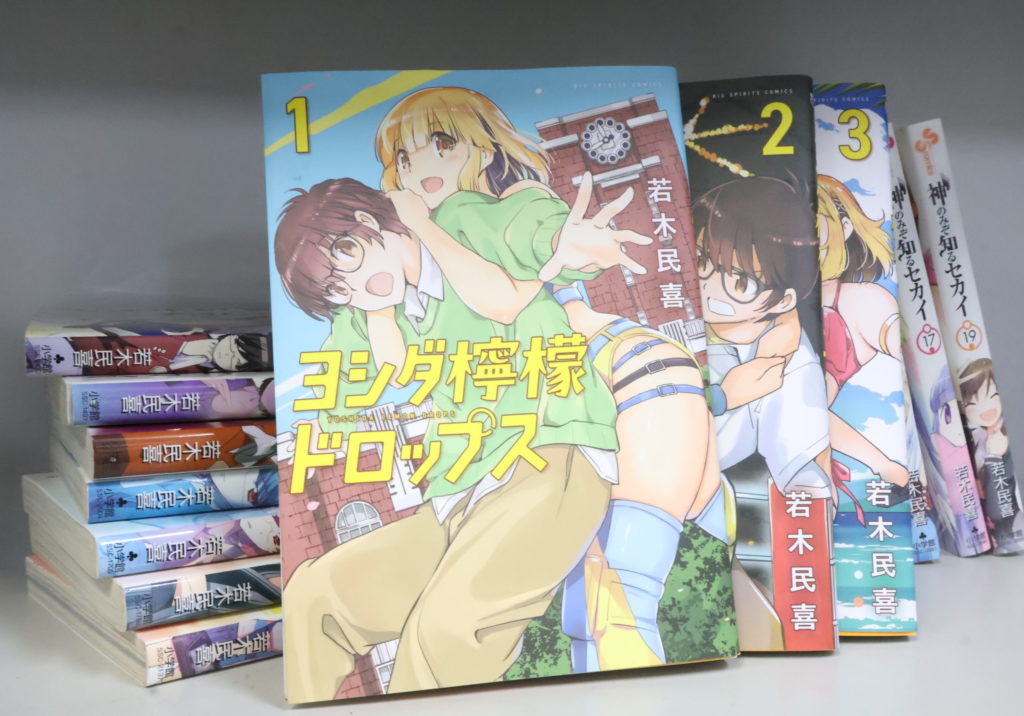【卒業生インタビュー 京大出たあと、 何したはるの?】Vol.11 サイゼリヤ元社長 堀埜一成さん 「我が人生頂上なし」
2025.02.16

目次
将来設計図は持たない全体を俯瞰する将来設計
「策略」で転職
「気楽」なレストラン
明るい未来を示す
まずは見てみよう
将来設計図は持たない
――幼少期について。
幼少期は非常に病弱でした。それもあってわがままを許されて育ったと思います。内向的な性格で友だちはほとんどいなくて、遊んでいたのは近所の女の子たちだけでした。中学校1年生の時に大阪へ引っ越したことが、大きな転機になりました。当時は転校生が珍しかったのもあって周囲から注目され、それまでの内向的な性格が、嘘のように活発になりました。スポーツに励んだり、学級委員長を務めたりすることでチヤホヤされた経験が今のいい加減な性格を形成したと言えるかもしれません。
――京大受験について。
成績は決して良くなく、受験時も「合格の確率は25%」と言われましたが、大阪での生活で度胸が身についていて、多少のことでは動じなくなっていました。当日も、入試の数学がとても難しくて「誰も解けないだろう」とうれしくなったほどです。周囲が落胆している中で冷静さを保てたことが合格につながったのだと思います。
――学部選択について。
明確な将来設計図は持っておらず、最初から進路を決めて大学に進学するのは、自分の可能性を狭めてしまうのではという思いもあり、成り行き任せでした。
京大には入りたかったものの、特に勉強するつもりも目的もなく、技術系の学部の中で一番入りやすいだろうという理由で農学部を選びました。入学して何をしようかとなっても決めたのはアメフト部に入ることくらいでした。
――学部での研究内容は。
農学部では生物生産工学科(当時)に所属し、卒業論文では酵素の性質に関する研究を行いましたが、正直なところ、研究内容はよく分かっていませんでした。大学院では酵素の大量生産をテーマとしましたが、これも指導教官の「君は将来工場で働くだろうから」という勧めで実用的なテーマを選びました。しかし、大学院でも熱心に勉強したとは言えず、助手の方に頼りながら、最後の数ヶ月だけ頑張って修論を書き上げました。
――進路に影響を与えた出来事は。
必要な単位が足りなくて困ってしまい、授業担当の先生にお酒を持って相談に行くと、被験対象として「死ぬまで走るやつを連れてこい」と言われました。そんなやついないぞ、と困り果てていたら先輩が協力してくれ、無事単位をもらうことができました。そんな態度で、しかも当時は大学院に進学する人は少なく、進路指導の先生に大学院への志望を伝えたところ「京大を馬鹿にしているのか」と激怒されました。それでもなんとか合格すると、先生たちの態度が変わりましたね(笑)。様々な幸運や周囲の助けに恵まれながら、大学院まで進むことができました。
目次へ戻る
全体を俯瞰する将来設計
――大学卒業後は味の素に就職。その決め手は。
当時の農学部では先生から就職先を薦められ、面接に行くのが通例でした。あるとき先生に「味の素を受けてみるか」と言われ、味の素の創業家が出資していた奨学金を受けていたので、味の素に行けば返さなくていいと思って受け入れました。実際は返還しないといけなかったのですが(笑)。
――味の素時代、印象的な出来事は。
まずは偉い人がたくさんいる採用面接で、海外工場志望ですと豪語しました。ところが入社してみると技術系の全員が、まずは国内、それも工場ではなく研究所に配属されるんですね。様々なことをまとめて勉強させることが目的なのですが、当時はものすごく不満でした。
最初は制がん剤の探索というテーマを与えられて研究に取り組みました。初めはすごく嫌だったのですが、やっていくうちに楽しくなって、天職ではないかと感じていました。すると1年半後に九州工場への辞令が出ました。この異動は最初に志望していた海外工場勤務の準備にあたるもので、当時の上司が僕のために作ってくれたルートでした。ですが、研究が楽しかったので異動がすごく嫌だと思ったのを覚えています。そして九州で3年間アミノ酸製造の研究をした後、29歳でブラジル工場への辞令を受けました。
当時の味の素では、海外の工場へはベテランが行っていたので、久しぶりの若手の出向でした。私は30歳で製造部長に任命されて、ブラジル工場で「味の素」の原料、グルタミン酸ソーダを作っていました。日本から一番遠い工場だったので、目が届かないのをいいことに、色々な実験をして、他の人にはない経験をたくさんしていました。また、工場の従業員と釣りや投網で遊んでいると、日本から視察に来たお偉いさんに気に入られて、わんぱく小僧と名付けられて名前を覚えてもらうこともできました。なにが役立つかは分からないなと実感しましたね。初めは2年の約束だったのですが、帰りたくないと言って5年も居させてもらいました。
その後、国内のメイン工場で医薬用のアミノ酸製造を担当した後、周りから「だいぶ研究所から離れているし、そろそろ新しい知識を入れた方がいい」と勧められて研究室に戻りました。
印象的な仕事は、アミノ酸を作る微生物の研究所で人事面のマネジメントを任されたことですね。研究所には研究のように細かいことを考えられるメンバーはたくさんいましたが、人事のように全体を俯瞰して将来図を描く技術が不足していました。そういう発想をCDP(career development program。適性や希望を考慮しながら配属先や役職を決定して、従業員の能力を最大化するプログラム)のマップを作って示し、人事異動の草案をつくることもありました。そのマップは私が辞めた後も使われ続けたそうです。サイゼリヤでも自分で作りましたし、今の仕事であるコンサルティングにおいても、人の育て方や人事構成の将来設計をもって人材の育成を考える企業は多くないので、そのようなお話をする際に役立てています。
目次へ戻る
「策略」で転職
――サイゼリヤへの転職の決め手は。
実は僕より先に、ブラジル時代の上司がサイゼリヤに転職していて、その人から誘われました。ブラジルで3年間一緒に働いていたので、僕に生産管理の経験があることを知っていました。それは当時のサイゼリヤに不足していた部分でした。何度も誘われたのですが、僕はそもそもサイゼリヤそのものを知らなかったんです。さらに看板を見たら「ワイン」と書いてあって、「僕は下戸だから、なんでこの店に……」と断り続けていました。
2年が経ったとき、これが最後だから創業者の正垣社長に会ってくれと言われ、20世紀最後のクリスマスにホテルの高級なディナーに招かれました。次々に運ばれてくる手の込んだ料理をうまいな、すごいなと思って食べていたときに正垣さんが「どうだ、うまくないだろう」と。
これが転職の決め手です。最初は何を言っているのか僕には理解できなかった。色々聞いてみると、値段の高い料理は、普段はしない組み合わせの料理を出すのだけれど、そんなのうまいはずがない。いい材料を普通の組み合わせで食べるのが一番うまいんだと。
さらに追い打ちをかけるように、「サイゼリヤで農業と食堂業の産業化をしてくれないか」と打診された。この二つでコロッと傾いてしまって、転職を決めました。とにかく僕が知らない世界があるんだと、正垣さんのでっかい話にロマンを感じました。でも、入社後、「おまえみたいなやつは大きな話をしたら動くと思っていた」と、策略だったことを明かされました(笑)。
――転職の際、心残りは。
まったくなかった。後から聞いた話では、味の素で僕を海外工場の工場長にするという大抜擢人事が用意されていたそうですが、それを知っても何とも思わなかった。所詮スパイラルアップ、同じようなことを続けているだけだなと思ったんですね。僕はこれが嫌いなので、別の世界を見てみたかった。
目次へ戻る
「気楽」なレストラン
――入社後社長になるまで。
入社してすぐ、取締役として生鮮食品のバイヤーと農場開発に取り組みました。農場開発には特に力を入れていて、福島県・白河の山でレタス栽培を任されました。
ところが畑を作ろうと思ったら、大きな岩がゴロゴロ出てきて、耕運機が入らなかった。岩を掘り出そうとしても1週間で1個ぐらいしか取れない。では掘り出すのではなくて砕こうと。1台1億円くらいするストーンクラッシャーという機械を社長の私費で買ってもらって、整地をしました。そうすると深さ40㌢くらいの岩がなくなって、耕運機が入るようになりました。のちにこのストーンクラッシャーは原発事故の際に貸し出して、除染に活用されました。
水もなかったので井戸を山の頂上に掘ることもあり、かかったコストを計算するととんでもなく高価なレタスを作っていたことになるかもしれません。一見すると馬鹿げた試行錯誤をたくさん経験できたと思います。
――サイゼリヤの魅力、強みは。
美味しすぎるものを出さないところですね。美味しすぎると、ちょっとした振れ幅で味が落ちたと感じられてしまう。だから味の安定性を求めていて、その中で重視しているのは、まずくないこと。基準として、冷めたらまずいものは作らないという理念が昔からあります。熱ければごまかせても、冷めたときに本当の味がわかるんです。だから試作の際は冷ましてからも食べます。
また、色々なことが気楽なんです。特に価格は、あまりお財布を気にしなくていいようにしてあります。もう一つは店のざわつき感。店内は音が少し反響する環境にしていて、ざわざわしています。だから周りを気にせず話せて、楽しく感じられる。
それから安心感もある。ある店舗に視察に行ったとき、お母さんが小さい子を残して買い物に行ったこともありました。託児所みたいに信用してもらえているのかなと、うれしかったです。
――お気に入りメニューは。
フレッシュトマトのスパゲティ(※)ですね。余ったトマトを全部入れて作ったら美味しいものができて、よく売れましたね。スパゲッティはどれも好きですね。
※編集注:現在はグランドメニューから外れている。
目次へ戻る
明るい未来を示す
――社長の仕事とは。
ひとつは、リーダーとして従業員に対してどんなときでも明るい未来を示すことです。暗い話をしたら、組織全体が落ち込んでしまいます。
これを学んだのは、2010年のチリの炭鉱事故です。かなり多くの人が事故で炭鉱の中に閉じ込められたにもかかわらず、全員が体も精神も健康に帰還してきたんです。そこではリーダーが、俺たちは外に出られるんだ、明るい未来があるんだと、愚痴ひとつこぼさず常に明るい話をしたことが生存に繋がったと言われています。トップに立つ人間は、自分たちの将来が明るいことを言い切らないと駄目だと思います。
また、好奇心からとにかく世界各国の繁盛店を巡って、繁盛店に共通することとはなんだろうと考えました。結論は「美味しいから食べてほしい」という姿勢があることです。料理を褒めると、もっと食べてよ、と次から次に料理を出してくれる。儲かるという理由ではなく、自分たちが食べて美味しいもの、人に勧めたいものを出そうと学びましたね。
――自身は社長に向いていたか。
13年間任せてもらえたので、向いていたんだろうとは思っています。一つには楽観的であること。それだけだと放漫経営になりますが、いろいろな失敗を通して心配性な面もあって、それも役立ったと思います。他にも、ロジカルでありながら感覚も大事にしていて、そういう両面性を常に持っていました。
また、「これをやろう」と決断できる人は意外と少ないので、物事を決める力もリーダーに必要な素養だと思います。
――仕事で大切にしていたことは。
まず大切なのは観察です。最初に「プラン」が来るPDCA(Plan、Do、Check、Action)という言葉が嫌いです。僕が言いたいのは「See Think Plan」で、まずは見てから考える。問題を発見してからでないとプランを立てられないと考えています。
――社長時代の一番の成果は。
就任当初から、「技能を技術にしろ」と言っていました。どうしても食堂業では「俺の背中を見て覚えろ」と言う。これでは「技能」で、多店舗化に耐えられなくて駄目なんですね。そうではなくて、会議や論議を通して文字媒体を作り、伝えられる「技術」を築く。技術という概念を導入したことが一番の成果だと思います。
――心残りは。
サイゼリヤの店舗数を増やすために、店舗の面積を今の標準である75坪から40坪にしたいと考えていました。40坪はだいたいコンビニと同じ大きさなので、出店可能な物件が多くあります。だいたいの店舗モデルも見えてきていた段階で辞めてしまったのは残念です。
目次へ戻る
まずは見てみよう
――現在の取り組みは。
今はリンゴ農家さんと一緒に、ゼロエミッション農家ということを考えています。りんご栽培では、収穫したりんごのうち95%を捨ててしまうんです。こんなにもったいないこともないなと思い、捨てなくて良いリンゴ栽培に取り組んでいます。またリンゴでできれば桃など他の果物にも波及できるかなとも考えています。
――進路選択において大切にしていたことは。
いい加減な人間でしたから、意識的に大切にしていたことはほとんどなかったです。
ただ、親の反応を見ていたのかもしれないですね。親に自分の選択を話した際、嫌な顔をされるとその選択を取らないことが多かったです。ところが、サイゼリヤに行くよと話したら、とても喜んでくれた。それに背中を押されたと思って決めましたね。散々苦労をかけてきたので、親の反応を気にしていたんだろうなと思います。
――働く、生きていく原動力は。
僕の信条は「我が人生頂上なし」。頂上は死ぬまで見つけたくないです。死ぬまでに頂上に着いてしまったらその先はもう降りるしかない。だから最後まで成長していきたいということをずっと考えていますね。
――最後に、進路選択へのアドバイスを。
サイゼリヤ時代に社内報に書いたこともあるのですが、「世の中に失敗はない、予想していなかったことが起こっただけ」。何がなぜ、どのようにして起こったのか見てみよう。これが大成功への道しるべ、という言葉を残します。〈了〉
目次へ戻る
堀埜一成(ほりの・いっせい)
1957年、富山県生まれ。京都大学農学部、大学院農学研究科修了。81年味の素に入社後、ブラジル工場などでの勤務を経て、2000年、サイゼリヤ創業者・正垣泰彦氏より生産技術者として口説かれ、株式会社サイゼリヤに入社。同年、取締役就任。09年、同社代表取締役社長に就任、22年退任。現在はコンサルティング業、ホリノMIオフィス代表取締役社長。
食堂業と農業の産業化を自らのミッションとし、13年の在任期間で急速成長後の基盤づくり、成熟期の技術開発など独自の感性で会社の進化をけん引する。
1957年、富山県生まれ。京都大学農学部、大学院農学研究科修了。81年味の素に入社後、ブラジル工場などでの勤務を経て、2000年、サイゼリヤ創業者・正垣泰彦氏より生産技術者として口説かれ、株式会社サイゼリヤに入社。同年、取締役就任。09年、同社代表取締役社長に就任、22年退任。現在はコンサルティング業、ホリノMIオフィス代表取締役社長。
食堂業と農業の産業化を自らのミッションとし、13年の在任期間で急速成長後の基盤づくり、成熟期の技術開発など独自の感性で会社の進化をけん引する。