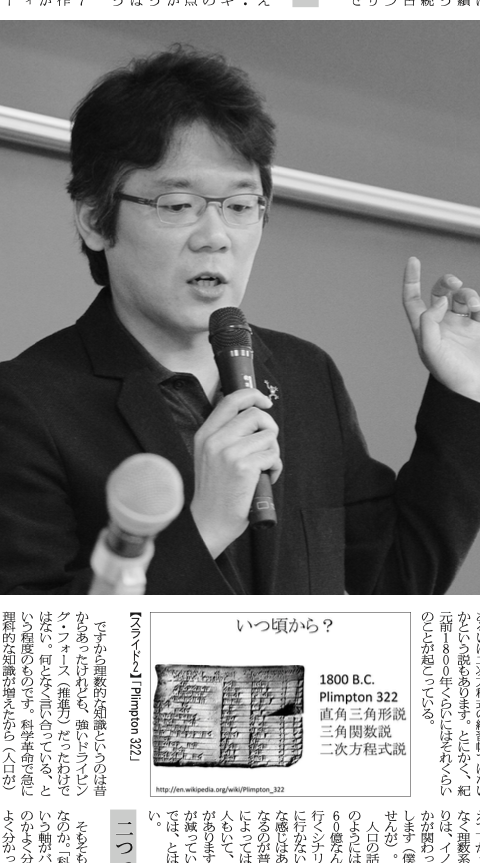【連載第十九回】京大新聞の百年 心が折れても「京大新聞のファン」
2024.12.01
「学生自治の話題を扱うのは使命だが、シンパシーを持てなかった」、「学生自治に対して妥協してはいけない」――同時期に在籍した編集員でも感覚は様々で、その多様さは「真面目と不真面目が共存していた」という紙面の雑多性にも表れる。25年4月の創刊100周年に向け、歴史を振り返る連載の第十九回は、前回に引き続き00年代後半から10年代にかけての編集部内外の雰囲気を聞き取り取材でたどる。(編集部)
50団体の要望まとめ、建て替え実現
拾い読み⑯ 「京大雑記」やスポーツ多い 2014年の紙面
00年代後半から10年代前半を知る4名への聞き取り取材の内容を掲載する。「関わり方が人それぞれ」との言葉どおり、関心や取り組み方が様々の各編集員を、京大新聞というひとつの団体につなぎとめたものは何だったのだろうか。(村)

―入社のきっかけは。
如 予備校が受験生に配っていたDMに東大新聞が入っていた。京大新聞はどんな感じかなと気になって見学に行った。
狭 浪人時代、予備校に京大新聞が置いてあって、読んでいた。実は(如)さんの「こくばん」(編集員コラム)もきっかけのひとつ。編集部でいろいろな意見の人がいることによる揺れを描写していた。意見が割れるようなことも自由に書けるのはおもしろそうだなと興味を持った。
―実際入ってみて、印象は。
如 私は旧ボックスを知る最後の世代。壁に「NO NO 天皇」とか書いてあって、政治色の強い時代の名残りがおもしろかった。先輩がベロベロに酔いながらザ・タイマーズを大音量で流して歌っているのを見たときは、やばいところに来たなと思ったけど(苦笑)。
狭 本や漫画がたくさん置いてあるあの雰囲気は心地よかった。
―会議の雰囲気は。
狭 おおらかな側面もあるし、話題によってはピリピリすることもあった。
如 自由な雰囲気だった。先輩がビールを飲みながら、「〇〇くんのペンネームは麒麟の麒で決まりね」みたいな。一般的な大学サークルのノリを求めて見学に来る学生は、カオスな雰囲気が嫌だなとか、この長い会議はいつ終わるんだろうとか思っていただろうし、実際、数人入ったけどあまり定着しなかった。
狭 年によって波がある。学年で5人ほどいると多いほう。それより少ないとバタバタして、しばらくして増えて持ち直して、また減って誰かに負担が偏る、みたいなイメージ。
如 誰が何を書くか、だいたい得意分野があったし、継続的に追うネタもあるから、担当が固定されがちだった。特に学部自治会や寮生とつながりのある編集員が問題意識を持って発議して、記事化に至るという流れが多かった。僕はノンポリで、そういう取材に取り組む人たちから見れば、主体的ではないと思われていたかもしれない。ただ、自分個人がどう思うかはともかく、そういうネタを扱うことは使命だと考えていたし、プラットフォームとしてあっていいとは思っていた。
―「こくばん」で、自治にシンパシーを持てないと書いていた。
如 その感覚は一貫してある。たとえば吉田寮問題は、今も続いているけど、やっぱり僕は部外者だという意識。我々がどうこう言うことではないと思うし、草葉の陰から見守りたい。
―学生自治に対して様々な距離感や考え方の人が共存していた。
如 そうだね、受け皿は広かったと思う。
狭 バチバチの政治闘争をやる場ではないし。
如 少し上の世代は連絡用のメーリングリストで喧嘩するほどだったと聞く。白熱して、別の人が「続きは編会で」と仲裁に入るとか。僕がいたときは、そこまでこじれることはなくて、ある意味で人材不足だったと言えるかも。たとえば熊野寮関係のネタを持ってくる編集員に対して、誰も何も言わない。編集部のチェック体制という観点では、もう少し「当事者」がいたらよかったかな。
狭 学生自治に関する話題は、自分自身が積極的に取材に行くことはなかったけど、興味は持っていたし、多くの学生に読まれるかはともかく、報じる意義はあると考えていた。今の京大新聞でもそういう話題が扱われていて、現役の人も意識しているんだろうなと感じる。
―印象に残っている記事は。
如 大学構内の池を紹介する「キャンパスポンド」みたいに、言ってしまえば当たり障りのない記事ばかり書いて、先輩に「おまえは何がやりたいのかまったくわからん」と言われた。どちらかというと僕は、車で新聞を運んだり、営業の役職をやったりと、執筆以外のプロセスに携わることが多かった。印刷所のインクの香りが好きだったなと今でも思い出すし、そういうことを体験できてよかった。
狭 自分が手がけた特集を、発行後の会議で同級生にこてんぱんに批判されたことがあって、心に傷を負った。A4で5枚ほど配られて、両面にびっしりと、ここがだめだ、この言葉はどういうつもりで書いているのか、などと指摘された。ちょうど新歓の時期で、見学の新入生に見られないように会議前にその資料が配られて、自分だけ心が折れた状態。その日の会議ではほぼ話さず、終了後にみんなで行く食事にも加わらず、ひとりで帰って家で泣いた。それがトラウマになって1年ほど記事を書かなかった。しかも、放任の雰囲気だから、誰かが間に入ってくれたりフォローしてくれたりすることもなかった。
ただ、そのとき卒アル担当を務めていて、それは全うしなければという不思議な使命感があったから、その後も普段の会議には出席し続けた。今となっては、そういうことを経て文章が書けるようになったと思うし、その同級生のことを憎む気持ちはまったくない。最近は、職場のウェブサイトでコラムを書いたり、趣味の競技かるたの会誌に対談記事を載せたりしているから、当時の経験が活きている側面がある。
如 記事を書かなくなる時期は僕もあった。とある取材相手の方への配慮不足で、めちゃめちゃ怒られて謝罪記事を出した。それから半年くらい書かなかった。
―営業の手応えは。
如 トラブルがあって予備校1社から出してもらえなくなったりしたけど、資金に困ることはそんなになかったと思う。
―アルバム担当に使命感。
狭 5つぐらいある役職を編集員で分担している。それぞれ時間がかかることをやっているし、それを誰かに投げるのは申し訳ない。主要な財源だからしっかりやらないと、という意識もあった。
―いろいろありつつ、やめずに在籍したのはどういう思いか。
如 つかず離れず、束縛されないし、所詮学生サークルだから、誰かがいなくなったら誰かが代わりをやる。それがむしろ戻りやすかった。体育会の部だと練習をサボると退部になりうるし、会社もそれに近い。京大新聞は良くも悪くも放任で、楽しかった。現役のみなさんも自由を謳歌してもらえればと思う。
狭 やっぱりボックスという空間が好きという気持ち。あとは、京大新聞に存在意義を感じていた。独自の視点でいろいろなネタが集まっていて、カオスな記事もある。浪人生のときから読んでいて、ある意味ずっと京大新聞のファンだから、心の中でいいなと思う気持ちがあるし、だからいろいろあっても関わり続けたんだと思う。〈了〉
―入社のきっかけは。
文章を書くのが好きで、作ったものが形になって残るという点で京大新聞に興味を持った。1回生の春から存在を知っていたけど、新歓の宣伝文の下に小さい字で、新入生が多すぎると面倒を見切れないと書いてあって、躊躇した。それで2回生の年に入った。冷淡な空気を予想していたら、思ったより面倒見がよかった。先に入った同回生から、人によって関わり方が全然違うから自分でネタを探すことが大事だよと言われていて、まさにその通りだった。
―山口さんは書評に力を入れた。
自分はノンポリだからそれくらいしか発露できないという気持ちがあって、書評を通して風刺を楽しんだ。たとえば当時の松本紘総長の著書を少し意地悪な視点で評すとか。ツイッターができたばかりのころで、記事を読んだ方が感想を投稿してくれていて、それを見るのが楽しみだった。批判的なコメントも、おもしろいと言ってくれることもあって、そういう反応をすぐに知れるのが新鮮な体験だった。
―編集部の雰囲気は。
「ここぞ」の集中力がすさまじいという印象。いつも作業がギリギリで、入稿日の朝3時、4時の土壇場になると、いい意味で「どうしてこのクオリティのものが」と驚く成果物ができあがる。そういう能力に長けている人が多かったんだろう。
―特集の検討や原稿の校正では厳しい指摘が飛ぶという声も。
それはお互い様。自分で気づけないことを言ってもらえるのはありがたいし、やめてほしいなと思ったことはない。
―編集方針に関して、ミニコミ的でもマスコミ的でもあったという話がある。
たしかに両面あった。付け加えると、真面目と不真面目がいいバランスで同居する数少ない媒体だと思う。真面目な顔をしてニュースを読むキャスターの隣で漫才をやるような。それは一般紙にはない特長。逆に不真面目に振り切る媒体は他にあったとしても、そこに学内情勢の真面目な解説が共存するのは珍しいし、それが魅力だと思う。
構成員としては、ずっといなきゃいけないわけではないという気楽さも感じていた。久しぶりに顔を出しても、「この記事書く?」と言って受け入れてくれる。懐の深い団体だと思う。
―印象的な記事は。
灘高校教員(当時)の前川直哉さんへのインタビュー。ジェンダー研究者として、学校でジェンダー学の授業を実施するなど興味深い取り組みをされていると先輩経由で知って、話を聞いた。掲載後、大学のLGBTQ支援サークルの代表さんから、発信してくれてありがたいというお言葉をいただき、励みになった。
記事ではないが、入試のカンニング事件も印象的。当時、一緒にボックスにいた(春)が問題文の流出に気づいて、京大新聞のツイッターで指摘した(前回の連載参照)。その時点では受験生によるカンニングだとは分からず、トラブルとか内部告発的な流出とか、様々な推測が成り立つ。何があったのかと投げかける意図でツイートしたところ、賛否両論の反応があった。投稿しなければ騒ぎにならず逮捕者が出なかったのではないかとか、逆によくやったという声も。その件をきっかけに京大新聞を知った方もいるだろうし、いろいろな意味で影響があった。
あとは円城塔さんの講演会。芥川賞をとられた直後だった。かねがね好きな作家さんで、ダメ元でお願いしたところ快く引き受けてくださった。もう少しお客さんに来てほしかったが、講演自体は申し分なかった。
―現役編集部に一言。
百周年に向け、真面目な企画以外におふざけ要素もあっていいと思う。働いていると、学生時代ほどはっちゃけられない。今のうちに、めいっぱい取材・執筆・議論を経験してほしい。〈了〉
前回掲載した中川崇さん(06〜11)への聞き取り取材記事のうち、現ボックス棟建設に至る経緯に関する内容を以下に掲載する。(村)
京大新聞に入ったころはボックス棟が木造で、脆弱性に危機感があった。しかもボックスの床には灯油がしみ込んでいる。当時はエアコンがなく、学生部から支給される灯油を取りに行ってストーブを使っていた。何かあったらどうしようという不安を抱えるなか、06~07年にかけて大学でボックス棟の建て替えに予算がつく状況になった。職員からもこの機会を逃すと次があるか分からないと聞いていたから、危機感もあいまって、力を入れて動いた。B連という50団体からなる組織があり、その時期にちょうど持ち回りの幹事が京大新聞に回ってきて、私が担当になった。
たくさんの団体の意見をまとめるのは大変で、そもそも建て替えるということの合意に労力がかかった。合意後も、建物の設計や各団体のボックスの配置など、いろいろと検討事項があり、ワーキンググループを立ち上げて議論した。そこで原案を作って、総会に示して合意を取りつけた。たとえば、移転でスペースが減る団体には共用の倉庫を割り振ることにしたが、山岳部からは命に関わる備品が含まれるため他団体の荷物と一緒に置くのは避けたいという要望が出て、それならこっちのスペースを使ってもらおうとか。あとは、階段を一部逆向きに設計すれば階段下を有効活用でき、写真部の暗室として使えるなとか。音楽系団体のための音出し共用室について、広い部屋も必要だと後から分かったから、頼んで設計を変えてもらった場面もあった。もめることも一部であったが、個別の相談にはできる限り対応したつもり。
一段落して別団体が幹事になった後も、担当として会議に出て状況を注視し続けた。A・B棟ができて京大新聞も含めた該当団体が移転し、それらが入っていた旧ボックス棟をつぶして、C~E棟を建てることで、全団体が移ることができた。全棟ができ移転完了したタイミングで、また京大新聞に幹事が回ってきた。「運命やな」と思いながら、私自身2回目の担当になった。このとき問題になったのは、共用の会議室ができたのに活用できていなかったこと。だから規約を定めて使えるようにした。その流れで、B連じたいの新しい規約も作成し、名も変えた。B連には吉田南の学生集会所の団体も含まれていたが、その後建て直した学生集会所に残った団体もあれば、西部に移ってきた団体もあった。いま稲盛財団記念館が建っている場所(当時アジア・アフリカ研と呼称)から西部へ移転してきた団体もあった。改めて、西部構内の新ボックス棟の関係団体の集まりだと明示したほうがいいという議論があって、現在の「西部課外活動施設使用団体連絡協議会」、通称・西団連という名前に変えた。
振り返ると、無事に建て替えできてよかった。エアコンが完備され、火災のリスクが激減し、トイレなどの衛生面も大幅に改善された。当時の尾池和夫総長と学生担当の東山紘久副学長は学生に対して比較的優しく、この2人の体制のもと枠組みを決められたことも大きかった。印象的なのは、建物の24時間開放をめぐる議論での尾池さんの言葉。「23時間59分は開放して1分間だけ閉めるのはどうか、という提案があったとしても乗ってはいけないよ」と。自治や自由に対して妥協してはいけないという趣旨。1分が2分に、2分が2時間になり、そのうち完全に閉められてしまうぞと。これは入学アルバムか何かの総長インタビューで改めて聞いた言葉だったように思うが、歴代総長のなかでも学生自治について深く考えてくれていたのが尾池総長だった。学生の自主的な動きはもちろんあったけど、そういった様々な背景のもと、ハード・ソフト両面で学生にとって課外活動しやすいボックス棟ができあがったことは喜ばしかった。〈了〉
新聞社▼京大新聞主催・円城塔氏講演会▼第3回文学賞開催→吉村萬壱氏インタビュー:初めて食べる「味」の作品を 時事▼原理研に注意▼複眼時評:「あの戦争」に関わる3点の史料/貨幣の価値を変えよ▼書評:『近代日本の国家権力と天皇制』▼公開講座:マスメディアが作るアフリカ像▼就職先一覧▼シンポ:北朝鮮の人々▼トークライブ:震災映像の想像力 教育研究▼二次試験までに読んでおきたい本:『ぼんやりの時間』『不安の概念』▼アイヌ遺骨「追求する会」再度抗議:話し合いに至らず▼文、セメスター制へ▼▼英語による教養科目が開始▼元岐阜大学教授・寺島氏→「英語で授業」が何をもたらすか▼国際連携学位プログラム創設へ▼新1回生にTOEFL試験▼附属図書館に新エリア:ラーニング・コモンズ▼附属図書館、盗難相次ぐ▼国際人材総合教育棟、埋文調査▼総博特別展:研究者と作る京料理▼関東大震災フィルム、京大書庫で確認▼フィードバック期間導入▼書評:『「サル」化する人間社会』▼春秋講義:生命と老化 大学運営▼自転車シェア実験導入→利用者の声受け増台▼京大雑記:学生不在の「民主主義」▼学域・学系制、臨時評議会で可決▼学務部棟に防カメ:金庫周辺を管理徹底▼総長選、意向投票が「意向調査」に▼書評:松本紘総長『京都から大学を変える』→エンターテイナーとしての才能を証明▼京大ジャパンゲートウェイ構想、文科省に申請▼新総長に山極氏→単独インタビュー:「権限集中より合意形成を」▼「山極氏に投票しないで」:学生有志が貼紙「研究者として不可欠」▼企業への学術指導、公務で実施可に▼京大あれこれ:吉田南図書館裏の黒ねこ/総人棟の扉/京大理容室▼出席登録を電子化へ▼吉田南グラウンドに照明設置▼学内で私服警官見つかる:総長「毅然とした態度で臨む」▼11月祭、教員酒場が教員甘酒に:総長が自粛要請▼学生集会所建替え大幅な遅れ:震災で人材・機材不足▼京大、携帯3社のワイファイを導入▼吉田南中庭を整備:木を切り日当たり良く▼入試検定料、コンビニ支払い可に▼障害学生支援ルームに聞く:学びやすい京大へ 学生▼寮紹介▼農家と料亭をつなぐ:京大生の野菜卸売▼1コマでキャンパスを飛び出そう▼ドイツ留学体験記▼京大雑記:走ることの意味▼吉田寮祭ヒッチレース体験記:砂丘から左京を目指せ/ドライバー体験記→JAFを呼び、愛車が廃車に▼編集員座談会:私たちはどう生きるか→とにかく働きたくない▼41年ぶり全国へ:陸上部、全日本大学駅伝出場→18位の力走▼硬式野球部田中、猛虎2軍相手に熱投/田中、プロ入り▼ギャング1部残留▼熊野寮に家宅捜索:報道各社が寮前に大挙→寮が抗議声明 文化▼ドライブ紀行:琵琶湖一周▼京都乗合バス紀行▼映画評:『アナと雪の女王』→女性のアイコンとしての魔女とプリンセスの存在に新しい道を見出した▼知ってますか? 自助グループ▼晴耕雨眠:セブンイレブンの冷凍つけ麺がおいしい▼LGBTと学校:遠藤まめた氏▼ベランダーのすすめ▼こくばん:最後にちゃんと空を見たのはいつだろう→スマホに買い替えてから下を向く時間が長くなった▼京で涼む/恐で涼む▼対談:認識は旅をする▼著者に聞く:『世界一の紙芝居屋 ヤッサンの教え』▼インタビュー:シネ・ヌーヴォ支配人▼京都の紅葉をめぐる▼法学部有信会・秋季講演、平野啓一郎氏が講演 広告▼センターリサーチ:代々木41万7千人▼駿台・河合塾全面▼みずほ銀行▼BBQくに荘
目次
聞き取り⑨ 関わり方は人それぞれ 00年代後半〜10年代在籍者に聞く50団体の要望まとめ、建て替え実現
拾い読み⑯ 「京大雑記」やスポーツ多い 2014年の紙面
聞き取り⑨ 関わり方は人それぞれ 00年代後半〜10年代在籍者に聞く
00年代後半から10年代前半を知る4名への聞き取り取材の内容を掲載する。「関わり方が人それぞれ」との言葉どおり、関心や取り組み方が様々の各編集員を、京大新聞というひとつの団体につなぎとめたものは何だったのだろうか。(村)
心が折れても「京大新聞のファン」

如さん(08~13)、狭さん(12~18)(いずれもペンネーム)
=10月26日、京都大学東京オフィス
=10月26日、京都大学東京オフィス
自治への考え方様々
―入社のきっかけは。
如 予備校が受験生に配っていたDMに東大新聞が入っていた。京大新聞はどんな感じかなと気になって見学に行った。
狭 浪人時代、予備校に京大新聞が置いてあって、読んでいた。実は(如)さんの「こくばん」(編集員コラム)もきっかけのひとつ。編集部でいろいろな意見の人がいることによる揺れを描写していた。意見が割れるようなことも自由に書けるのはおもしろそうだなと興味を持った。
―実際入ってみて、印象は。
如 私は旧ボックスを知る最後の世代。壁に「NO NO 天皇」とか書いてあって、政治色の強い時代の名残りがおもしろかった。先輩がベロベロに酔いながらザ・タイマーズを大音量で流して歌っているのを見たときは、やばいところに来たなと思ったけど(苦笑)。
狭 本や漫画がたくさん置いてあるあの雰囲気は心地よかった。
―会議の雰囲気は。
狭 おおらかな側面もあるし、話題によってはピリピリすることもあった。
如 自由な雰囲気だった。先輩がビールを飲みながら、「〇〇くんのペンネームは麒麟の麒で決まりね」みたいな。一般的な大学サークルのノリを求めて見学に来る学生は、カオスな雰囲気が嫌だなとか、この長い会議はいつ終わるんだろうとか思っていただろうし、実際、数人入ったけどあまり定着しなかった。
狭 年によって波がある。学年で5人ほどいると多いほう。それより少ないとバタバタして、しばらくして増えて持ち直して、また減って誰かに負担が偏る、みたいなイメージ。
如 誰が何を書くか、だいたい得意分野があったし、継続的に追うネタもあるから、担当が固定されがちだった。特に学部自治会や寮生とつながりのある編集員が問題意識を持って発議して、記事化に至るという流れが多かった。僕はノンポリで、そういう取材に取り組む人たちから見れば、主体的ではないと思われていたかもしれない。ただ、自分個人がどう思うかはともかく、そういうネタを扱うことは使命だと考えていたし、プラットフォームとしてあっていいとは思っていた。
―「こくばん」で、自治にシンパシーを持てないと書いていた。
如 その感覚は一貫してある。たとえば吉田寮問題は、今も続いているけど、やっぱり僕は部外者だという意識。我々がどうこう言うことではないと思うし、草葉の陰から見守りたい。
―学生自治に対して様々な距離感や考え方の人が共存していた。
如 そうだね、受け皿は広かったと思う。
狭 バチバチの政治闘争をやる場ではないし。
如 少し上の世代は連絡用のメーリングリストで喧嘩するほどだったと聞く。白熱して、別の人が「続きは編会で」と仲裁に入るとか。僕がいたときは、そこまでこじれることはなくて、ある意味で人材不足だったと言えるかも。たとえば熊野寮関係のネタを持ってくる編集員に対して、誰も何も言わない。編集部のチェック体制という観点では、もう少し「当事者」がいたらよかったかな。
狭 学生自治に関する話題は、自分自身が積極的に取材に行くことはなかったけど、興味は持っていたし、多くの学生に読まれるかはともかく、報じる意義はあると考えていた。今の京大新聞でもそういう話題が扱われていて、現役の人も意識しているんだろうなと感じる。
心折れても憎しみない
―印象に残っている記事は。
如 大学構内の池を紹介する「キャンパスポンド」みたいに、言ってしまえば当たり障りのない記事ばかり書いて、先輩に「おまえは何がやりたいのかまったくわからん」と言われた。どちらかというと僕は、車で新聞を運んだり、営業の役職をやったりと、執筆以外のプロセスに携わることが多かった。印刷所のインクの香りが好きだったなと今でも思い出すし、そういうことを体験できてよかった。
狭 自分が手がけた特集を、発行後の会議で同級生にこてんぱんに批判されたことがあって、心に傷を負った。A4で5枚ほど配られて、両面にびっしりと、ここがだめだ、この言葉はどういうつもりで書いているのか、などと指摘された。ちょうど新歓の時期で、見学の新入生に見られないように会議前にその資料が配られて、自分だけ心が折れた状態。その日の会議ではほぼ話さず、終了後にみんなで行く食事にも加わらず、ひとりで帰って家で泣いた。それがトラウマになって1年ほど記事を書かなかった。しかも、放任の雰囲気だから、誰かが間に入ってくれたりフォローしてくれたりすることもなかった。
ただ、そのとき卒アル担当を務めていて、それは全うしなければという不思議な使命感があったから、その後も普段の会議には出席し続けた。今となっては、そういうことを経て文章が書けるようになったと思うし、その同級生のことを憎む気持ちはまったくない。最近は、職場のウェブサイトでコラムを書いたり、趣味の競技かるたの会誌に対談記事を載せたりしているから、当時の経験が活きている側面がある。
如 記事を書かなくなる時期は僕もあった。とある取材相手の方への配慮不足で、めちゃめちゃ怒られて謝罪記事を出した。それから半年くらい書かなかった。
「つかず離れず」自由
―営業の手応えは。
如 トラブルがあって予備校1社から出してもらえなくなったりしたけど、資金に困ることはそんなになかったと思う。
―アルバム担当に使命感。
狭 5つぐらいある役職を編集員で分担している。それぞれ時間がかかることをやっているし、それを誰かに投げるのは申し訳ない。主要な財源だからしっかりやらないと、という意識もあった。
―いろいろありつつ、やめずに在籍したのはどういう思いか。
如 つかず離れず、束縛されないし、所詮学生サークルだから、誰かがいなくなったら誰かが代わりをやる。それがむしろ戻りやすかった。体育会の部だと練習をサボると退部になりうるし、会社もそれに近い。京大新聞は良くも悪くも放任で、楽しかった。現役のみなさんも自由を謳歌してもらえればと思う。
狭 やっぱりボックスという空間が好きという気持ち。あとは、京大新聞に存在意義を感じていた。独自の視点でいろいろなネタが集まっていて、カオスな記事もある。浪人生のときから読んでいて、ある意味ずっと京大新聞のファンだから、心の中でいいなと思う気持ちがあるし、だからいろいろあっても関わり続けたんだと思う。〈了〉
ニュース番組の隣で漫才をするような両面性
山口駿さん(09~15)=11月9日、オンライン
真面目と不真面目の同居
―入社のきっかけは。
文章を書くのが好きで、作ったものが形になって残るという点で京大新聞に興味を持った。1回生の春から存在を知っていたけど、新歓の宣伝文の下に小さい字で、新入生が多すぎると面倒を見切れないと書いてあって、躊躇した。それで2回生の年に入った。冷淡な空気を予想していたら、思ったより面倒見がよかった。先に入った同回生から、人によって関わり方が全然違うから自分でネタを探すことが大事だよと言われていて、まさにその通りだった。
―山口さんは書評に力を入れた。
自分はノンポリだからそれくらいしか発露できないという気持ちがあって、書評を通して風刺を楽しんだ。たとえば当時の松本紘総長の著書を少し意地悪な視点で評すとか。ツイッターができたばかりのころで、記事を読んだ方が感想を投稿してくれていて、それを見るのが楽しみだった。批判的なコメントも、おもしろいと言ってくれることもあって、そういう反応をすぐに知れるのが新鮮な体験だった。
―編集部の雰囲気は。
「ここぞ」の集中力がすさまじいという印象。いつも作業がギリギリで、入稿日の朝3時、4時の土壇場になると、いい意味で「どうしてこのクオリティのものが」と驚く成果物ができあがる。そういう能力に長けている人が多かったんだろう。
―特集の検討や原稿の校正では厳しい指摘が飛ぶという声も。
それはお互い様。自分で気づけないことを言ってもらえるのはありがたいし、やめてほしいなと思ったことはない。
―編集方針に関して、ミニコミ的でもマスコミ的でもあったという話がある。
たしかに両面あった。付け加えると、真面目と不真面目がいいバランスで同居する数少ない媒体だと思う。真面目な顔をしてニュースを読むキャスターの隣で漫才をやるような。それは一般紙にはない特長。逆に不真面目に振り切る媒体は他にあったとしても、そこに学内情勢の真面目な解説が共存するのは珍しいし、それが魅力だと思う。
懐の深い団体で気楽に
構成員としては、ずっといなきゃいけないわけではないという気楽さも感じていた。久しぶりに顔を出しても、「この記事書く?」と言って受け入れてくれる。懐の深い団体だと思う。
―印象的な記事は。
灘高校教員(当時)の前川直哉さんへのインタビュー。ジェンダー研究者として、学校でジェンダー学の授業を実施するなど興味深い取り組みをされていると先輩経由で知って、話を聞いた。掲載後、大学のLGBTQ支援サークルの代表さんから、発信してくれてありがたいというお言葉をいただき、励みになった。
記事ではないが、入試のカンニング事件も印象的。当時、一緒にボックスにいた(春)が問題文の流出に気づいて、京大新聞のツイッターで指摘した(前回の連載参照)。その時点では受験生によるカンニングだとは分からず、トラブルとか内部告発的な流出とか、様々な推測が成り立つ。何があったのかと投げかける意図でツイートしたところ、賛否両論の反応があった。投稿しなければ騒ぎにならず逮捕者が出なかったのではないかとか、逆によくやったという声も。その件をきっかけに京大新聞を知った方もいるだろうし、いろいろな意味で影響があった。
あとは円城塔さんの講演会。芥川賞をとられた直後だった。かねがね好きな作家さんで、ダメ元でお願いしたところ快く引き受けてくださった。もう少しお客さんに来てほしかったが、講演自体は申し分なかった。
―現役編集部に一言。
百周年に向け、真面目な企画以外におふざけ要素もあっていいと思う。働いていると、学生時代ほどはっちゃけられない。今のうちに、めいっぱい取材・執筆・議論を経験してほしい。〈了〉
目次へ戻る
50団体の要望まとめ、建て替え実現
前回掲載した中川崇さん(06〜11)への聞き取り取材記事のうち、現ボックス棟建設に至る経緯に関する内容を以下に掲載する。(村)
学生も参画した建物設計
京大新聞に入ったころはボックス棟が木造で、脆弱性に危機感があった。しかもボックスの床には灯油がしみ込んでいる。当時はエアコンがなく、学生部から支給される灯油を取りに行ってストーブを使っていた。何かあったらどうしようという不安を抱えるなか、06~07年にかけて大学でボックス棟の建て替えに予算がつく状況になった。職員からもこの機会を逃すと次があるか分からないと聞いていたから、危機感もあいまって、力を入れて動いた。B連という50団体からなる組織があり、その時期にちょうど持ち回りの幹事が京大新聞に回ってきて、私が担当になった。
たくさんの団体の意見をまとめるのは大変で、そもそも建て替えるということの合意に労力がかかった。合意後も、建物の設計や各団体のボックスの配置など、いろいろと検討事項があり、ワーキンググループを立ち上げて議論した。そこで原案を作って、総会に示して合意を取りつけた。たとえば、移転でスペースが減る団体には共用の倉庫を割り振ることにしたが、山岳部からは命に関わる備品が含まれるため他団体の荷物と一緒に置くのは避けたいという要望が出て、それならこっちのスペースを使ってもらおうとか。あとは、階段を一部逆向きに設計すれば階段下を有効活用でき、写真部の暗室として使えるなとか。音楽系団体のための音出し共用室について、広い部屋も必要だと後から分かったから、頼んで設計を変えてもらった場面もあった。もめることも一部であったが、個別の相談にはできる限り対応したつもり。
自治に妥協してはいけない
一段落して別団体が幹事になった後も、担当として会議に出て状況を注視し続けた。A・B棟ができて京大新聞も含めた該当団体が移転し、それらが入っていた旧ボックス棟をつぶして、C~E棟を建てることで、全団体が移ることができた。全棟ができ移転完了したタイミングで、また京大新聞に幹事が回ってきた。「運命やな」と思いながら、私自身2回目の担当になった。このとき問題になったのは、共用の会議室ができたのに活用できていなかったこと。だから規約を定めて使えるようにした。その流れで、B連じたいの新しい規約も作成し、名も変えた。B連には吉田南の学生集会所の団体も含まれていたが、その後建て直した学生集会所に残った団体もあれば、西部に移ってきた団体もあった。いま稲盛財団記念館が建っている場所(当時アジア・アフリカ研と呼称)から西部へ移転してきた団体もあった。改めて、西部構内の新ボックス棟の関係団体の集まりだと明示したほうがいいという議論があって、現在の「西部課外活動施設使用団体連絡協議会」、通称・西団連という名前に変えた。
振り返ると、無事に建て替えできてよかった。エアコンが完備され、火災のリスクが激減し、トイレなどの衛生面も大幅に改善された。当時の尾池和夫総長と学生担当の東山紘久副学長は学生に対して比較的優しく、この2人の体制のもと枠組みを決められたことも大きかった。印象的なのは、建物の24時間開放をめぐる議論での尾池さんの言葉。「23時間59分は開放して1分間だけ閉めるのはどうか、という提案があったとしても乗ってはいけないよ」と。自治や自由に対して妥協してはいけないという趣旨。1分が2分に、2分が2時間になり、そのうち完全に閉められてしまうぞと。これは入学アルバムか何かの総長インタビューで改めて聞いた言葉だったように思うが、歴代総長のなかでも学生自治について深く考えてくれていたのが尾池総長だった。学生の自主的な動きはもちろんあったけど、そういった様々な背景のもと、ハード・ソフト両面で学生にとって課外活動しやすいボックス棟ができあがったことは喜ばしかった。〈了〉
目次へ戻る
拾い読み⑯ 「京大雑記」やスポーツ多い 2014年の紙面
2014
新聞社▼京大新聞主催・円城塔氏講演会▼第3回文学賞開催→吉村萬壱氏インタビュー:初めて食べる「味」の作品を 時事▼原理研に注意▼複眼時評:「あの戦争」に関わる3点の史料/貨幣の価値を変えよ▼書評:『近代日本の国家権力と天皇制』▼公開講座:マスメディアが作るアフリカ像▼就職先一覧▼シンポ:北朝鮮の人々▼トークライブ:震災映像の想像力 教育研究▼二次試験までに読んでおきたい本:『ぼんやりの時間』『不安の概念』▼アイヌ遺骨「追求する会」再度抗議:話し合いに至らず▼文、セメスター制へ▼▼英語による教養科目が開始▼元岐阜大学教授・寺島氏→「英語で授業」が何をもたらすか▼国際連携学位プログラム創設へ▼新1回生にTOEFL試験▼附属図書館に新エリア:ラーニング・コモンズ▼附属図書館、盗難相次ぐ▼国際人材総合教育棟、埋文調査▼総博特別展:研究者と作る京料理▼関東大震災フィルム、京大書庫で確認▼フィードバック期間導入▼書評:『「サル」化する人間社会』▼春秋講義:生命と老化 大学運営▼自転車シェア実験導入→利用者の声受け増台▼京大雑記:学生不在の「民主主義」▼学域・学系制、臨時評議会で可決▼学務部棟に防カメ:金庫周辺を管理徹底▼総長選、意向投票が「意向調査」に▼書評:松本紘総長『京都から大学を変える』→エンターテイナーとしての才能を証明▼京大ジャパンゲートウェイ構想、文科省に申請▼新総長に山極氏→単独インタビュー:「権限集中より合意形成を」▼「山極氏に投票しないで」:学生有志が貼紙「研究者として不可欠」▼企業への学術指導、公務で実施可に▼京大あれこれ:吉田南図書館裏の黒ねこ/総人棟の扉/京大理容室▼出席登録を電子化へ▼吉田南グラウンドに照明設置▼学内で私服警官見つかる:総長「毅然とした態度で臨む」▼11月祭、教員酒場が教員甘酒に:総長が自粛要請▼学生集会所建替え大幅な遅れ:震災で人材・機材不足▼京大、携帯3社のワイファイを導入▼吉田南中庭を整備:木を切り日当たり良く▼入試検定料、コンビニ支払い可に▼障害学生支援ルームに聞く:学びやすい京大へ 学生▼寮紹介▼農家と料亭をつなぐ:京大生の野菜卸売▼1コマでキャンパスを飛び出そう▼ドイツ留学体験記▼京大雑記:走ることの意味▼吉田寮祭ヒッチレース体験記:砂丘から左京を目指せ/ドライバー体験記→JAFを呼び、愛車が廃車に▼編集員座談会:私たちはどう生きるか→とにかく働きたくない▼41年ぶり全国へ:陸上部、全日本大学駅伝出場→18位の力走▼硬式野球部田中、猛虎2軍相手に熱投/田中、プロ入り▼ギャング1部残留▼熊野寮に家宅捜索:報道各社が寮前に大挙→寮が抗議声明 文化▼ドライブ紀行:琵琶湖一周▼京都乗合バス紀行▼映画評:『アナと雪の女王』→女性のアイコンとしての魔女とプリンセスの存在に新しい道を見出した▼知ってますか? 自助グループ▼晴耕雨眠:セブンイレブンの冷凍つけ麺がおいしい▼LGBTと学校:遠藤まめた氏▼ベランダーのすすめ▼こくばん:最後にちゃんと空を見たのはいつだろう→スマホに買い替えてから下を向く時間が長くなった▼京で涼む/恐で涼む▼対談:認識は旅をする▼著者に聞く:『世界一の紙芝居屋 ヤッサンの教え』▼インタビュー:シネ・ヌーヴォ支配人▼京都の紅葉をめぐる▼法学部有信会・秋季講演、平野啓一郎氏が講演 広告▼センターリサーチ:代々木41万7千人▼駿台・河合塾全面▼みずほ銀行▼BBQくに荘