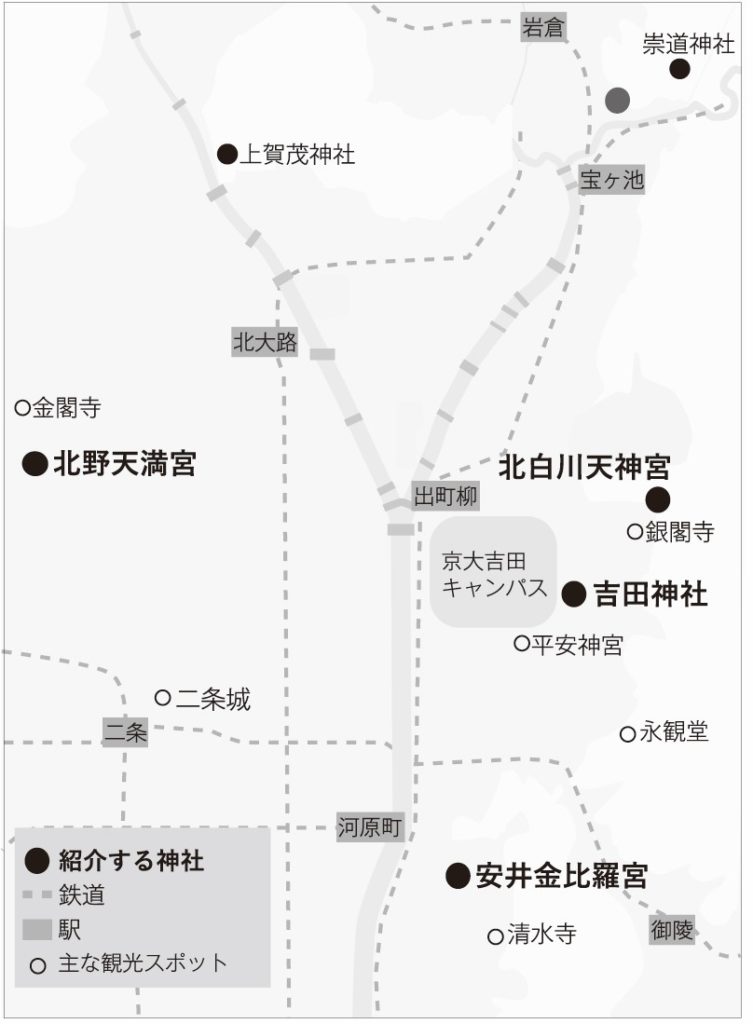前川直哉 灘中学校・高等学校教諭 「日本社会と「男の絆」」
2013.05.01
一昔前に比べ、同性愛への関心は少しずつ高まっているのかもしれない。ボーイズ・ラブを扱う書店は珍しくなく、テレビや雑誌では特集も組まれている。「日本も、大昔は同性愛が盛んだった」ということを耳にした人は多いだろう。 だが、「あなたの周りに同性愛者はいるか」と聞かれると、途端に歯切れが悪くなる人が多いのも確かだ。異性愛でないものは過去や虚構の中に閉ざされ、今・ここのテーマとしてはなかなか語られない。こうした在り方に疑問を呈しているのが、ジェンダー・セクシュアリティ研究者、前川直哉氏である。高校でジェンダーをテーマとした先進的な取り組みも展開している氏に、日本における「男の絆」と、それにが周縁化してきた多様な性について、お話をうかがった。(薮・湘)
まえかわ・なおや(灘中学校・高等学校教諭 ジェンダー・セクシュアリティ研究者)
1977年兵庫県生まれ。東京大学を卒業後、一般企業勤務を経て2005年に京都大学大学院人間・環境学研究科修士課程に入学。2012年に同研究科博士後期課程を単位取得退学。灘中学校・高等学校非常勤講師を経て、2007年より同中・高教諭(日本史)。専門はジェンダー・セクシュアリティの社会史。著書に『男の絆 ―― 明治の学生からボーイズ・ラブまで』(筑摩書房)、共著に『セクシュアルマイノリティをめぐる学校教育と支援』(開成出版)など。
学部段階では、ジェンダーやセクシュアリティの研究はしていなかったのですが、学部を出た後に働いていた企業を辞めてから、このテーマについて研究してみたいと思うようになりました。元々歴史が好きだったこともあって、ジェンダー史に関する本を色々と読んだのです。
よく言われることですが、ジェンダーやセクシュアリティなど、現在の日本社会に存在している規範を相対化するには、場所や時代をずらしてみる方法が有効です。つまり諸外国ではどうなっているかという「比較」の手法と、他の時代はどうだったかという「歴史」の手法ですね。僕は外国語が苦手なので、「歴史」を選んだとも言えます。もっとも、こんな理屈は後から気が付いたんですが。歴史が好きで、ラッキーでした(笑)。
その後、人環の小山静子研究室に入ったのですが、それも京大を選んだというよりは、本を色々と読む中で小山先生の著作にあたり、目を開かれる思いがしたのですね。自分にとって大変分かりやすかっただけでなく、内容も興奮するものだったのです。「ああ、自分の知りたかった事が、ここに書かれている」と。小山先生は「良妻賢母」という規範について、主に研究されていました。女性のジェンダーが近代に入り、日本の教育の中でどのように構築されていったか、ということです。
そこで、同じように、自分が関心のあるセクシュアリティの問題についても、「なぜセクシュアル・マイノリティ、特に同性愛が排除されていったのか」ということを考えたいと思ったのです。自分の知識として、森鴎外の『ヰタ・セクスアリス』に描かれるような学生男色(明治時代のエリート男子学生などに見られた男色)のことなどがすでに頭にありましたが、そういうものがなぜ無くなっていったのか。そういったことを「歴史」として調べる。その「歴史」を調べることで、現在の社会の問題、自分たちセクシュアル・マイノリティが感じている生きづらさ、そういうのを解きほぐせるんじゃないか。それで近代史をやることにしたのです。
―江戸・明治期、あるいは戦国期においては同性愛に対する観方が寛容だった、という俗説が存在します。そのような俗説が伝えられてきた背景には何があるのでしょうか。
現在でも「江戸・明治期は男色に対して寛容だった」と言われていますが、実際に史料を調べていったところ、あまり寛容とは言えない状況でした。例えば明治期に入ってすぐに、改定律例と呼ばれる明治初期の刑法典によって「鶏姦(けいかん)」、すなわちアナル・セックスが懲役刑の対象となっています。このように、明治の知識人の間には男色を禁止しようとする価値観が存在しました。ならば、江戸時代には寛容だったかというとそうでもない。確かに、男色が流行していた時期はあります。それでも、あまり誇れるものじゃないよね、という観方のほうが、江戸時代を通じて強かったと言えます。
そんな中で常に語られてきたのが「男色は、昔は盛んだった」という物言いです。現在でもそうですし、明治時代には「江戸時代はさかんだった」と言われ、江戸時代には「戦国時代はさかんだった」とされた。要するに、常に「過去」のものとして語られてきた。それは同性愛というセクシュアリティを「過去」のものとして追いやってしまう、周縁化していくということです。近代において、「過去」のものはすなわち野蛮なもの、後れたものとみなされます。「過去」への周縁化を進めることによって、逆に現在のセクシュアリティが見えづらくなってしまう効果もあったのではと考えています。
―例えば戦国時代の男色の実態はどんなものだったのでしょうか。
正直、分かりづらいところが多いですね。戦場では男性の方が圧倒的に多いですから、そうした行為はわりと日常的に存在していたのかもしれません。ただ、現在のように「同性愛/異性愛」という分け方は存在しません。男色と女色(男性による異性愛)は両立するものだと考えられていました。極端に言えば、「今日はパンを食べよう、次の日はパンに飽きたからご飯を食べよう」というような感覚で、近世には男色と女色が語られていたりもします。
例えば、織田信長が同性愛者あるいは両性愛者だったという言い方をする人がいます。しかしそれはあまり意味のないことです。当時は男性とセックスするか、女性とセックスするかというのはあくまで行為の話であって、それがその人のアイデンティティを形成するという観方がそもそも存在していませんでした。歴史的に見ると、現代人が「男性とセックスする男性は同性愛者だ」というふうに思うことの方が、奇妙であるとも言えます。
―今のお話で、ミシェル・フーコー(1926―1984)が指摘しているように、近代以降「狂気」の概念が確立したことでいわゆる「精神病」が誕生したということを想起します。
そうですね、フーコーの議論は非常に参考になります。ただ、近代科学との関連で考えるなら、異なる点が一つあります。同性愛が性科学によって、「変態性欲」として周縁化されていったのは、日本では大正期になってからです。しかしそれ以前の明治期においても、すでに男色を周縁化する動きがありました。
先ほどお話した通り、まず明治時代になった直後に、大人の社会から男色は排除されていきます。そして、一部の男子学生の間で流行していた男色も、次第にダメだとされるようになりました。
第一に肉体的な関係が排除されました。学生男色というものが明治期に流行りましたが、これは一部の男子学生の間で、「お互いの成長」が期待できる関係としてイメージされていたもので、肉体的な接触を伴うケースも少なくありませんでした。女子学生に対する高度な教育が整備されていない時代、「智力の交換」や「大志の養成」は男子学生同士だからできるのだ、という考え方の延長線上に、学生男色があったのです。ところが、この学生男色について、肉体的な接触を伴うものはいけないという観方が1900年前後に出てきます。
そして1900年代に入ると、高等女学校が全国に整備されることで、教育を受けた女性が男子学生の前に登場します。この時期、男子学生が共有する大きなテーマとして浮上してきたのが「女学生との恋愛」や、そこから結び付く「結婚」です。この頃から、男子学生同士の親密な関係を表現する語としての「男色」や「男同士の恋」といった言葉が、力を失っていきます。それに代わって主流となったのが「友情」「朋友」といった言葉でした。特に「朋友」という言い方がよくなされています。この言葉を使うことで、男性同士の親密な関係を「異性愛」と両立できるものにした。女性との結婚、恋愛などと両立できるように、男子学生同士の関係の表現の仕方が変わっていったのです。
ですから単純に「科学」、日本の場合は大正時代における「性欲学」ですが、それがすべて悪いと言ってしまうのは、ちょっと違うんじゃないかと考えています。それ以前からすでに、男性同士の性的な接触は禁止され、排除されていたのです。
―著書にもお話がありましたが、明治時代においては男色が「上下関係に基づく関係」であったという観方があります。現代には「同性愛者は異性愛者をなりふり構わず狙っている」という偏見が広がっていますが、これは明治時代からの流れによるものといえるのでしょうか。
うーん……それらは別々のことではないでしょうか。明治時代の学生男色においては、年上が能動側、年下が受動側という年齢の上下関係があり、確かに明治時代の新聞なんかを見ますと、「不良学生による美少年狩り」があった、などと報じる記事があります。
ただ現代について言えば、「同性愛」というのはセクシュアリティにのみ注目した言い方であるというのが重要です。一人ひとりの同性愛者には当然、好きなタイプの人がいますね。であるにもかかわらず、同性愛者は同性であれば誰でも好きになるというようなイメージが、この言葉には貼りついてしまっているようにも感じます。
またセクシュアリティを非常に強調した言い方なので、その人がまるで24時間セックスのことばかり考えているかのように誤解されてしまう側面があります。でも、ヘテロの人を「異性愛者」だと言う時、ずっとその人が異性のことばかり考えているようには思いませんよね。同性愛者だって同じです。「生きづらい」、「自分はマイノリティである」ということを考えることはあるかもしれませんが、ずっと同性のことばかり思っているわけではない。当たり前のことですが、「腹が減ったな」だとか、「単位足りないな、どうしよう」、「明日1限出られるかな」といったことを考えている。それなのに、セクシュアリティを強調する言い方であるために誤った観方が広がってしまうのです。
また、「同性愛者が異性愛者を狙う」などという言い方がなされる場合に、念頭に置かれているのは男性だと思います。つまり、男性の同性愛者が男性の異性愛者を襲う、と。女性についてはあまりそういうふうに考えられていない。この背景には、男性には「性において能動であれ」というメッセージが働いているという、ジェンダーの規範があるでしょう。「草食系男子」という言い方が特別な意味を持つのは、男性は「肉食」であるのが当たり前だというふうに思われているからです。
ですから、「性に能動的である」男性が同性愛者であると分かった時、周りにいる男性を能動的に「狙う」のではないかと感じてしまう。それが男性の異性愛者にとっては一つの脅威と感じられてしまうわけです。自分は性において能動的であるはずなのに、同性愛者を前にすると、自分が受動側になってしまうのではないか、と。男性にとって、自分が誰かの性欲の対象になっているということは想像しにくいのです。だから、目の前の相手に男性同性愛者だとカミングアウトされると、思わずビクッと緊張してしまう。別に、君のことを狙ってるよと言われたわけでもないのに、ついつい身構えてしまう。「ノンケの自惚れ」なんて言われたりもしますけどね(笑)。
―女性同士の恋愛の例は、どれくらい記録されているのでしょうか。
明治期について言えば、全くないわけではないのですが、史料として残っているケースは少ないですね。
巌谷小波(1870―1933)という、明治時代に活躍した童話作家がいます。1900年から1902年まで、彼はドイツへ洋行に行きました。マグヌス・ヒルシュフェルト(1868―1935)というドイツの有名な性科学者によって、男性同性愛者の団体が立ち上げられたのとちょうど同じ時期でした。その会合に小波も呼ばれ、日本の男色について色々話してほしいと要請されました。帰国後、彼は『小波洋行土産』という本を著し、その中でヒルシュフェルトたちの団体についても触れています。この本で小波は「男子と男子との交接」を「男色」と表現しているのに対し、「女子と女子との交接」については「日本にはその事ありて、いまだその名無きがごとし」と記しています。
現在で言うレズビアン、つまり女性同士の同性愛は、当時「あることはある」と思われてはいたのでしょうが、まだはっきりとそれを指し示す言葉がなかった。「同性愛」が言葉として出てくるのは大正期に入ってからで、それ以降は女学生による同性愛なども頻繁に報じられるようになります。
そうですね。例えば欧米では、政治家はもちろん、学者や映画俳優、ミュージシャン、スポーツ選手など、同性愛者であることをカミングアウトしている人は大勢います。それに対し日本ではカミングアウトしている人が非常に少ない。これは明らかに、日本において同性愛解放が遅れている、つまりカミングアウトによる不利益が恐れられているということです。もちろん、研究やゲイ解放運動などを通じて自らが同性愛者であることをカミングアウトしている人はたくさんいますし、政治家でも地方議会では徐々に増えつつあります。それでも、まだまだ少ないと言わざるを得ません。
パトリック・リネハンさんというアメリカ総領事が大阪にいらっしゃいますが、彼はゲイであることを公表しています。カナダで同性パートナーと結婚式を挙げ、二人で日本に来られています。そのリネハンさんが、今の日本の状況はちょうど30年前のアメリカと同じだと仰っていました。つまり、映画にもなった有名なハーヴェイ・ミルク(1930―1978)ら地方政治家が出てきた段階であると。アメリカはその後、多くの紆余曲折を経て、自らの同性愛をカミングアウトする国会議員も出てくるようになりましたし、またオバマ大統領、クリントン元国務長官らも、同性愛に対する差別を無くすことがアメリカにとって非常に大きな課題であると明言しています。
日本だって30年ほど遅れてはいるけれども、そのステップを踏んでいることは間違いありません。ただ欧米諸国に比して、なぜこれほど遅れてしまっているのか。僕自身の見立てとしては、日本ではジェンダー差別の解消が遅れているということが、深く関係しています。男性のホモ・ソーシャルな結び付き、「男の絆」によって社会を独占したいという欲望が、日本にはまだまだ根強いわけです。こうしたホモ・ソーシャルな社会において男性同性愛者は、そこから弾き出されないように、自らのセクシュアリティを隠し続けようとします。自分が男性同性愛者であると言った瞬間に、所属しているホモ・ソーシャル社会から排除されてしまう。「俺たちは性を支配する側の立場であるはずだ。それなのに、お前は何なのだ」と。
日本は女性の社会進出が非常に遅れている国です。つい最近、女性の国会議員比率(衆議院)はわずか7・9%で、これは190カ国中160位台であると報じられました。つまり、いわゆる先進国の中だけでなく、世界全体で見ても最低レベルに位置しているのです。企業にしても、管理職の女性が非常に少ないことはご存知の通りです。このように、女性の進出を阻みながら、男性だけで社会を動かそうという欲望がこの国には根強く残っている。これこそが、多くの男性同性愛者がカミングアウトできずにいる最も大きな原因であると考えています。
一部のタレントさんのように、カミングアウトをした上で、かえってそれを「持ちネタ」にしている人たちについては、個々人によって考え方が分かれるでしょう。はっきり言えるのは、そういう光景を喜ぶ視聴者、テレビ局が存在しているということです。むしろメディアとしては、分かりやすい形のゲイの方が安心できるのだと思います。ゲイとはこのような人であるという偏ったステレオタイプを作り、それに沿った振り付けをさせている部分もあるでしょう。現実社会でゲイやレズビアンが息苦しい思いをしている、という社会問題に焦点を当てたとしても、視聴率がとれない。それよりは「ゲイのタレントがイケメン俳優に色目を使う」といった構図の方が、テレビ的には笑いの対象として成立しやすいということなのでしょう。
同じことはテレビ番組に限ったことではなく、普段の日常生活についても言えますよね。京大生でも普段の会話の中で、セクシュアル・マイノリティの人権について真剣に議論する場面とか、ほとんどないでしょう。それに比べれば、「ゲイ」や「ホモ」といった言葉を使って、笑いをとりにいこうとする場面の方が圧倒的に多いはず。残念ながら現在の日本では、こうした人権感覚のなさが一般的なものとなっています。メディアの責任も大きいでしょうが、それを受け入れている視聴者にも責任はあると思います。
そんな中、NHKの「ハートをつなごう」は、セクシュアル・マイノリティをめぐる差別や生きづらさに真摯に向き合っている、数少ない良心的な番組です。また、同じNHKの「障がい者情報バラエティー・バリバラ」では、障がいを持つ性的マイノリティが取り上げられる回もあります。民放でも同性婚などの話題を扱うドキュメンタリーが、少しずつ増えてきました。それでもやはり、同性愛が笑い・からかいの対象とされている番組のほうが圧倒的に多いというのが現状です。
ところで、「オネエ」タレントやゲイキャラを売りにしているタレントさんはたくさんいらっしゃると思いますが、レズビアンについては全くいないものとされているのではないでしょうか。テレビを見ていると、そのことに疑問を覚えることがあります。男性同性愛者より女性同性愛者のほうが息苦しさを感じているはずだ、というのが僕の考えです。
世界的には、レズビアンをカミングアウトしている女優さんやアーティストがたくさんいます。またThe L Word(邦題:『Lの世界』)というレズビアンやバイセクシュアルの女性たちを描いたテレビドラマなどもある。ただ、欧米諸国においてもレズビアンよりゲイのほうが目立っているというのも確かで、既存のジェンダー力学を反映しているように思います。
「ボーイズ・ラブ」が広がり始めたのは1990年代です。それ以前、男性同士の恋愛を描いたマンガ・小説は「やおい」や「耽美」と呼ばれていました。商業誌でこれらの作品を専門的に扱っていたのは『JUNE』という雑誌で、書店でも隅の方に置いてあって、いわば日陰の存在だったと言えます。同人誌の世界では、アニパロを中心にたくさんの作品が描かれていましたが。それが90年代に入り、一気に何冊もの商業誌が出版されるようになり、マーケットを広げていきました。今はそれが「定着」している時代にあたると思っています。
その背景にはいくつかありますが、一つには「女性が男性を見る」という構図が、以前に比べ一般的になってきたことが挙げられます。昔も今も、「男性が(性的な対象として)女性を見る」というのが基本的な構図であることに変わりはありませんが、「見られる男性、見る女性」という構図も少しずつ市民権を得てきました。ボーイズ・ラブに限らず、「ジャニーズ」や「韓流」についても、同様のことが言えるでしょう。例えば芸能雑誌『Myojo』の表紙に登場する被写体を時代ごとに分析すると、50年代の創刊当初は女性スター単体だったのが、70年代・80年代に「女性と男性の組合せ」に変化し、90年代半ばに「男性アイドルばかり」の表紙へと移行していきます。
また元々、文学やマンガの中で「男の絆」を称揚する空気があったわけです。『週刊少年ジャンプ』が「友情・努力・勝利」を旗印に掲げたように、男同士の友情を主題とする作品は、映画でも、テレビドラマでも、文学やマンガでも、それこそ星の数ほど描かれてきました。そしてマンガについて言えば、戦後に少年漫画/少女漫画と分化していった時に、少女漫画は「恋愛」を一つのメインテーマとして描くようになったという歴史的経緯があります。少年漫画の中では恋愛は取るに足らないもの、あくまで味付けにすぎないものとされたのに対し、少女漫画ではメインとされた。それは近代における性別役割分業観によって、「男性は社会に生きよ」、「女性は家庭のことをやれ」と唱えられたことと、深く関わっています。「恋」や「愛」は、女性化された概念として捉えられてきた経緯があるわけです。
そして、恋愛を描く少女漫画の伝統と、男の絆を称揚する少年漫画の伝統が結び合わさる中で出来てきたのが「ボーイズ・ラブ」作品であると僕は考えています。男の絆は、実際に当事者として巻き込まれるのは色々と大変そうだが、鑑賞者として外から見ている分には楽しい。「男の絆」から弾き出された女性たちが、「男の絆を鑑賞する」という戦略を編み出した。さらに、少女漫画は恋愛を描くのに長けている。ならば、こいつらを恋愛させてみるのはどうだ、ということで出来上がってきたのがボーイズ・ラブだと言えます。
ですから僕は、ボーイズ・ラブはある意味ではジェンダー規範の必然的な帰結の一つ、流行るべくして流行ったものだと思っています。当初は様々な抑圧の中で、あまり目立たないようになされてきたものが、90年代以降になってどんどん広がっていったわけです。ボーイズ・ラブは流行るべくして流行ったのに、男性がそのことで騒ぎ出しているだけなのかもしれません(笑)。
―ステレオタイプ的な観方ですが、ボーイズ・ラブを愛好する女性は「腐女子」と呼ばれ、例えば鉛筆と消しゴムなど、何でもカップルにしてしまうということがある種のネタとして言われることがあります。
まず「腐女子」という呼称について、自称なのか他称なのかという問題があります。自称として使う場合はともかく、他称としてこの呼称が持ちだされる場合には、やはり差別的なニュアンスがつきまとっているのではないかと僕は思います。
他称として名指される際、なぜボーイズ・ラブを愛読する女性たちが「腐女子」と呼ばれ、かつその行動が批判の対象となりがちなのか。批判されるリスクを察知しているので、ボーイズ・ラブを好む女性読者たちは自らのことを予め「腐女子」と自嘲しておき、「私たちは腐っているのです、放っておいてください」とバリアを張っておかなければならないというケースもあるように感じます。
ヘテロの男性が女性に対して性的な欲望を抱いている時に、そんなバリアを張っているでしょうか。2ちゃんねるやTwitterなどでも「ホモォ…」と囁くAA(アスキーアート)が流行ったことがあります。こんなふうに「腐女子」と呼ばれる女性たちは自嘲しなければならない。一方ヘテロ男性は、夜な夜な1時間も2時間もエロ動画を必死になって探していても、「エロォ…」と自嘲したりしませんよね。そういう非対称さにはやはり問題があると思います。なぜボーイズ・ラブが好きな女性たちは予め自分を貶めなければならないのか。なぜヘテロ男性は、夜な夜な動画を探す自らの滑稽さを笑わず、彼女たちだけを嘲笑するのか。この点を考えるべきではないでしょうか。
―一般的に、異性愛者男性が好んで読むものは「オタク文化」の中心に位置づけられ、それを専門とする批評家も現れています。これに対し、ボーイズ・ラブの批評をめぐる状況はどうなのでしょうか。
ボーイズ・ラブにも専門の批評家はいます。また三浦しをんさんのように、積極的にボーイズ・ラブについて発信している方も、ジェンダー研究者に限らずたくさんいらっしゃいます。
ただ、ボーイズ・ラブを読むという行為自体について、研究者たちが色々と語ろうとすると、ファンからは抵抗や批判がある場合も少なくありません。自分たちが楽しんで読んでいるものを、外部からあれこれ言わないでほしい、という気持ちはよく分かる。この辺りは、なかなか難しい所です。
ちなみに僕は、「なぜボーイズ・ラブを読むのか」といった問いの立て方はしません。むしろ問われるべきは、「なぜポーイズ・ラブを読むという行為が、これほど言挙げされるのか」だと考えています。
余談ですが、昨年末に雑誌『ユリイカ』でボーイズ・ラブの特集をした時、普段よりかなり売れ行きが良かったそうです(笑)。ですから、ボーイズ・ラブに対する評論はそれなりに求められているとも言えます。
―ボーイズ・ラブは然るべくして流行するようになったということですが、ガールズ・ラブ、いわゆる「百合」についてはどうなのでしょうか。
ガールズ・ラブ作品については僕自身あまり詳しくないので、答えるのは難しいですね。ただ一つ言えるのは、これまで女性同士の性愛は、基本的にヘテロ男性のためのポルノグラフィー、つまりアダルトビデオなどの中で扱われるケースがほとんどだった。それがいわゆる「百合」作品として漫画の中に取り入れられると、女性の読者も増えてきているという現象があります。依然、男性が性的消費の対象としている部分があるのも、間違いないのですが。これから注目していきたいところです。
―前川さんは勤務先の灘高校で、ジェンダー学を中心に取り扱う講座を開いているということですが、そこではどのような授業をされているのでしょうか。
これは「社会講座」という科目名で、高3の文系クラスの全生徒を対象に行なっています。この講座は週2回、大学入試とは全く関係のないことをやろうという趣旨で行われているものです。僕が担当しているのは「ジェンダー/セクシュアリティ」で、最初の2回でジェンダー/セクシュアリティに関する概論を説明し、その上で生徒たちに自由発表をしてもらいます。1コマ50分という時間的な制限もありますので、1回につき2名に、15分発表・10分質疑応答をやってもらう。そういうかたちで、ミニ・ゼミのようなことをやっています。生徒たちはかなり乗ってくれて、こちらから細かいことを説明しなくても、自ら色々な本を読み、主体的に発表してくれますね。
ジェンダーと就労に関する問題や、インドにおける女性差別問題など、かなり堅いテーマを扱う発表もありますし、あるいはサブカルチャーに関するものもあります。昨年は「男の娘」文化について発表してくれた生徒もいました。非常に面白い発表ばかりですし、僕自身刺激を受けています。また、生徒たちに聞いても楽しんでやってくれているみたいですね。受験生の6月、7月というのは忙しい時期だとは思うのですが、彼らは一生懸命準備をしてくれます。
―そのような授業をやろうと思うようになったきっかけは。
元々「社会講座」という、入試と関係のないものをやろう、という趣旨の時間が作られた時、僕は高校教員であると同時に、ジェンダー/セクシュアリティの研究者ですから、このテーマでやってみようと考えたわけです。最初の1年間は講義形式で行っていたのですが、やっているうちにむしろ生徒の発表が聞きたいと思うようになり、2年目からゼミの形式にしたところ予想以上にうまく行った。それで、今年も同じかたちで続けることにしました。
また、ジェンダーやセクシュアリティというのは身近なテーマであり、考えれば考えるほど社会とつながっていく問題です。僕が勤める学校は男子校ですので、このテーマについて全く知らないまま大学に進学していくと、自分が「男性」であるということによってどのような位置にあるのかに無自覚なまま社会に入ってしまう危険性があります。男子校の生徒にこそ、ジェンダーについての授業が必要だというのが、僕の実感です。
また中学校や高校では、同性愛差別の問題について、ほとんど語られないという現状があります。同性愛差別というのは、あらゆる種類の差別の中でも、最も日常的に起こっている差別の一つです。例えば、あからさまな部落差別や障がい者に対する差別の発言を、同級生や教員から聞くことは、今の高校生はあまりないはずです。でも同性愛差別となると、「お前ホモかよ、気持ち悪い」、「そんなにナヨナヨして、お前はオカマか」などと生徒も言うし、教員でさえ言ってしまう現実がある。クラスの中にはそれを聞いて、息苦しさを感じている生徒がいるのに。
ですから、教員の側がまず同性愛差別について正しく理解しなければならないし、生徒がそういう差別的な発言をすれば介入して、それはダメだと言わなければなりません。これが他の差別であれば、教師は大抵の場合、放置しないと思います。でも同性愛差別においては放置されてしまっている。そういうことに対する危機感はありますね。教員の中には、同性愛とトランス・ジェンダーの区別がついていない人も多いのが実情です。
学校ではなぜ、同性愛差別の問題について触れられないのか。そこにはいくつか理由があります。学校で差別問題を取り扱うべきかどうか、あるいは、同性愛者に対するからかいが差別なのかどうか、といったことについて、教師が迷ってしまっている部分もあります。しかし、やはり学校において教員は、現代社会に残る差別問題について積極的に考え、これを無くしていくよう努力する必要があります。そしてまた、同性愛に対するからかいは、それによって生きづらさ・息苦しさを感じている人たちが現実に多くいるという、明らかな差別の事例です。例えば人権週間の強調事項にも、「性的指向を理由とする差別をなくそう」というのが、はっきりメッセージとしてあるわけです。
こう考えると、学校で同性愛に対する差別についてきちんと正しい情報を伝え、差別的な発言が行われている現場を見たら、教員が介入して対処すべきだという結論になります。それが出来ていない大きな理由は、やはり教員の知識が乏しいからです。よく言い訳にされる言い方に、性に関することは学校で扱いにくい、というのがあります。でも、現実に起こっている差別によって、多くの生徒が息苦しさを感じているのに、教員らが全く無頓着であるという現状に、言い訳は許されません。確かに、いま学校の先生たちは、非常に忙しい。それでも、これは生徒たちの人権に関わる最優先事項なのだと認識を改めていくことで、セクシュアル・マイノリティに対する理解は、今後どんどん広まっていくのではないかと思います。学校が変われば、社会全体も大きく変わっていくはずです。
また私自身、教員として、差別によって息苦しさを感じる生徒だけでなく、誰かを傷つけてしまう側の生徒のことも考えたいという思いがあります。そのまま何も手を打たないと、知らず知らずのうちに「この世の中は異性愛者だけでできている」と思い込み、傷つける立場に回る危険性がある。最近、電通総研が行った調査では、約5%の人が自分をLGBTだと回答しています。つまり例えばTwitterでも、100人のフォロワーがいれば、そのうち5人はセクシュアル・マイノリティであるはずなのです。でもみんな、声をあげることができないでいる。普段そのことを意識しているかいないかで、SNSでの「つぶやき」一つをとっても、対応が変わってくるはずです。
傷つけられること、無視されることにはもう慣れている、というマイノリティも多いと思いますが、やはり気遣えるかそうでないかというのは大きいと思います。誰もが異性愛者だという思い込みを、週1回の授業によって少しでも変えたい。誰かは分からないけど、自分の周りに息苦しさを抱えている人がいるのだということに想像力がおよび、言動に反映できる人になって欲しい。そういう期待はしています。こんなふうに学校の授業を通じて、セクシュアル・マイノリティについての正確な知識を学ぶ人が増えていけば、この国も少しは生きやすくなるんじゃないかな。
ジェンダーについて話を戻せば、うちの学校に限らず、東大も京大も男子校出身者が多いでしょう。つまり官僚や企業トップのような、この国を動かしているような人たちについても、別学出身者が多いことになります。それゆえ、ジェンダーについてどうしても鈍感である人たちがこの国を牛耳ってしまう。そういう意味で、灘高校でこうした授業を行うことには意味があるのでは、と思っています。
―「国を動かす人たち」ということにも関連しますが、昨年12月の総選挙で、自民党が圧勝し、その裏で、自民党が「セクシュアル・マイノリティ差別に対する政策」に唯一消極的であったことが話題となりました。今後、マイノリティの人たちの生活に影響はあるのでしょうか。
確かに、何を言っているんだとは思いますが、正直なところ、政党としてどんな政策を立てるのも勝手だとは思います(笑)。問題は、それが争点にならないことです。自民党のことについても、報じたメディアは少なかったのではないでしょうか。アメリカのように、同性婚の是非をめぐって大統領選で激しくやり合うといった状況はあってもいいだろうと思います。アメリカに限らず、欧米の多くの国ではdiversity(多様性)という観点から、セクシュアル・マイノリティについて考える動きが年々強まっています。社会を活性化するためにdiver- sityが不可欠だという言い方がされている。
社会が活性化するかどうかは別にしても、現実問題として、多くの人が息苦しさを感じているのは良くないという思いが僕にはあります。セクシュアル・マイノリティについてもそうですし、ジェンダーの問題についてもこれは言える。他の国を模範にするわけではありませんが、日本の現状として、女性が活躍できず、セクシュアル・マイノリティが声を上げられない。その点、変えるべき部分はまだまだある。政策にしても、政党として何を言うのも勝手ですが、それぞれの考えを、もっとメディアが政治的イシューとして取り上げるべきだと思います。
―市民として求められることは。
市民というと大げさですが(笑)、やはりジェンダーやセクシュアリティの問題について敏感であってほしいと思います。気付かないかもしれないが、自分の身の周りにセクシュアル・マイノリティがいるという事実があり、もしかしたら自分も差別的な言動をしているかもしれない。そのことは常に念頭に置いてほしいですね。僕自身、一番仲の良かった人には、最後までなかなかカミングアウトすることができませんでした。仲が良いからこそ、言えなかった。その人が平気で同性愛について「からかい」的な発言をするものだから、余計に難しかったのです。
この記事を見ている人に考えてもらいたいのは、自分の友達の中に、セクシュアリティのことで悩んでいる人がいるかもしれないということです。例えば自らの同性愛を自覚している人たちは、日常生活の中で、それを誤魔化すのが非常に得意です。男性同性愛者の場合、彼氏のことを「彼女」と言えばよい。AV女優の名前だって、興味がなくても何人分かは覚えてしまいます。普段の会話からでは、誰が同性愛者なのか、誰がセクシュアル・マイノリティなのか、分かりません。それでも、男性同性愛者、女性同性愛者、あるいはトランス・ジェンダーの人は近くにいるし、それぞれの生きづらさを抱えています。そういうことについて敏感になってほしい。「誰が同性愛者なのか」と、探偵のようなまなざしで観察する必要はありません。そうではなくて、誰かは分からないけど、身近にいるんだと知っておいてほしい。
もし「自分はそういう人に会ったことがない、テレビの中だけの世界だ」と思っているのであれば、それはそういう態度をあなたがとっているからなのです。自分は同性愛者であることを受け入れるというシグナルが出てさえいれば、恐らくあなたに打ち明ける人もいるはずです。
また同性愛について、「可哀想な一部の人々」という捉え方も間違いだと思っています。あらゆる人はバイセクシュアルの可能性を持っているというのが僕の考えで、自分自身も性の思い込みにとらわれていないか問わねばなりません。誰にでも、同性に対して好きになる、憧れる気持ちがあるはずです。そういった自分の内側から聞こえる声にもう少し耳を傾けて、何も特別なことはないんだとみんなが思えるようになれば、だいぶ状況は変わってくる。そういうふうに思います。
―ありがとうございました。
まえかわ・なおや(灘中学校・高等学校教諭 ジェンダー・セクシュアリティ研究者)
1977年兵庫県生まれ。東京大学を卒業後、一般企業勤務を経て2005年に京都大学大学院人間・環境学研究科修士課程に入学。2012年に同研究科博士後期課程を単位取得退学。灘中学校・高等学校非常勤講師を経て、2007年より同中・高教諭(日本史)。専門はジェンダー・セクシュアリティの社会史。著書に『男の絆 ―― 明治の学生からボーイズ・ラブまで』(筑摩書房)、共著に『セクシュアルマイノリティをめぐる学校教育と支援』(開成出版)など。
セクシュアル・マイノリティの史学
―研究されている内容について、江戸・明治期に注目されるようになったきっかけは何だったのでしょうか。学部段階では、ジェンダーやセクシュアリティの研究はしていなかったのですが、学部を出た後に働いていた企業を辞めてから、このテーマについて研究してみたいと思うようになりました。元々歴史が好きだったこともあって、ジェンダー史に関する本を色々と読んだのです。
よく言われることですが、ジェンダーやセクシュアリティなど、現在の日本社会に存在している規範を相対化するには、場所や時代をずらしてみる方法が有効です。つまり諸外国ではどうなっているかという「比較」の手法と、他の時代はどうだったかという「歴史」の手法ですね。僕は外国語が苦手なので、「歴史」を選んだとも言えます。もっとも、こんな理屈は後から気が付いたんですが。歴史が好きで、ラッキーでした(笑)。
その後、人環の小山静子研究室に入ったのですが、それも京大を選んだというよりは、本を色々と読む中で小山先生の著作にあたり、目を開かれる思いがしたのですね。自分にとって大変分かりやすかっただけでなく、内容も興奮するものだったのです。「ああ、自分の知りたかった事が、ここに書かれている」と。小山先生は「良妻賢母」という規範について、主に研究されていました。女性のジェンダーが近代に入り、日本の教育の中でどのように構築されていったか、ということです。
そこで、同じように、自分が関心のあるセクシュアリティの問題についても、「なぜセクシュアル・マイノリティ、特に同性愛が排除されていったのか」ということを考えたいと思ったのです。自分の知識として、森鴎外の『ヰタ・セクスアリス』に描かれるような学生男色(明治時代のエリート男子学生などに見られた男色)のことなどがすでに頭にありましたが、そういうものがなぜ無くなっていったのか。そういったことを「歴史」として調べる。その「歴史」を調べることで、現在の社会の問題、自分たちセクシュアル・マイノリティが感じている生きづらさ、そういうのを解きほぐせるんじゃないか。それで近代史をやることにしたのです。
―江戸・明治期、あるいは戦国期においては同性愛に対する観方が寛容だった、という俗説が存在します。そのような俗説が伝えられてきた背景には何があるのでしょうか。
現在でも「江戸・明治期は男色に対して寛容だった」と言われていますが、実際に史料を調べていったところ、あまり寛容とは言えない状況でした。例えば明治期に入ってすぐに、改定律例と呼ばれる明治初期の刑法典によって「鶏姦(けいかん)」、すなわちアナル・セックスが懲役刑の対象となっています。このように、明治の知識人の間には男色を禁止しようとする価値観が存在しました。ならば、江戸時代には寛容だったかというとそうでもない。確かに、男色が流行していた時期はあります。それでも、あまり誇れるものじゃないよね、という観方のほうが、江戸時代を通じて強かったと言えます。
そんな中で常に語られてきたのが「男色は、昔は盛んだった」という物言いです。現在でもそうですし、明治時代には「江戸時代はさかんだった」と言われ、江戸時代には「戦国時代はさかんだった」とされた。要するに、常に「過去」のものとして語られてきた。それは同性愛というセクシュアリティを「過去」のものとして追いやってしまう、周縁化していくということです。近代において、「過去」のものはすなわち野蛮なもの、後れたものとみなされます。「過去」への周縁化を進めることによって、逆に現在のセクシュアリティが見えづらくなってしまう効果もあったのではと考えています。
―例えば戦国時代の男色の実態はどんなものだったのでしょうか。
正直、分かりづらいところが多いですね。戦場では男性の方が圧倒的に多いですから、そうした行為はわりと日常的に存在していたのかもしれません。ただ、現在のように「同性愛/異性愛」という分け方は存在しません。男色と女色(男性による異性愛)は両立するものだと考えられていました。極端に言えば、「今日はパンを食べよう、次の日はパンに飽きたからご飯を食べよう」というような感覚で、近世には男色と女色が語られていたりもします。
例えば、織田信長が同性愛者あるいは両性愛者だったという言い方をする人がいます。しかしそれはあまり意味のないことです。当時は男性とセックスするか、女性とセックスするかというのはあくまで行為の話であって、それがその人のアイデンティティを形成するという観方がそもそも存在していませんでした。歴史的に見ると、現代人が「男性とセックスする男性は同性愛者だ」というふうに思うことの方が、奇妙であるとも言えます。
―今のお話で、ミシェル・フーコー(1926―1984)が指摘しているように、近代以降「狂気」の概念が確立したことでいわゆる「精神病」が誕生したということを想起します。
そうですね、フーコーの議論は非常に参考になります。ただ、近代科学との関連で考えるなら、異なる点が一つあります。同性愛が性科学によって、「変態性欲」として周縁化されていったのは、日本では大正期になってからです。しかしそれ以前の明治期においても、すでに男色を周縁化する動きがありました。
先ほどお話した通り、まず明治時代になった直後に、大人の社会から男色は排除されていきます。そして、一部の男子学生の間で流行していた男色も、次第にダメだとされるようになりました。
第一に肉体的な関係が排除されました。学生男色というものが明治期に流行りましたが、これは一部の男子学生の間で、「お互いの成長」が期待できる関係としてイメージされていたもので、肉体的な接触を伴うケースも少なくありませんでした。女子学生に対する高度な教育が整備されていない時代、「智力の交換」や「大志の養成」は男子学生同士だからできるのだ、という考え方の延長線上に、学生男色があったのです。ところが、この学生男色について、肉体的な接触を伴うものはいけないという観方が1900年前後に出てきます。
そして1900年代に入ると、高等女学校が全国に整備されることで、教育を受けた女性が男子学生の前に登場します。この時期、男子学生が共有する大きなテーマとして浮上してきたのが「女学生との恋愛」や、そこから結び付く「結婚」です。この頃から、男子学生同士の親密な関係を表現する語としての「男色」や「男同士の恋」といった言葉が、力を失っていきます。それに代わって主流となったのが「友情」「朋友」といった言葉でした。特に「朋友」という言い方がよくなされています。この言葉を使うことで、男性同士の親密な関係を「異性愛」と両立できるものにした。女性との結婚、恋愛などと両立できるように、男子学生同士の関係の表現の仕方が変わっていったのです。
ですから単純に「科学」、日本の場合は大正時代における「性欲学」ですが、それがすべて悪いと言ってしまうのは、ちょっと違うんじゃないかと考えています。それ以前からすでに、男性同士の性的な接触は禁止され、排除されていたのです。
―著書にもお話がありましたが、明治時代においては男色が「上下関係に基づく関係」であったという観方があります。現代には「同性愛者は異性愛者をなりふり構わず狙っている」という偏見が広がっていますが、これは明治時代からの流れによるものといえるのでしょうか。
うーん……それらは別々のことではないでしょうか。明治時代の学生男色においては、年上が能動側、年下が受動側という年齢の上下関係があり、確かに明治時代の新聞なんかを見ますと、「不良学生による美少年狩り」があった、などと報じる記事があります。
ただ現代について言えば、「同性愛」というのはセクシュアリティにのみ注目した言い方であるというのが重要です。一人ひとりの同性愛者には当然、好きなタイプの人がいますね。であるにもかかわらず、同性愛者は同性であれば誰でも好きになるというようなイメージが、この言葉には貼りついてしまっているようにも感じます。
またセクシュアリティを非常に強調した言い方なので、その人がまるで24時間セックスのことばかり考えているかのように誤解されてしまう側面があります。でも、ヘテロの人を「異性愛者」だと言う時、ずっとその人が異性のことばかり考えているようには思いませんよね。同性愛者だって同じです。「生きづらい」、「自分はマイノリティである」ということを考えることはあるかもしれませんが、ずっと同性のことばかり思っているわけではない。当たり前のことですが、「腹が減ったな」だとか、「単位足りないな、どうしよう」、「明日1限出られるかな」といったことを考えている。それなのに、セクシュアリティを強調する言い方であるために誤った観方が広がってしまうのです。
また、「同性愛者が異性愛者を狙う」などという言い方がなされる場合に、念頭に置かれているのは男性だと思います。つまり、男性の同性愛者が男性の異性愛者を襲う、と。女性についてはあまりそういうふうに考えられていない。この背景には、男性には「性において能動であれ」というメッセージが働いているという、ジェンダーの規範があるでしょう。「草食系男子」という言い方が特別な意味を持つのは、男性は「肉食」であるのが当たり前だというふうに思われているからです。
ですから、「性に能動的である」男性が同性愛者であると分かった時、周りにいる男性を能動的に「狙う」のではないかと感じてしまう。それが男性の異性愛者にとっては一つの脅威と感じられてしまうわけです。自分は性において能動的であるはずなのに、同性愛者を前にすると、自分が受動側になってしまうのではないか、と。男性にとって、自分が誰かの性欲の対象になっているということは想像しにくいのです。だから、目の前の相手に男性同性愛者だとカミングアウトされると、思わずビクッと緊張してしまう。別に、君のことを狙ってるよと言われたわけでもないのに、ついつい身構えてしまう。「ノンケの自惚れ」なんて言われたりもしますけどね(笑)。
―女性同士の恋愛の例は、どれくらい記録されているのでしょうか。
明治期について言えば、全くないわけではないのですが、史料として残っているケースは少ないですね。
巌谷小波(1870―1933)という、明治時代に活躍した童話作家がいます。1900年から1902年まで、彼はドイツへ洋行に行きました。マグヌス・ヒルシュフェルト(1868―1935)というドイツの有名な性科学者によって、男性同性愛者の団体が立ち上げられたのとちょうど同じ時期でした。その会合に小波も呼ばれ、日本の男色について色々話してほしいと要請されました。帰国後、彼は『小波洋行土産』という本を著し、その中でヒルシュフェルトたちの団体についても触れています。この本で小波は「男子と男子との交接」を「男色」と表現しているのに対し、「女子と女子との交接」については「日本にはその事ありて、いまだその名無きがごとし」と記しています。
現在で言うレズビアン、つまり女性同士の同性愛は、当時「あることはある」と思われてはいたのでしょうが、まだはっきりとそれを指し示す言葉がなかった。「同性愛」が言葉として出てくるのは大正期に入ってからで、それ以降は女学生による同性愛なども頻繁に報じられるようになります。
「男の絆」が排除してきたもの
―海外では著名人が積極的に自身のセクシュアリティをカミングアウトしていることが多いように見受けられます。それに対し、日本では自身のセクシュアリティを意識した職業に就いている人が一部にいる一方、一切カミングアウトしない人がほとんどという、二極化した状況があります。そうですね。例えば欧米では、政治家はもちろん、学者や映画俳優、ミュージシャン、スポーツ選手など、同性愛者であることをカミングアウトしている人は大勢います。それに対し日本ではカミングアウトしている人が非常に少ない。これは明らかに、日本において同性愛解放が遅れている、つまりカミングアウトによる不利益が恐れられているということです。もちろん、研究やゲイ解放運動などを通じて自らが同性愛者であることをカミングアウトしている人はたくさんいますし、政治家でも地方議会では徐々に増えつつあります。それでも、まだまだ少ないと言わざるを得ません。
パトリック・リネハンさんというアメリカ総領事が大阪にいらっしゃいますが、彼はゲイであることを公表しています。カナダで同性パートナーと結婚式を挙げ、二人で日本に来られています。そのリネハンさんが、今の日本の状況はちょうど30年前のアメリカと同じだと仰っていました。つまり、映画にもなった有名なハーヴェイ・ミルク(1930―1978)ら地方政治家が出てきた段階であると。アメリカはその後、多くの紆余曲折を経て、自らの同性愛をカミングアウトする国会議員も出てくるようになりましたし、またオバマ大統領、クリントン元国務長官らも、同性愛に対する差別を無くすことがアメリカにとって非常に大きな課題であると明言しています。
日本だって30年ほど遅れてはいるけれども、そのステップを踏んでいることは間違いありません。ただ欧米諸国に比して、なぜこれほど遅れてしまっているのか。僕自身の見立てとしては、日本ではジェンダー差別の解消が遅れているということが、深く関係しています。男性のホモ・ソーシャルな結び付き、「男の絆」によって社会を独占したいという欲望が、日本にはまだまだ根強いわけです。こうしたホモ・ソーシャルな社会において男性同性愛者は、そこから弾き出されないように、自らのセクシュアリティを隠し続けようとします。自分が男性同性愛者であると言った瞬間に、所属しているホモ・ソーシャル社会から排除されてしまう。「俺たちは性を支配する側の立場であるはずだ。それなのに、お前は何なのだ」と。
日本は女性の社会進出が非常に遅れている国です。つい最近、女性の国会議員比率(衆議院)はわずか7・9%で、これは190カ国中160位台であると報じられました。つまり、いわゆる先進国の中だけでなく、世界全体で見ても最低レベルに位置しているのです。企業にしても、管理職の女性が非常に少ないことはご存知の通りです。このように、女性の進出を阻みながら、男性だけで社会を動かそうという欲望がこの国には根強く残っている。これこそが、多くの男性同性愛者がカミングアウトできずにいる最も大きな原因であると考えています。
一部のタレントさんのように、カミングアウトをした上で、かえってそれを「持ちネタ」にしている人たちについては、個々人によって考え方が分かれるでしょう。はっきり言えるのは、そういう光景を喜ぶ視聴者、テレビ局が存在しているということです。むしろメディアとしては、分かりやすい形のゲイの方が安心できるのだと思います。ゲイとはこのような人であるという偏ったステレオタイプを作り、それに沿った振り付けをさせている部分もあるでしょう。現実社会でゲイやレズビアンが息苦しい思いをしている、という社会問題に焦点を当てたとしても、視聴率がとれない。それよりは「ゲイのタレントがイケメン俳優に色目を使う」といった構図の方が、テレビ的には笑いの対象として成立しやすいということなのでしょう。
同じことはテレビ番組に限ったことではなく、普段の日常生活についても言えますよね。京大生でも普段の会話の中で、セクシュアル・マイノリティの人権について真剣に議論する場面とか、ほとんどないでしょう。それに比べれば、「ゲイ」や「ホモ」といった言葉を使って、笑いをとりにいこうとする場面の方が圧倒的に多いはず。残念ながら現在の日本では、こうした人権感覚のなさが一般的なものとなっています。メディアの責任も大きいでしょうが、それを受け入れている視聴者にも責任はあると思います。
そんな中、NHKの「ハートをつなごう」は、セクシュアル・マイノリティをめぐる差別や生きづらさに真摯に向き合っている、数少ない良心的な番組です。また、同じNHKの「障がい者情報バラエティー・バリバラ」では、障がいを持つ性的マイノリティが取り上げられる回もあります。民放でも同性婚などの話題を扱うドキュメンタリーが、少しずつ増えてきました。それでもやはり、同性愛が笑い・からかいの対象とされている番組のほうが圧倒的に多いというのが現状です。
ところで、「オネエ」タレントやゲイキャラを売りにしているタレントさんはたくさんいらっしゃると思いますが、レズビアンについては全くいないものとされているのではないでしょうか。テレビを見ていると、そのことに疑問を覚えることがあります。男性同性愛者より女性同性愛者のほうが息苦しさを感じているはずだ、というのが僕の考えです。
世界的には、レズビアンをカミングアウトしている女優さんやアーティストがたくさんいます。またThe L Word(邦題:『Lの世界』)というレズビアンやバイセクシュアルの女性たちを描いたテレビドラマなどもある。ただ、欧米諸国においてもレズビアンよりゲイのほうが目立っているというのも確かで、既存のジェンダー力学を反映しているように思います。
ボーイズ・ラブをめぐって
―「ボーイズ・ラブ」の普及は、「同性愛」を主要ジャンルの一つとして確立させました。書店では、いわゆる少女漫画と同規模のコーナーが設けられていることも珍しくなく、その産業としての力は非常に大きいものとなっています。「ボーイズ・ラブ」がこれほど広がるようになったのにはどのような背景があるのでしょうか。「ボーイズ・ラブ」が広がり始めたのは1990年代です。それ以前、男性同士の恋愛を描いたマンガ・小説は「やおい」や「耽美」と呼ばれていました。商業誌でこれらの作品を専門的に扱っていたのは『JUNE』という雑誌で、書店でも隅の方に置いてあって、いわば日陰の存在だったと言えます。同人誌の世界では、アニパロを中心にたくさんの作品が描かれていましたが。それが90年代に入り、一気に何冊もの商業誌が出版されるようになり、マーケットを広げていきました。今はそれが「定着」している時代にあたると思っています。
その背景にはいくつかありますが、一つには「女性が男性を見る」という構図が、以前に比べ一般的になってきたことが挙げられます。昔も今も、「男性が(性的な対象として)女性を見る」というのが基本的な構図であることに変わりはありませんが、「見られる男性、見る女性」という構図も少しずつ市民権を得てきました。ボーイズ・ラブに限らず、「ジャニーズ」や「韓流」についても、同様のことが言えるでしょう。例えば芸能雑誌『Myojo』の表紙に登場する被写体を時代ごとに分析すると、50年代の創刊当初は女性スター単体だったのが、70年代・80年代に「女性と男性の組合せ」に変化し、90年代半ばに「男性アイドルばかり」の表紙へと移行していきます。
また元々、文学やマンガの中で「男の絆」を称揚する空気があったわけです。『週刊少年ジャンプ』が「友情・努力・勝利」を旗印に掲げたように、男同士の友情を主題とする作品は、映画でも、テレビドラマでも、文学やマンガでも、それこそ星の数ほど描かれてきました。そしてマンガについて言えば、戦後に少年漫画/少女漫画と分化していった時に、少女漫画は「恋愛」を一つのメインテーマとして描くようになったという歴史的経緯があります。少年漫画の中では恋愛は取るに足らないもの、あくまで味付けにすぎないものとされたのに対し、少女漫画ではメインとされた。それは近代における性別役割分業観によって、「男性は社会に生きよ」、「女性は家庭のことをやれ」と唱えられたことと、深く関わっています。「恋」や「愛」は、女性化された概念として捉えられてきた経緯があるわけです。
そして、恋愛を描く少女漫画の伝統と、男の絆を称揚する少年漫画の伝統が結び合わさる中で出来てきたのが「ボーイズ・ラブ」作品であると僕は考えています。男の絆は、実際に当事者として巻き込まれるのは色々と大変そうだが、鑑賞者として外から見ている分には楽しい。「男の絆」から弾き出された女性たちが、「男の絆を鑑賞する」という戦略を編み出した。さらに、少女漫画は恋愛を描くのに長けている。ならば、こいつらを恋愛させてみるのはどうだ、ということで出来上がってきたのがボーイズ・ラブだと言えます。
ですから僕は、ボーイズ・ラブはある意味ではジェンダー規範の必然的な帰結の一つ、流行るべくして流行ったものだと思っています。当初は様々な抑圧の中で、あまり目立たないようになされてきたものが、90年代以降になってどんどん広がっていったわけです。ボーイズ・ラブは流行るべくして流行ったのに、男性がそのことで騒ぎ出しているだけなのかもしれません(笑)。
―ステレオタイプ的な観方ですが、ボーイズ・ラブを愛好する女性は「腐女子」と呼ばれ、例えば鉛筆と消しゴムなど、何でもカップルにしてしまうということがある種のネタとして言われることがあります。
まず「腐女子」という呼称について、自称なのか他称なのかという問題があります。自称として使う場合はともかく、他称としてこの呼称が持ちだされる場合には、やはり差別的なニュアンスがつきまとっているのではないかと僕は思います。
他称として名指される際、なぜボーイズ・ラブを愛読する女性たちが「腐女子」と呼ばれ、かつその行動が批判の対象となりがちなのか。批判されるリスクを察知しているので、ボーイズ・ラブを好む女性読者たちは自らのことを予め「腐女子」と自嘲しておき、「私たちは腐っているのです、放っておいてください」とバリアを張っておかなければならないというケースもあるように感じます。
ヘテロの男性が女性に対して性的な欲望を抱いている時に、そんなバリアを張っているでしょうか。2ちゃんねるやTwitterなどでも「ホモォ…」と囁くAA(アスキーアート)が流行ったことがあります。こんなふうに「腐女子」と呼ばれる女性たちは自嘲しなければならない。一方ヘテロ男性は、夜な夜な1時間も2時間もエロ動画を必死になって探していても、「エロォ…」と自嘲したりしませんよね。そういう非対称さにはやはり問題があると思います。なぜボーイズ・ラブが好きな女性たちは予め自分を貶めなければならないのか。なぜヘテロ男性は、夜な夜な動画を探す自らの滑稽さを笑わず、彼女たちだけを嘲笑するのか。この点を考えるべきではないでしょうか。
―一般的に、異性愛者男性が好んで読むものは「オタク文化」の中心に位置づけられ、それを専門とする批評家も現れています。これに対し、ボーイズ・ラブの批評をめぐる状況はどうなのでしょうか。
ボーイズ・ラブにも専門の批評家はいます。また三浦しをんさんのように、積極的にボーイズ・ラブについて発信している方も、ジェンダー研究者に限らずたくさんいらっしゃいます。
ただ、ボーイズ・ラブを読むという行為自体について、研究者たちが色々と語ろうとすると、ファンからは抵抗や批判がある場合も少なくありません。自分たちが楽しんで読んでいるものを、外部からあれこれ言わないでほしい、という気持ちはよく分かる。この辺りは、なかなか難しい所です。
ちなみに僕は、「なぜボーイズ・ラブを読むのか」といった問いの立て方はしません。むしろ問われるべきは、「なぜポーイズ・ラブを読むという行為が、これほど言挙げされるのか」だと考えています。
余談ですが、昨年末に雑誌『ユリイカ』でボーイズ・ラブの特集をした時、普段よりかなり売れ行きが良かったそうです(笑)。ですから、ボーイズ・ラブに対する評論はそれなりに求められているとも言えます。
―ボーイズ・ラブは然るべくして流行するようになったということですが、ガールズ・ラブ、いわゆる「百合」についてはどうなのでしょうか。
ガールズ・ラブ作品については僕自身あまり詳しくないので、答えるのは難しいですね。ただ一つ言えるのは、これまで女性同士の性愛は、基本的にヘテロ男性のためのポルノグラフィー、つまりアダルトビデオなどの中で扱われるケースがほとんどだった。それがいわゆる「百合」作品として漫画の中に取り入れられると、女性の読者も増えてきているという現象があります。依然、男性が性的消費の対象としている部分があるのも、間違いないのですが。これから注目していきたいところです。
―前川さんは勤務先の灘高校で、ジェンダー学を中心に取り扱う講座を開いているということですが、そこではどのような授業をされているのでしょうか。
これは「社会講座」という科目名で、高3の文系クラスの全生徒を対象に行なっています。この講座は週2回、大学入試とは全く関係のないことをやろうという趣旨で行われているものです。僕が担当しているのは「ジェンダー/セクシュアリティ」で、最初の2回でジェンダー/セクシュアリティに関する概論を説明し、その上で生徒たちに自由発表をしてもらいます。1コマ50分という時間的な制限もありますので、1回につき2名に、15分発表・10分質疑応答をやってもらう。そういうかたちで、ミニ・ゼミのようなことをやっています。生徒たちはかなり乗ってくれて、こちらから細かいことを説明しなくても、自ら色々な本を読み、主体的に発表してくれますね。
ジェンダーと就労に関する問題や、インドにおける女性差別問題など、かなり堅いテーマを扱う発表もありますし、あるいはサブカルチャーに関するものもあります。昨年は「男の娘」文化について発表してくれた生徒もいました。非常に面白い発表ばかりですし、僕自身刺激を受けています。また、生徒たちに聞いても楽しんでやってくれているみたいですね。受験生の6月、7月というのは忙しい時期だとは思うのですが、彼らは一生懸命準備をしてくれます。
―そのような授業をやろうと思うようになったきっかけは。
元々「社会講座」という、入試と関係のないものをやろう、という趣旨の時間が作られた時、僕は高校教員であると同時に、ジェンダー/セクシュアリティの研究者ですから、このテーマでやってみようと考えたわけです。最初の1年間は講義形式で行っていたのですが、やっているうちにむしろ生徒の発表が聞きたいと思うようになり、2年目からゼミの形式にしたところ予想以上にうまく行った。それで、今年も同じかたちで続けることにしました。
また、ジェンダーやセクシュアリティというのは身近なテーマであり、考えれば考えるほど社会とつながっていく問題です。僕が勤める学校は男子校ですので、このテーマについて全く知らないまま大学に進学していくと、自分が「男性」であるということによってどのような位置にあるのかに無自覚なまま社会に入ってしまう危険性があります。男子校の生徒にこそ、ジェンダーについての授業が必要だというのが、僕の実感です。
また中学校や高校では、同性愛差別の問題について、ほとんど語られないという現状があります。同性愛差別というのは、あらゆる種類の差別の中でも、最も日常的に起こっている差別の一つです。例えば、あからさまな部落差別や障がい者に対する差別の発言を、同級生や教員から聞くことは、今の高校生はあまりないはずです。でも同性愛差別となると、「お前ホモかよ、気持ち悪い」、「そんなにナヨナヨして、お前はオカマか」などと生徒も言うし、教員でさえ言ってしまう現実がある。クラスの中にはそれを聞いて、息苦しさを感じている生徒がいるのに。
ですから、教員の側がまず同性愛差別について正しく理解しなければならないし、生徒がそういう差別的な発言をすれば介入して、それはダメだと言わなければなりません。これが他の差別であれば、教師は大抵の場合、放置しないと思います。でも同性愛差別においては放置されてしまっている。そういうことに対する危機感はありますね。教員の中には、同性愛とトランス・ジェンダーの区別がついていない人も多いのが実情です。
学校ではなぜ、同性愛差別の問題について触れられないのか。そこにはいくつか理由があります。学校で差別問題を取り扱うべきかどうか、あるいは、同性愛者に対するからかいが差別なのかどうか、といったことについて、教師が迷ってしまっている部分もあります。しかし、やはり学校において教員は、現代社会に残る差別問題について積極的に考え、これを無くしていくよう努力する必要があります。そしてまた、同性愛に対するからかいは、それによって生きづらさ・息苦しさを感じている人たちが現実に多くいるという、明らかな差別の事例です。例えば人権週間の強調事項にも、「性的指向を理由とする差別をなくそう」というのが、はっきりメッセージとしてあるわけです。
こう考えると、学校で同性愛に対する差別についてきちんと正しい情報を伝え、差別的な発言が行われている現場を見たら、教員が介入して対処すべきだという結論になります。それが出来ていない大きな理由は、やはり教員の知識が乏しいからです。よく言い訳にされる言い方に、性に関することは学校で扱いにくい、というのがあります。でも、現実に起こっている差別によって、多くの生徒が息苦しさを感じているのに、教員らが全く無頓着であるという現状に、言い訳は許されません。確かに、いま学校の先生たちは、非常に忙しい。それでも、これは生徒たちの人権に関わる最優先事項なのだと認識を改めていくことで、セクシュアル・マイノリティに対する理解は、今後どんどん広まっていくのではないかと思います。学校が変われば、社会全体も大きく変わっていくはずです。
また私自身、教員として、差別によって息苦しさを感じる生徒だけでなく、誰かを傷つけてしまう側の生徒のことも考えたいという思いがあります。そのまま何も手を打たないと、知らず知らずのうちに「この世の中は異性愛者だけでできている」と思い込み、傷つける立場に回る危険性がある。最近、電通総研が行った調査では、約5%の人が自分をLGBTだと回答しています。つまり例えばTwitterでも、100人のフォロワーがいれば、そのうち5人はセクシュアル・マイノリティであるはずなのです。でもみんな、声をあげることができないでいる。普段そのことを意識しているかいないかで、SNSでの「つぶやき」一つをとっても、対応が変わってくるはずです。
傷つけられること、無視されることにはもう慣れている、というマイノリティも多いと思いますが、やはり気遣えるかそうでないかというのは大きいと思います。誰もが異性愛者だという思い込みを、週1回の授業によって少しでも変えたい。誰かは分からないけど、自分の周りに息苦しさを抱えている人がいるのだということに想像力がおよび、言動に反映できる人になって欲しい。そういう期待はしています。こんなふうに学校の授業を通じて、セクシュアル・マイノリティについての正確な知識を学ぶ人が増えていけば、この国も少しは生きやすくなるんじゃないかな。
ジェンダーについて話を戻せば、うちの学校に限らず、東大も京大も男子校出身者が多いでしょう。つまり官僚や企業トップのような、この国を動かしているような人たちについても、別学出身者が多いことになります。それゆえ、ジェンダーについてどうしても鈍感である人たちがこの国を牛耳ってしまう。そういう意味で、灘高校でこうした授業を行うことには意味があるのでは、と思っています。
―「国を動かす人たち」ということにも関連しますが、昨年12月の総選挙で、自民党が圧勝し、その裏で、自民党が「セクシュアル・マイノリティ差別に対する政策」に唯一消極的であったことが話題となりました。今後、マイノリティの人たちの生活に影響はあるのでしょうか。
確かに、何を言っているんだとは思いますが、正直なところ、政党としてどんな政策を立てるのも勝手だとは思います(笑)。問題は、それが争点にならないことです。自民党のことについても、報じたメディアは少なかったのではないでしょうか。アメリカのように、同性婚の是非をめぐって大統領選で激しくやり合うといった状況はあってもいいだろうと思います。アメリカに限らず、欧米の多くの国ではdiversity(多様性)という観点から、セクシュアル・マイノリティについて考える動きが年々強まっています。社会を活性化するためにdiver- sityが不可欠だという言い方がされている。
社会が活性化するかどうかは別にしても、現実問題として、多くの人が息苦しさを感じているのは良くないという思いが僕にはあります。セクシュアル・マイノリティについてもそうですし、ジェンダーの問題についてもこれは言える。他の国を模範にするわけではありませんが、日本の現状として、女性が活躍できず、セクシュアル・マイノリティが声を上げられない。その点、変えるべき部分はまだまだある。政策にしても、政党として何を言うのも勝手ですが、それぞれの考えを、もっとメディアが政治的イシューとして取り上げるべきだと思います。
―市民として求められることは。
市民というと大げさですが(笑)、やはりジェンダーやセクシュアリティの問題について敏感であってほしいと思います。気付かないかもしれないが、自分の身の周りにセクシュアル・マイノリティがいるという事実があり、もしかしたら自分も差別的な言動をしているかもしれない。そのことは常に念頭に置いてほしいですね。僕自身、一番仲の良かった人には、最後までなかなかカミングアウトすることができませんでした。仲が良いからこそ、言えなかった。その人が平気で同性愛について「からかい」的な発言をするものだから、余計に難しかったのです。
この記事を見ている人に考えてもらいたいのは、自分の友達の中に、セクシュアリティのことで悩んでいる人がいるかもしれないということです。例えば自らの同性愛を自覚している人たちは、日常生活の中で、それを誤魔化すのが非常に得意です。男性同性愛者の場合、彼氏のことを「彼女」と言えばよい。AV女優の名前だって、興味がなくても何人分かは覚えてしまいます。普段の会話からでは、誰が同性愛者なのか、誰がセクシュアル・マイノリティなのか、分かりません。それでも、男性同性愛者、女性同性愛者、あるいはトランス・ジェンダーの人は近くにいるし、それぞれの生きづらさを抱えています。そういうことについて敏感になってほしい。「誰が同性愛者なのか」と、探偵のようなまなざしで観察する必要はありません。そうではなくて、誰かは分からないけど、身近にいるんだと知っておいてほしい。
もし「自分はそういう人に会ったことがない、テレビの中だけの世界だ」と思っているのであれば、それはそういう態度をあなたがとっているからなのです。自分は同性愛者であることを受け入れるというシグナルが出てさえいれば、恐らくあなたに打ち明ける人もいるはずです。
また同性愛について、「可哀想な一部の人々」という捉え方も間違いだと思っています。あらゆる人はバイセクシュアルの可能性を持っているというのが僕の考えで、自分自身も性の思い込みにとらわれていないか問わねばなりません。誰にでも、同性に対して好きになる、憧れる気持ちがあるはずです。そういった自分の内側から聞こえる声にもう少し耳を傾けて、何も特別なことはないんだとみんなが思えるようになれば、だいぶ状況は変わってくる。そういうふうに思います。
―ありがとうございました。